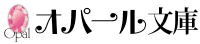すべては君のために 年下御曹司社長は鉄仮面女子をどうしても振り向かせたい 1
第一章
黎真(れいしん)テック本社十一階。
扱っている内容のせいなのか、法務部のオフィスに満ちる空気は常に緊張感を帯びている。
過剰に騒がしくなることも、気安い雑談が飛び交うこともない。社員一人一人が、目の前の案件と自分自身の判断力に向き合っている空間だ。
二課の主任である久慈詠子(くじようこ)は、その中でもひときわ異彩を放っていた。打ち合わせ用のテーブルに広げられた契約書類に目を通すその姿勢には寸分の曖昧さもなく、視線はまるで文字の奥に潜む意図を穿つような鋭さを帯びていた。
彼女の指先が迷いなく動き、付箋と赤ペンで整然と修正指摘を記した書類を揃える。その一連の動作には無駄がなく、静かな威圧感さえある。
整えた資料を、向かいの若手営業社員──佐原(さわら)の前に差し出した。
「お預かりしていた契約書をお返しします」
詠子の声は穏やかで、むしろ低めのトーンが耳に心地よい。けれどそこに感情はなく、あくまで事務的で必要な報告の一環に過ぎないという風情だった。
佐原は苦笑いと愛想笑いが入り交じった顔で書類を受け取った。
「えーと……これ、そんなにダメですか?」
その問いに詠子は少しだけ首を傾げる。その仕草に柔らかさはなく、応対に必要な最低限の動きだった。眼差しはすでにファイルに貼った赤い付箋の位置へと戻っている。
「ダメというより『曖昧すぎる』という印象です。特に第七条、責任範囲の文言は双方にとって危うい構成になっていますね。文面としての整合性は保たれていますが、運用面では問題が生じやすいと思われます」
「でも、相手は重要なクライアントになる見込みなんですよ。まだ確定してませんけど、向こう次第では長期契約になりそうなんです」
佐原が身を乗り出し、声を潜めて懇願してくる。言い訳じみた主張ではあるが、営業としての本音が滲んでいる。
「だから、あんまり条件を厳しくすると印象が悪いかなーって……」
数字に追われる立場として言いたいことは理解できる。けれど、それとこれとは別の話だ。
詠子はわずかに視線を伏せて言葉を選ぶ間を置いた。そして、落ち着いた声で言い放つ。
「でしたら、なおのこと修正が必要です。契約条件を曖昧にしたまま契約を結んでしまった場合、将来的に齟齬が生じた際にどこまで対応すべきか、責任を取るべきかが不明瞭になります。誤解が生まれる余地を残さず最初から明確にしておくべきです」
理屈の通った完全なる正論。だが、そこに余白はない。どこかで「落としどころ」を期待していたのだろう。佐原は口元を引きつらせながら書類を手繰り寄せる。すでに反論を諦めたような表情だった。
「……わかりました、直します」
「よろしくお願いします」
佐原は椅子を引いて立ち上がり、「曖昧すぎる」契約書を手にしながらぼそりと呟いた。
「はー、やっぱり『鉄仮面』は厳しいなー……」
あからさまな嫌味にも詠子はまったく動じない。視線ひとつ向けず、無言のまま自席に向かうとディスプレイの電源を入れた。まるでなにも聞こえていなかったかのような完璧なまでの無反応ぶりに、完全なる敗北を悟った佐原は肩を落として退室していく。
扉が閉まった途端、斜め前のデスクから朗らかな声が届いた。
「あーぁ、久慈さん、また営業に嫌われちゃったね」
声の主は綾部栞(あやべしおり)。黎真テックの企業弁護士の一人で、知的財産権の分野に精通しているので契約書の法務確認を頼む機会が多い。
飄々としているように見えて、仕事に対しては非常に冷静。特に訴訟リスクの分析に長けた人物として法務部内でも一目置かれている。
ほとんどの同僚は詠子の淡々とした態度に当たり障りのない会話しかできないが、歳が近いせいもあるのか綾部だけは臆さず話しかけてくる。むしろその徹底した線引きを面白がっている節すら感じられた。
詠子はモニターから目を離さず、平坦な声色で返す。
「問題が起きてからでは遅いので」
「まぁ……それはそうだよね」
それはこれまで何度も繰り返し使ってきた常套句だった。けれど、そのたびにどこかで、相手から「冷たい」「厳しすぎる」と思われるのだと理解もしている。ただ、それでも譲歩するつもりは微塵もなかった。
綾部は冷ややかな対応を気にした様子もなく、積まれた書類の上に頬杖をついてから「だけどさ」と続けた。
「久慈さんはちゃんと修正案まで提示してあげてるじゃない? ただ『ここが駄目』って言うだけじゃなくて、『こうすればどうか』までコメントを入れてから返しているでしょ。めちゃくちゃありがたいことなはずなんだけど、その気遣いをわかってない人、多いよね」
詠子自身は弁護士資格を持っていない。社員から預かった契約書を弁護士にチェックしてもらい、その評価をフィードバックすることを主な業務としている。
詠子はキーボードを叩く手を止め、手元の資料をたしかめてから再び視線をモニターに向けて文章を打ち始めた。
「それも仕事です。個人的な配慮でも優しさでもなく、業務の一環に過ぎません」
その言葉には過不足なく、何の温度も含まれていなかった。素っ気ないにもほどがある返答に綾部はふっと小さく笑う。
「そういうところ、ほんと偉いと思うよ。でも前職の法務部なんてさ、契約書に赤ペンでダメ出しだけして『対応はそっちで』が当たり前だったのよ。直し方を教えてくれる人なんていなかったし、そこまで法務が関わる必要はないって考え方が主流だった」
綾部は別の大手メーカーの法務出身で、二年前に中途採用で黎真テックに転職してきた。詠子の知る文化とはまるで違う世界の話に瞬きを一度だけして、短く相槌を打つ。
「そうなんですか」
「うん。だから、黎真テックの法務ってすごく丁寧だと思う。特に久慈さんみたいに私情を挟まずに、必要なことだけを正確に指摘してくれる人なんて貴重だよ」
あからさまな褒め言葉にも詠子は一切表情を変えず、返事もせず、ただ視線を資料に落とすだけ。そして綾部の電話が鳴ったことで会話は終わった。
その後も詠子は黙々とキーボードを叩き、メールの返信を済ませる。そして確認の済んだ資料を綴じるべくキャビネットへと向かった。
開けようと手をかけたガラス扉に映るのは──目鼻立ちのはっきりとした女性の顔。だがそこには感情の欠片すら見つけられなかった。
入社八年目の二十九歳、法務部主任である久慈詠子はある意味有名人である。
美人の分類に入るであろう顔立ちに高めの身長、姿勢のぶれない立ち居振る舞い。いつも冷静で、どんな相手にも感情を見せることはない。必要な言葉だけを選び、無駄を削ぎ落とした調子で告げるその様子は、ひとことで言えば「隙がない女」だった。
だが、その完璧さはしばしば誤解を生んだ。他部署からの相談にも淡々と指摘を返し、法務担当として正論だけを突きつける。笑って取り繕うことも、気休めを言うことも決してない。その態度は、まるで鋼でできた仮面を被っているかのように見えた。
『久慈さんに相談すると、全部論破される』
『感情が読めない』
『優しいんだか怖いんだか、正直よくわからない』
そんな声が、いつしか冗談交じりのあだ名となり、社員の間に広がっていった。
それが──「鉄仮面」。
しかし、詠子はそのあだ名を知った時もまったくの無反応だった。苛立つでも、傷つくでもなく、ただ淡々と受け止めていた。仕事に私情を持ち込まないのは当然のことだったし、何よりも、自分を取り繕ってまで好かれたいとは思っていなかったからだ。
(私は、課された仕事をこなすだけ)
詠子は自分にそう言い聞かせるとキャビネットの扉を開いた。
午後の穏やかな空気が流れる中、いつものように黙々と仕事を進めていた詠子は社内掲示板の通知に目を留めた。
ポップアップには「黎真マレーシア 役員人事のお知らせ」とある。
黎真マレーシア──正式表記は Reishin Malaysia Sdn. Bhd.。
黎真テックの海外子会社の中でも中核拠点であり、東南アジア市場の戦略を一手に担う重要な組織だ。
役員人事は把握しておく必要があるだけで、断じて気になるわけではない。誰にするでもない言い訳を心の中でしながら、詠子の指先はリンクをクリックしていた。
画面いっぱいに開いたお知らせには、整然とした文面が並んでいる。
【黎真マレーシア 役員人事のお知らせ】
このたび、黎真マレーシア(Reishin Malaysia Sdn. Bhd.)の役員人事につきまして、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
新代表取締役社長
鷹梁 聖央(現:事業本部長)
新事業本部長
森岡 俊介(現:企画部長)
管理部長交代
ジェームズ・リー(現:黎真シンガポール 管理部長)
以上
スクロールする手が、ある名前のところで止まった。
──鷹梁聖央(たかはしせお)。
詠子は眉ひとつ動かさず、画面を凝視する。胸の奥から懐かしい記憶の断片が静かに蘇る気配を感じたが、それを意識の表面まで浮かばせることはしなかった。
しかし背後で、不意に小さなざわめきが広がる。
「ねえ、見た? 鷹梁聖央がマレーシアの社長になるんだって」
「やっぱり鷹梁家の直系は出世が早いなあ」
すると、隣のデスクから男性社員が顔を上げ、補足するように口を開いた。
「いやいや、聖央は専務の息子だって。社長の甥だから直系じゃないよ」
「えっ、そうなんですか!?」
「私も、てっきり社長の息子かと思ってた」
「社長の息子は慎翔だけ。黎真USAの副CEOをやってるよ。でも、あの人はどうにも評判が良くないんだよなぁ」
男性社員が声のトーンを少し落としてそう言うと、椅子に深くもたれた。
するとその言葉を受けるように、女性社員の一人が声を潜めて続ける。
「そういえば聞いたことあるかも。『あの人が社長になったら黎真テックは終わる』って、結構前から噂されてるよね」
そんな中、綾部栞がタブレットを片手に席を立ち、数人の輪に近寄ってきた。彼女は淡々とした声で、しかし確信を持った口調で言葉を挟む。
「黎真テックってさ、昔から『次期社長はまず海外子会社の社長を経験する』っていう暗黙のルールがあるでしょ。だから今回の人事で、聖央が最有力候補になったってことだよね」
「そうなるね。だって、慎翔はすっごくやり手らしいけど……USAの離職率が跳ね上がっているみたい」
「うん。日本にもその件でレポートが上がってきてる。でも、本人は非を認めようとしないって話だよ」
周囲の社員たちは互いに顔を見合わせながら、小声で頷き合った。
黎真テックの将来を左右する人事ということもあって、法務部には珍しく軽い高揚感を帯びた空気が漂っている。
詠子はその様子を横目で捉えながらも、無関心を装って資料の確認を続けていた。だが、耳は自然と会話を拾ってしまう。
画面に映った「鷹梁聖央」の名前は、さっきから視界の端に焼き付いたままだった。
「聖央さんって今年で二十六だっけ? 若いけど優秀って評判だよね。彼が来てから万年赤字だったのが解消されたって話を聞いたことがある」
「うん。淡々とした感じだけど、頭の回転が速くて、めちゃくちゃ仕事ができる人なんだってね」
その言葉を最後に、詠子は画面に意識と視線を集中させる。
久しく見なかった名前が不意に現実味を帯び、詠子の胸に波紋を落としていった。
「そういえば久慈さんって、鷹梁聖央のこと知ってるんじゃないですか?」
唐突に水を向けてきたのは、法務部の若手社員・村瀬(むらせ)だった。まだ入社三年目だが部内では情報収集が早いことで有名だ。名前を呼ばれて一瞬だけ視線を向けると、興味津々といった様子でこちらを見つめている。
「普通の漢字の『高橋』聖央って名前で、昔インターンで来てたんですよね? たしか、久慈さんが指導社員の一人だったって聞いたんですけど」
「えぇ、そうです」
その一言に、周囲の視線が一斉に詠子へと向けられた。
無関心を装っていた詠子がキーボードを打つ手を止める。顔の位置も表情も変えないが、胸の奥底から懐かしい記憶が湧き上がってきた。
「えっ、そうなんですか?」
「それ初耳!」
驚いた様子で声を上げたのは、隣の席に座る別の女性社員だった。さらにもう一人、男性社員が会話に加わる。
「じゃあ、黎真テックの新卒で入ったわけじゃないんですね?」
「はい。本社からの出向ではなく、黎真マレーシアに現地採用枠で入社されています」
詠子は抑揚のない声で答えた。それでも周囲の社員たちは納得したように頷き、さらに質問を重ねてくる。
「で、久慈さん。彼はインターンの時からやっぱり優秀だったんですか?」
「そうそう、学生時代からすごかったんですかね?」
複数の声が重なり、小さな期待と好奇心が彼女のデスクを包む。
それでも詠子は、揺れそうになる感情を押し込み、淡々とした口調で短く返した。
「とても優秀でしたよ」
そう答えると、自然と会話は一段落した。けれど、彼女はキーボードを再び叩きながら、内心でひとりごちる。
(正確には『とても優秀だと後になって判明した』んだけどね……)
その言葉を胸の奥に閉じ込めたまま視線を画面に向ける。
けれど、わずかに鼓動が乱れていたことを、詠子自身ですら気付いていなかった。
五年前──。
黎真テックでは毎年、夏季に「汎用的能力活用型インターン」という二週間の集中プログラムを実施している。
総合重工業分野で国内トップを誇る同社では、いわゆる就業体験型ではなく、実際の業務課題を与え、企画・調査・提案まで行わせる実践重視の形式を取っている。
学生たちは特定部署に固定されるのではなく、複数部署を順番に回りながら各部門での実務に関わる。社員は持ち回りで指導役を担当し、そのフィードバックは最終日にまとめて人事へ報告される決まりだ。
詠子の所属する法務部も例外ではなく、その年は六名のインターン生の指導にあたることとなった。
インターン初日の月曜日。
広い会議室に六人の学生が並ぶ中、詠子は淡々と業務説明を進めていた。契約書の基礎知識や社内規定に関する簡単な講義、そして最終日に提出する課題の概要を伝える。
その時、ふと目に留まったのが──高橋聖央だった。
背が高くてがっしりとした身体つき、そして端整な顔立ちをしている彼はインターンの中でもひときわ目立つ存在だった。
だが、詠子の印象に残ったのは容姿ではなく、彼の表情の乏しさだった。
何を考えているのか読めない無機質な瞳。受け答えもしっかりしているが、どこか心ここにあらずな雰囲気を漂わせている。
彼らに与えた課題は会社の新規事業に関する契約書モデルのリスク分析。六人とも同じテーマだが、他の学生が積極的に質問し、メモを取り、試行錯誤している中、聖央は一人で黙々と課題に取り組んでいた。
仕上がりは可もなく不可もなく、教科書通りに整えられてはいるが、学生特有の独自性も工夫も感じられなかった。
だが──問題は別のところにある。
詠子が気になったのは、課題の出来ではなく彼の纏う「空気」だった。退屈そうに、あるいは面倒くさそうに時間を過ごしているように見える。
黎真テックのインターンは狭き門であり、ここまで来る学生たちは皆、何かを掴もうと必死だ。媚びへつらえとは言わないが、学ぶ姿勢を見せられない学生に付き合う義理はない──そう考えていた。
四日目の木曜日を終えても、その印象は変わらなかった。
他のインターン生は次々に質問を投げかけ、発表資料の準備を必死で進めているのに対し、聖央だけは最低限のタスクを静かにこなし、必要以上の関心を示そうとはしない。
(この状況は、彼自身のためにもならない)
そう感じた詠子は、五日目の金曜日、昼過ぎに社内グループウェアを立ち上げた。
件名:面談のお願い
高橋さん
少しお時間をいただきたいので、終業後に第六会議室までお越しください。
法務部 久慈詠子
送信ボタンを押してから、詠子はしばしディスプレイを見つめていた。
口調をどうするか、言葉をどこまで選ぶか、答えを探しながら業務をこなしていく。
このままでは、何も得ずに終わってしまう──そう自分に言い聞かせるように、詠子は終業時間五分前にこれまで聖央が提出してきたレポートを手に立ち上がる。
会議室のあるフロアへと歩みを進める足取りは、ほんの少し重く感じられた。
詠子は約束の時間より早めに会議室に到着した。扉を開けたまま中に入り、廊下に面している窓のブラインドをすべて上げる。
夕陽が差し込み、ロの字に並んだテーブルに柔らかな光が落ちた。詠子は一番奥の椅子に腰を下ろし、持ってきたレポートに目を落としながら聖央を待つ。
やがて、戸口に人影が現れた。
開け放たれた扉の前で彼は軽くノックし、「失礼します」と低い声で告げてから静かに扉を閉める。
詠子は扉に最も近い位置の椅子を指し示した。
「そちらに座ってください」
面談の内容は外に聞かれてよいものではない。だが、万が一の誤解は避けたい。
扉は閉めるができるだけ距離を取り、さらに廊下を通る人からも姿が見える位置で対峙する。セクハラやパワハラの誤解を防ぐため、詠子なりに考えた最善策だった。
促されるままに椅子に腰を下ろした聖央は、背筋を伸ばし、端整な顔をこちらに向けている。しかし表情からは感情が読み取れない。だが、それは詠子も同じだ。
無表情同士が向かい合う会議室に、わずかな緊張が流れている。
「急にお時間をいただいて申し訳ありません」
「いえ、気になさらないでください」
低く落ち着いた声で返され、詠子は小さく息を吐いた。時間は無駄にできないので早速本題へ入ることにする。
「まず、五日間を過ごしてみて、どう感じましたか」
聖央は一瞬だけ思案する素振りを見せ、口元に淡い笑みを浮かべる。
「非常に学びの多い時間です。社員の皆さんのレベルの高さを実感しましたし、自分の至らなさを痛感する毎日です」
模範解答だ──詠子はそう確信する。
インターンの教本に載っていそうなほど整った言葉で、欠点らしい欠点が見当たらない。だが同時に、そこからは聖央の気持ちはまったく伝わってこなかった。
彼にはなにか事情があるのかもしれない。しかし、そんなことは詠子には関係ない。
このインターンでは、各部署のエース級の社員が多忙の中、時間を割いて指導にあたっている。だからこそ、聖央の熱の感じられない態度には苛立ちを覚えずにはいられなかった。
「率直に申し上げます。これは私見ですが、高橋さんからは課題に取り組む意欲がまったく感じられません」
遠回しな表現を避け、単刀直入に伝える。
社員は真剣にインターン生と向き合っている。少しでも学びを得てほしいと願い、準備にも時間をかけている。その中で、彼の態度は他の学生たちの士気を削ぎかねなかった。
「研修内容に不足を感じているのであれば、インターンを辞退するという選択肢もあります。その場合でも、高橋さんの就職活動に不利になるようなことはしません。大学へはこちらからできる限りのフォローをするとお約束します」
詠子の考えを一気に伝えると、聖央はすっと顔を強張らせた。もしかして気分を害したのかもしれない。だが反論するでも弁解するでもなく、無言のままテーブルに視線を落としていた。
小さな会議室に重苦しい空気が漂う。数秒の沈黙ののち、聖央は静かに視線を上げた。
「私の振る舞いのせいで、皆さんを不愉快にさせてしまっていたのでしたら申し訳ありません」
彼の口から出てきたのはまさかの謝罪。意外な反応に詠子は一瞬だけ目を見開きそうになる。しかしすぐに表情を整えてから淡々と答える。
「不愉快になったわけではありません。ただ、心配をしているだけです」
聖央は深く頷き、まっすぐにこちらを見据えた。
「来週からは気を付けます。引き続き、ご指導よろしくお願いいたします」
「……わかりました。こちらこそよろしくお願いします」
互いにほとんど表情を変えないまま会話は終わったが、詠子の胸には、説明できないわずかな違和感が残っていた。
そして宣言通り──週明けの高橋聖央はまるで別人のように変わっていた。
課題に積極的に取り組み、疑問点があれば社員に質問し、インターン同士の議論でも率先して意見を述べる。
その熱意は、最初は指導担当の社員たちを戸惑わせたが、やがて同じ熱量で応えるようになっていった。
離れた場所からその様子を眺めていた詠子は、静かに安堵の息をついた。
(これなら最終日のプレゼンは期待できそうね)
表情には決して出さないが、自然と胸が高鳴るのを自覚していた。
プレゼンまで三日という時、詠子がインターンたちが研修室として使っている会議室の前を通りかかると、中から話し声が聞こえてきた。
何気なく足を止めた途端、耳に飛び込んできたのは自分の名前だった。
「法務の久慈さん、ちょっと厳しすぎると思わない? 私、話をするのが怖くて……」
声の主は神園彩葉。
広報志望のインターン生で、ふんわりとした可愛らしい容姿と人懐っこい笑顔が印象的な学生だ。男女問わず指導社員から可愛がられていて、詠子に対してもいつもフレンドリーに接してきていた。
だからこそ、思わぬ本音にじわりと胸が痛んだ。
(まぁ……嫌われるのも無理はないけどね)
「わかるー。課題のフィードバック、結構厳しいこと言うよね」
「法務だから仕方ないかもだけどさぁ、もう少し優しくしてくれてもいいんじゃないかって思う時あるよなー」
他のインターン生たちも次々に同調し、室内には不満の輪が広がっていく。
この話を聞くべきではない。詠子は立ち去ろうと一歩を踏み出しかけた。だが、その時低い声が割って入ってくる。
「私は……そうは思いませんね」
一瞬で室内が静まり返る。声の主は聖央だった。
「久慈さんは法務部という『間違いは許されない』環境で仕事をしています。だからその視点を伝えてくれているのではないでしょうか」
「えっ……? で、でもぉ…………」
淡々とした声なのに、そこには揺るぎない確信が籠っていた。彩葉が戸惑ったように言葉を探すが、聖央は構わず続ける。
「むしろ、これだけ現場に近い基準で接してもらえるのはすごく恵まれていることだと思いますよ。私は、久慈さんが指導社員としていてくれてよかったと感謝しています」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥がじんわりと熱くなる。
(……そんなふうに考えてくれていたんだ)
同僚でさえ、自分の仕事に対する姿勢をここまで理解してくれる人は少ない。まして、まだ学生に過ぎない彼からそんな言葉が出るとは思ってもいなかった。
泣きそうになるのを必死で堪え、詠子はその場をそっと離れた。
(ありがとう)
声にはならない呟きが、会議室の前で静かに消えた。
──だから、彼が黎真テックへ入社してくることを、密かに楽しみにしていた。
しかし、新入社員の一覧に「高橋聖央」の名前はなかった。その時の落胆は自分でも驚くほど大きかった。
とはいえ、彼ほど優秀な人物であれば、きっとどんな企業からも内定を取れただろう。もしかすると海外にでも行ってしまったのかもしれない──詠子はそう自分に言い聞かせて慰めていた。
結果的にその予想は半分だけ当たっていた。
それから三年が経ち、聖央のことなどすっかり忘れていたある日の午後のこと。詠子は社内グループウェアを開き、掲示板に新着通知が出ているのを見つけた。
タイトルは「海外子会社役員人事のお知らせ」。一応チェックしておこうと軽い気持ちでクリックした次の瞬間、スクロールしていた指が止まる。
──黎真マレーシア(Reishin Malaysia Sdn. Bhd.)事業本部長、鷹梁聖央。
添付されていた顔写真を食い入るように見つめた。
一瞬、別人かと錯覚した。だが、「聖央」という名前はそうそうあるものではない。写真に写っている、涼しげな目元と端整な顔立ちの青年は、間違いなくあのインターン生──高橋聖央その人だった。
(まさか……創業者一族だったなんて)
姓を「鷹梁」から漢字を変えていたのは、おそらく忖度を避けるためだったのだろう。そう考えると色々なことに合点がいった。
さらに略歴を目で追うと、黎真テックからの出向ではなく、黎真マレーシアに現地採用枠で入社していたことがわかった。
最も簡単な手段を使わず、あえて海外で勝負したということだ。その事実に不思議と「彼らしい」と思ってしまった。
それから何度か、メールのCC欄にお互いのアドレスが入った状態で連絡を交わす機会があったものの、直接的なやり取りは皆無だった。
だから、あのインターンの日々は記憶の奥底に封じられたまま、今日まで過ごしてきた。
そして現在──。
(まさか、あの彼が次期社長とはね……)
懐かしさと同時に妙な気まずさが湧き上がってくる。だが詠子はすぐに思考を切り替えた。
(まぁ、雲の上の人になったんだもの。私には関係ない)
そう言い聞かせると、いつも通り無表情を崩さず、淡々と目の前の契約書に視線を戻した。