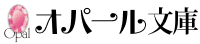崖っぷち若女将、このたびライバル旅館の息子と婚約いたしました。 3
第三話
この辺りの地理に詳しいとは本当だったようで、菖蒲はなんと試験開始三十分前にK大学の受験会場についていた。
耀一朗は菖蒲を降ろすと、握り締めた拳を菖蒲に向かって突き出した。
「頑張れよ。お前なら絶対に受かる」
「うん……ありがとう」
菖蒲はもう一度礼を言い門を潜ろうとし、直後にはっとして耀一朗を振り返った。
「日高、あなたの受験は大丈夫なの?」
耀一朗はニッと笑って今度はガッツポーズを作った。
「大丈夫、大丈夫。この街は俺の第二の故郷だって言っただろ? 俺のことは気にするな」
自転車をくるりと反転させ「じゃあな」と手を振る。
「あっ、そうだ。これで借りを作ったとか恩を返そうだとか思うなよ。俺がやりたくてやったことだからな!」
菖蒲の反論を待たずに自転車を加速させる。
菖蒲はその後ろ姿を曲がりで消えるまで見送った。
「……ずるいじゃない」
まだ心臓がドキドキしている。思えば大雪のこの日から、菖蒲の長い長い片思いは始まったのだ。
耀一朗は日高家に実に百年ぶりに誕生した男児だった。
日高家はどういうわけか娘ばかりが生まれていたので、耀一朗の誕生は奇跡であり祝福だともて囃された。
こうなれば耀一朗を日高旅館の大将にしようと、母の千晴が奮起するのも仕方なかったのかもしれない。当然、教育にも熱が入ることになる。
耀一朗もまず「月乃屋には負けるな」との日高家の家訓を叩き込まれた。「絶対に小百合さんのお嬢さんだけには勝ちなさい」と。
どうやら千晴は個人的にも小百合をライバル視していたようだ。
しかし、女将としての手腕は生涯小百合に敵わなかったようで、さっさと先に死なれあの世に勝ち逃げされたと悔しがっていた。
その分息子のお前が頑張れということなのだろう。「お前は男なんだから勝てるはず」などとなんの根拠もなく断言していた。
しかし、耀一朗は日高家や千晴の顔を立て、表向きには菖蒲と対立しているように見せかけていたが、内心はなんの意味があるのかと疑問を抱いていた。
正直江戸時代の家訓なんてもはやカビが生えて腐っているだろうとも思っていた。
無条件に家訓を受け入れられなかったのは、日高旅館の経営にそれほど魅力を感じていなかったことも大きかった。もっと広い世界を見てみたかったし、違う仕事をしてみたかったのだ。
一方、二つ下の妹の日和は幼い頃から日高旅館に愛着があった。本当は千晴の後を継いで女将になりたかったのだ。
日和はよくこう言っていた。
『お兄ちゃん、私も将来お兄ちゃんを手伝ってもいい? 私も旅館のお仕事大好きなの。本当は女将になりたいんだけど多分無理だし……』
耀一朗からすれば日和の方がよほど日高家当主に相応しかった。好きであることは最大の適性なのだ。
一度母に日和を女将にしてはどうかとさり気なく提案したことがある。
しかし、千晴は『あの子では菖蒲さんに勝てないわ』と断じ、二度とその話はするなと強引に話を打ち切ってしまった。
確かに日和はふわふわした娘で経営者に向いていないかもしれない。しかし、それは兄妹に施された不平等な教育の結果ではないか。
そう思うと次期大将としての期待を素直に受け入れられなかった。
かつて番頭を務め千晴を公私ともにサポートし、家族間のクッション役になってくれていた父親がもう亡くなっていたことも痛かった。
千晴の暴走を止められる者がいない。
一方でライバルであるはずの菖蒲は自分の進路になんの疑問も持っていないように見えた。将来月乃屋の女将となるべく汗一つ見せずに淡々と勉学に武道に励んでいる。
更に接客の際洗練された動きを取るべく、茶道と華道まで嗜んでいると聞いて、正直そこまでやるか⁉ と驚いたものだ。
一時は自分と同じ親に押し付けられているのではないかと訝しんだ。
耀一朗も日高旅館の手伝いをさせられていただけではない。将来経営に役立つ勉強しろとも言われていた。
だが、何事も特に努力せずとも簡単に、かつ要領よくこなせたのが不幸だった。
勉強は教科書を一度ざっと読めば頭に入るし、知識を自由自在に応用もできる。
運動もちょっと練習すればどの競技もできた。そのせいでよく運動部の助っ人を頼まれたものだ。
だから、逆にすべてがつまらない。
日高旅館の経営についても高校生になる頃には大体わかっており、それだけに千晴の手腕の欠点も見えてしまっていた。
同じ頃から母子の関係も悪化していた。問題を見過ごせずに経営に口を出すようになったからだ。
耀一朗からすれば無駄でしかないサービスを、伝統だと言い切って続け、結果営業成績も財務状況も悪化させる。信用しているからと経理のどんぶり勘定を長年放置する。
『おふくろ、一度帳簿を全部洗い直した方がいい。経理の沢(さわ)さんだけじゃない。料理長の原田(はらだ)さんの動きもだ。最近経費だっておかしな領収書が多すぎる』
しかし、千晴は『何を言っているの』と耀一朗の意見を一蹴した。
『そんなことをする必要はないわ。この仕事はお客様とのだけじゃない。従業員との信頼関係でも成り立っているのよ』
まして沢や原田らとは三代前からの付き合いである。そんな二人が日高旅館を、女将の自分を裏切るはずがないと。
ちっぽけな世界を狭い人間関係で維持しようとする千晴に嫌気が差した。だから、もうどうにでもなれと反発したのだ。
『じゃあ、勝手にしろよ。どうなっても知らないからな』と言い捨て、親しかった遠縁の独身男性、隆人(たかひと)の住む東京のマンションに家出した。
隆人は日高家の分家の出で千晴の従弟に当たる。この分家はホテル経営が主力の海陽館ホールディングスを立ち上げて成功しており、いまや日高旅館よりも規模がずっと大きくなっていた。
「――おふくろは馬鹿だ」
耀一朗はソファにゴロリと寝転びながら零した。テーブルにコーヒーを置いてくれた隆人に愚痴る。
隆人は苦笑しつつ向かいのソファに腰を下ろした。
「まあ、千晴さんは頑固だからな。人間、年を取れば取るほど考え方を変えられなくなっていくものだ。自分が間違っていたなんて思いたくないからね」
耀一朗にはそんな心境など知ったことではなかった。
「俺、やっぱり日高旅館を継ぐなんて嫌だ」
きっぱり言い切りデザイナーズマンションらしい剥き出しのコンクリート風の天井を睨み付ける。
「あんなところにいたら腐るだけだ。時代遅れでちっぽけでなんの進步もない」
ところがうんうんと聞いてくれていた隆人が、そこにだけは反論を唱えた。
「それはどうかな? 耀一朗、伝統を守り続けるには逆に時代の趨勢を読む能力が必要だぞ」
千晴のいい点をいくつか上げる。
「千晴さんって英語ペラペラだろう。今中国語も勉強しているそうだ。外国人の富裕層と話せるようになるために三十から英会話を始めたって聞いたよ。実際、それで質のいい外国人客が増えている」
「……」
その通りだった。
「耀一朗はなんでもできるからな。人の欠点ばかりが見えてしまうんだろうけど、千晴さんのそういう点は評価すべきだ。全方位で完璧な人間なんてそうそういないさ」
耀一朗は隆人と話すたびに自分の未熟さを思い知らされ、だからこそ隆人を信頼して尊敬していた。
だが、母や家族のことだけは身内だけに素直に聞き入れるのが難しい。
ふと脳裏に同じような立場にいる菖蒲の凜とした横顔が浮かぶ。
菖蒲は学校では家族については何も話さない。家庭内での問題にどう心の中で折り合いを付けているのか――。
菖蒲は弓道部の部長である。
毎日のように弓道場で練習に励んでおり、弓を引く姿の美しさが生徒たちの視線を惹き付けている。
その日も弓道場前に生徒が詰めかけていたので、なんとなく耀一朗もひょいと顔を覗かせた。
「あっ、日高先輩」
一応所属しているバスケットボール部の後輩までもがいたので呆れる。
「お前、こんなところで何をしてるんだ」
「僕も大月先輩のファンで……」
同じく弓道場を覗いていた何人かの女子生徒が黄色い声を上げる。
「えっ! 日高先輩! どうしてこんなところに」
「今度は弓道部に助っ人頼まれたんですか?」
「前の試合のスリーポイントシュート、すっごくかっこよかったです!」
どうも菖蒲とはファンが被っているらしかった。
適当に女子生徒たちを宥めて菖蒲が弓を射る姿を見つめる。
意志の強そうな黒い瞳には冷静と情熱が同居している。その視線に吸い込まれるように見惚れる間に矢が放たれた。
「的中!」
わっと声が上がる。
ギャラリーは盛り上がっているのに、菖蒲は落ち着いたままだった。「大月せんぱーい!」と呼ばれると微笑み返しはするが、感情の揺れがほとんど感じられない。道理で学校でクールビューティーと名高いはずだ。
なのに、自分に対してだけはやけにライバル心剥き出しかつ当たりが強いのは、恐らく大月家の家訓にも「日高旅館に負けるべからず」とでも記されているからだろう。
ふと、一度日高家と大月家の壁を取り払って話してみたいと思う。菖蒲の月乃屋に対する剥き出しの本音を知りたかった。
そして、その機会は思いがけなく早く訪れた。ただし、耀一朗と面と向かって話し合う形ではなかったが――。
二年生の三学期の終わりも近い頃、進路についての二者面談が行われることになった。
進学校ということもあってこの手の面談は一学期からたびたびあり、そのせいで大体の生徒はこの頃には進路がほぼ決まっている。
耀一朗もすでにW大学商学部を第一志望としていた。だが、その後どうするかまでは決めていない。
千晴と日高旅館にはうんざりしていたが、まだ身内の情もあるのでそう簡単に切り捨てられずにいた。
二者面談では進学先についてはもう決めてあるとだけ言っておいた。
「まあ、君の場合は僕が何かアドバイスするまでもないからねえ」
担任はそれで納得したらしく、一人当たり十五分かかるところが五分で終わった。
その後耀一朗はバスケットボールの練習をしようと体育館に向かった。しかし途中、机の中に宿題のプリントを忘れたのを思い出して立ち止まる。
引き返して教室のドアに手をかけようとすると、中から鈴を転がすような澄んだ、愛らしい声が聞こえたので思わず動きを止めた。
菖蒲だった。
その場から離れられなくなってしまう。ドアがわずかに開いていたのでこっそり隙間を覗き込むと、菖蒲と担任が向かい合って腰を下ろしていた。
面談は特別な事情がない限りは男女問わず五十音順で行われると聞いている。そのためもう菖蒲の分は終わっていると思い込んでいたのでドキリとした。
菖蒲は来たばかりらしく担任に礼を述べた。
「先生、今日は面談の時間を変更してくださってありがとうございます」
「旅館の手伝いって大変だね。お母さんと仲居さんたちの具合は大丈夫かい?」
「はい。なんとか回せています」
どうやら月乃屋でインフルエンザが流行って小百合と仲居、更に従業員の何人かが休んだため、菖蒲がピンチヒッターに入ったらしい。
「当分部活も休むことになると思います。授業も午後の授業は……」
「それはもうお父さんからも連絡が入っているし、ちゃんと許可を取ったから安心していいよ」
「……ありがとうございます!」
近頃千晴に反発して手伝いをサボっている耀一朗からすれば、菖蒲の月乃屋への献身は信じられないレベルだった。
一体何がそこまで菖蒲を突き動かすのだろう。
担任は「じゃあ、面談を始めようか」と話題を変えた。ガサガサ書類を捲る音がする。
「第一志望は私立……K大の商学部か。変わっていないね」
耀一朗は愕然としてその場に立ち尽くした。
菖蒲とは幼稚園から現在に至るまで同じ学校で、なんの根拠もなく大学も同じところに行く気がしていた。
ところが、菖蒲はK大学を受験するという。
当たり前だと思っていた存在がそばからいなくなってしまう――。
担任は耀一朗の気持ちを置き去りにして話を続けた。
「今のところは十分合格圏だね。ただ、ちょっと一つ気になっているところがあるんだ」
そこで言葉を切って菖蒲の目を覗き込む。
「大月さんだったらもっと上に行けると思う。T大や京都のK大を目指す気はないかい?」
「そこには商学部がないので」
「商学部にこだわらなくても経済でも、理数系でも旅館の経営には役立つと思うよ。もし他の道を目指すことになっても応用が利く。大月さん、熱海の外の世界は広いよ」
「……」
菖蒲はしばらく黙り込んだのち、「ありがとうございます」とポツリと告げた。
「期待してくれて嬉しいんですけど、無理だと思うんです」
「そうかなあ。大月さんは毎回テストで九割以上点を取っているし、全国模試も高順位だ。もったいないなあって思ってしまってね」
担任は残念で仕方がないのだろう。声に感情が滲み出ていた。
しかし、それでも菖蒲はぶれなかった。
「……T大やK大は私みたいに頑張って、頑張って、やっと今の成績を維持している生徒じゃなくて、教科書をざっと読んだだけで満点を取れるような、そんな人が行くところだと思うんです」
耀一朗は驚き目をわずかに見開いた。
菖蒲は確かに勉強にも部活にも手を抜く様子がない。しかし、何事もクールにすんなりこなしているイメージがあったのだ。
続いて耳に届いた凜とした声にはっとする。
「それに、私はやっぱり月乃屋の女将になりたいんです。熱海って観光だけで保っている小さな街かもしれません。でも」
菖蒲は言葉を句切った。
「地球って丸いですよね。世界の中心がどこかって、結局人間が決めているじゃないですか」
人差し指でトンと机を叩く。
「どこだって真ん中になれる。だったら、私にとっての世界の中心は熱海なんです」
世界はそこから広がっていると認識しているのだと。
「熱海からだって世界の広さはわかります。そして、熱海もそんな世界の一部だと思っています。私の世界の中心に世界中の人を集めるんですよ」
菖蒲はにっこり笑っていた。
「そうして月乃屋のファンをどんどん増やして、将来色んなところに別館が作れたら嬉しいですね」
「参ったなあ。もう何も言えないよ」
担任が苦笑している。
「あっ、もしかして英語がいつも満点なのは……」
「はい。ペラペラになって英語で接客できるようになりたいんです。英語が話せる外国人の従業員もいますけど、やっぱり女将自身が英語と中国語くらいは話せないと。日高旅館の女将さんはこれができるんです」
不意打ちで母の話になったので耀一朗の心臓がドキリと鳴る。
「日高旅館はライバルだけど、やっぱりいいところは見習わなくちゃ」
耀一朗は参ったなあと天井を仰いだ。
菖蒲は隆人と同じように千晴の長所を認めていたのだ。
そうか、これこそがプロ意識であり自分との違いかと目から鱗が落ちる。同時にやはり自分は旅館の大将には向いていないと思い知った。
(……カッコいいな)
女性に対してそう思ったのは初めてだった。その夢と情熱に敬意を抱いたのも。
後になって思い出してみればこの時にはもう菖蒲に恋に落ちていたのかもしれない。
菖蒲の二者面談を思いがけなく盗み聞きして以来、耀一朗は菖蒲が気になって仕方なかった。
一度面と向かって話してみたいと思ったが、何せ三百年に亘るライバルの家同士の長男と長女。
今更お友だちになりたいだのと抜かそうものなら、何が目的だと疑われるに違いない。下手をすれば変態、ストーカーと罵られそうだった。
ライバル視されるだけならまだしも、犯罪者扱いはさすがに精神的なダメージが大きい。
どうにかして接触できないかと頭を搾ったが、勉強のことならすぐ回転する頭脳もまったく役に立たなかった。
そうして攻めあぐねる中で春休みが終わり、耀一朗は三年生に進級した。
職員室前に張り出されたクラス分けを見に行った時には、生まれて初めてゴクリと息を呑んだ。
成績と志望校の難易度から考えて、恐らく自分も菖蒲も特進クラスだろうとは予測できていた。
しかし、絶対そうなるとも言い切れない。
だから相当緊張して見上げた張り紙の特進クラスのリストに、「日高耀一朗」と「大月菖蒲」の氏名を発見して思わずガッツポーズをしてしまった。
「ちょっとどいてくれる? 私もクラス分けのリストを見たいんだけど」
ところが喜びに冷水を浴びせるような冷ややかな、だが鈴を転がすような愛らしい声で指摘されてはっとして振り返る。
「大月……」
無駄に高い身長でリストを塞いでいたようだ。
一旦好意を自覚したからだろうか。ポニーテールにブレザーの制服姿の菖蒲は、眩しいほど可愛くキラキラ輝いて見えた。
平常心を装いつつ数歩横に移動する。
「悪い。ほら、入れよ」
菖蒲は耀一朗の隣に立つと、特進クラスのリストを見上げ、「……今年もあなたと同じクラスなの」と呟いた。
「これで三年間同じクラスってことね」
何気ない一言にちょっとときめいてしまい、こっそり横顔を見てみると、夜より深い黒い瞳には闘志の炎が燃えている。
「クラスのトップは譲らないわよ……」
やはりライバル視されているらしい。それにしてももうちょっと優しい表情ができないものなのか。
残念に思いながら観察を続けていると、ふとその大きな目の下に影が落ちているのに気付いた。
「大月、隈ができているぞ」
「えっ」
菖蒲は驚いたように頬に手を当てた。
「寝不足か?」
「……違うわよ」
耀一朗に指摘されたのが癪なのか、菖蒲は身を翻してその場から立ち去ってしまった。
菖蒲は昨年の三学期の終わりから午後の授業をたびたび休んでいる。
月乃屋ではまだインフルエンザが流行していて、菖蒲がピンチヒッターとして業務を手伝っているのだろう。
いくら努力家の菖蒲でも勉強と家業の手伝いの両立は無理があるのではないか。
果たして耀一朗の心配はそれから数ヶ月後の中間テストで、もっとも残酷な形で的中することになった。
高校三年生にとって一学期の中間テストは内申点を大きく左右する。特進クラスはもちろん、生徒は皆必死になって勉強する。
もっとも耀一朗にはいつもと変わらぬテストに過ぎず、一週間前にざっと教科書に目を通すだけで終わった。
テスト初日もいつも通り最初の十分で解答を終え、あとは見直しに時間を費やした。
それも間もなく終わってしまい、暇を持て余して何気なくクラスを見回す。
菖蒲は耀一朗の一つ前の席である。幼稚園から現在までの十五年間で一番近い席だった。
逆でなくてよかったと思う。テスト用紙も菖蒲から手渡されたし、こうして空き時間で密かに菖蒲を見つめていられるのだから。
(……ん?)
細い背中がぐらぐらと左右に揺れている。
体調が悪いのだろうか。
「おい――」
大丈夫かと尋ねる前に菖蒲の体が椅子ごとぐらりと横に倒れた。
「……‼」
耀一朗は電光石火の勢いで席から立ち腕を伸ばした。菖蒲の体が床に激突する前に片腕で抱き留める。
菖蒲の体は驚くほど柔らかく軽かった。
以前同じバスに乗った際、混み合っていたせいで体を密着させる羽目になったことを思い出す。菖蒲が結構なグラマーだったので、赤面した記憶があったが、今はそれどころではなかった。
いつもはツンツンしていても可愛いその顔は、まだ隈が目立ち真っ青だ。気を失っているのか瞼を閉じて意識もない。
時間を計っていた担任が慌てて駆け寄ってくる。テスト中のクラスはたちまち騒然となった。
「静かにしなさい!」
担任はスマホで校医を呼んだ。
「代理の先生もすぐ来るからテストは続けるように。五分延長する」
耀一朗は黙って見ていることなどできず、担任に「俺も手伝います」と声をかけた。
「でもね」
「もうテストの解答は終わっています」
担任は驚いたように耀一朗に目を向け、すぐに「じゃあ、頼む」と頷いた。
菖蒲を横抱きにして廊下に連れ出す。
間もなく校医が担架とともに現れ、担任と二人がかりで乗せて保健室に運んでいく。
校医はベッドに横たわる菖蒲を診察したが、ここには最低限の設備しかないので、病院に行った方が確実だと説明した。
「救急車呼ぶんですか?」
「ええ。私が付き添いますから、日高君はもう教室に戻って。テスト中だったんでしょう? 手伝ってくれてありがとう」
そう言われるともう何もできない。
後ろ髪を引かれながら退散するしかなかった。
それから丸々一週間菖蒲は学校を休んだ。
職員室を訪ねて担任に様子を聞いてみると、過労に加えて風邪をこじらせていたとのこと。やはり相当無理をしていたのだろう。
「あの、あいつ受験は大丈夫ですか?」
担任は椅子をくるりと回してかたわらに立つ耀一朗を見上げた。
「う……ん。大月さんは今までの成績がすごかったからね。そこまで響かないと思うよ。中間テストも見込み点が入るしね」
この高校ではテスト期間中に病欠した場合、点数は前回の七割をもらえることになっている。
しかし、七割ではクラスで五位以内は絶望的だ。今までずっと頑張ってきた菖蒲が落ち込まないか。
「……」
担任は耀一朗の顔をじっと見つめていたが、やがてニコリと笑ってA4サイズの封筒を耀一朗の胸に押し付けた。
「そうそう。テスト用紙とプリント類、大月さんの家に持っていってくれる? 確か歩いて十五分も離れてなかったね」
「は、はい……」
「じゃあ、頼んだよ。心配なんだろう? 一緒に育った幼馴染みだもんね」
担任が気を利かせてくれたのはありがたかった。正当な理由をもって大月宅を訪問できる。
管理の煩雑さから日高旅館内にあった自宅を手放し、今はマンションに暮らす日高家に対し、大月家は先祖代々同じ土地でこぢんまりとした趣味の良い日本邸宅に住んでいる。
恐る恐るチャイムを鳴らすと、インターフォンから「はい」と男性の声がした。
菖蒲の父親の幹比古だろうか。
日高だと名乗ると門前払いされそうなのであえて名乗らず、顔の代わりにカメラに向かって封筒を翳して見せた。
「俺、大月さんのクラスメートです。先生からプリント類を渡すように頼まれて……」
『ああ、はい。ちょっと待ってね』
年月で茶色みが増した木製の引き戸がガラガラと開く。
白髪で着流し姿の品のいい男性だった。
「ありがとう。わざわざ悪……って、君は日高旅館の息子じゃないか?」
秒でバレた。
しかし、ここでめげるわけにはいかない。
「菖蒲さんの具合はどうですか?」
この一週間心配で堪らなかったのだ。現状を把握しておきたかった。
「君には関係な――」
「関係あります。俺が担架で菖蒲さんを運んだんです」
幹比古の目がわずかに見開かれる。
耀一朗はそこで菖蒲は父親似なのだなと気付いた。顔立ちがよく似ている。それだけに躊躇したが、やはり言うべきことは言わねばならなかった。
「女将の修業は大事だと思います。でも、その前に菖蒲さんは高校生です。女の子で体力だってそんなにない。勉強に専念させてあげた方がいいと思います」
たとえ菖蒲が修業を望んだとしても、親ならまず我が子の体を気遣うべきだと訴える。
「最近、菖蒲さん元気がなかったんです。どうかお願いします。……それと今日俺が来たこと、あいつには絶対に教えないでください。多分嫌がるだろうから」
最後に深々と一礼し、返事を待たずに身を翻した。
「あっ、ちょっと君」
呼ばれても振り返ろうとはしなかった。
菖蒲が登校してきたのは翌週の月曜日のこと。
菖蒲が教室に入ってくるなり、皆一斉に彼女を取り囲んで質問攻めにした。
「体調もう大丈夫なの?」
「うん。ちょっと風邪引いちゃって」
耀一朗は素知らぬふりでクラスメートとお喋りしつつも、横目で菖蒲の様子をうかがった。
もう隈はなく顔色もよくなっているのでほっとする。
なんの気兼ねもなく菖蒲に声をかけられる連中が羨ましい。しかし、大勢のうちの一人になるのも嫌だった。
菖蒲はその日いつも通りに授業を受け、部活に顔を出して軽く練習し、一見特に落ち込んでいないようだった。
しかし、菖蒲が倒れるのを間近で目撃した身としては、また体調が悪くなりはしないかと心配でならない。
偶然菖蒲と帰宅の時間が同じで、その後ろをついていく羽目になった時には、「これはストーキングじゃない」と自分に言い聞かせた。家が同じ方向なのだから仕方ないと。
また倒れそうになったらすぐさま助けねばと心の準備をしておく。
菖蒲は耀一朗に気付かずどんどん歩いて行く。そして、人気(ひとけ)のないバス停の屋根の下で立ち止まった。頭上の時刻表を見上げている。
タイミングよく自分たちが乗るバスが来る。
ところが、菖蒲はその場に立ち尽くしたまま乗り込まない。見送ったのでどうしたのだろうと思って少し離れたところから見守っていると、やがてポツリとこう呟いた。
「英語はずっと百点だったのになあ……」
顔を伏せて目元を拭う。
「悔しい……」
耀一朗は堪らずに身を翻した。拳をぐっと握り締める。
日高家に生まれたばかりに菖蒲を慰める資格がないことが、この時ほど悔しいと思ったことはなかった。
------
ご愛読ありがとうございました!
この続きは9月4日発売予定のオパール文庫『崖っぷち若女将、このたびライバル旅館の息子と婚約いたしました。』でお楽しみください!