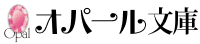崖っぷち若女将、このたびライバル旅館の息子と婚約いたしました。 2
第二話
早いもので今日が耀一朗の最終宿泊日である。
ようやく緊張感のある日々が終わる。ほっとするよりも寂しくなった。
耀一朗は現在東京でホテル経営に携わっているはずだ。今回の帰省終了後にはまた東京に戻るのだろう。
ただでさえ会いにくいのにまた当分顔を見られない。
そう思うとデザートのシャインマスカットとクリーム団子を運ぶ足が止まった。
(……何を考えているの。私は女将でこれは仕事。しっかりしなさい)
十六夜の間のドアをノックし、一礼して座卓にデザートを並べる。
「お食事はこちらで終了となります。お皿の片付けは九時を予定しておりますが、終わり次第ということでしたらフロントにお電話を――」
「――話がある。敬語はもういいから」
耀一朗は菖蒲に真っ直ぐに目を向けた。
「向かいに座れ」
座ってくださいでも座ってでもない、命令口調に、ついいつものくせでむっとしてしまう。
いけない、意地を張っている場合ではない。今この人はお客様なのだと自分に言い聞かせ、「ご用はなんでしょうか?」と質問で返した。
耀一朗はクリーム団子を一口で食べると、「うん、美味い」と頷いた。
「だけど、団子は前より味が落ちていないか。和菓子の取引先を変えたな?」
「えっ……」
その通りだったので目を瞬かせる。
「やっぱりそうか」
耀一朗はノートパソコンを取り出し起動させると、菖蒲に向け「見ろ」と画面を見せた。
しかし、そこに映っていたのは騎手を乗せた一頭の葦毛の競走馬だったので首を傾げる。背には紺色の布がかけられており、「イザショーブ」とプリントされているが、これは馬の名前だろうか。
「日高、この馬何?」
「ん?」
耀一朗は「おっと、ロック画面になっていた」とパソコンを操作した。
「俺、馬主やっていて、こいつがその馬。イザショーブっていい名前だろ。最近成績上げてきたんだぜ?」
「……馬主って個人で?」
「もちろん。さすがに俺の趣味に会社巻き込むわけにはいかないしな」
顧客にも馬主がいるので知っているが、個人が馬主となる条件は厳しい。
継続的に得られる見込みのある所得金額が、過去二カ年いずれも千七百万円以上あり、更に継続的に保有する資産の額が七千五百万円以上なければならないはずだ。
いくら日高屋の長男にして海陽館の社長とはいえ、この若さでそれだけの規模の資産があるとは――。
耀一朗は画面内のイザショーブを突いて見せた。
「こいつって牝馬なんだけど人間みたいな性格してるんだぜ。いつもツンツンしているくせに、気に入っている調教師にはデレデレ。俺には見向きもしないんだ。そういうところが気に入って馬主になったんだよな」
はて、誰かによく似た性格だ。しかし一体誰にと菖蒲が首を傾げる間に、耀一朗は改めてロック解除したパソコンの画面を見せた。
パワーポイントにデータが表示されている。
「これは……」
「俺を含めた覆面調査員の調査結果だ」
「なっ……」
ということは、耀一朗がミステリーショッパーであり見合い相手なのか。
この三日間もしやと思いつつも、「やっぱりそれだけは有り得ないわー。だってあの日高よ? 私に気なんてあるはずがないし」と結局否定していたのでなおさらぎょっとした。
だが、今はそれよりも――。
画面上のアプリには月乃屋の金の流れから長所、短所、すべてがずらりとグラフ化、文章化されている。
こんなデータを見せられると、菖蒲も席に着かざるを得なかった。
データには目の痛い指摘がいくつも並んでいた。
耀一朗は淡々とかつ容赦なく一つ一つのデータを読み解いていく。
「三千万円の赤字でキャッシュフローはトントン。借入金の元金も返済できてないだろう」
その上売り上げが落ちているので経費を削減しなければならない。
ライトブラウンの瞳が菖蒲の目を鋭く射抜いた。
「現状はお前のおふくろさんの小百合さんの代からなんじゃないか」
尊敬し、誇りにしている母の名を出されてカチンと来る。
「そんな。お母さんはこれでも利益を出していたわ」
「辛うじてだろう。小百合さんの経験と才能、カリスマ性でなんとかなってきたんだ」
「……っ」
菖蒲は膝の上で拳を握り締めた。
それではまるで自分が力不足と言われているようだし、実際そうなのだから反論しようがない。
悔しかった。
ところが、耀一朗は「お前のせいじゃない」と心を読んだようにぽつりと呟いたのだ。
「月乃屋にとっては時勢が悪いんだよ。最近熱海は復活したと言われているけど、若年層を中心に盛り上がっているだろう」
数年前のデータでは熱海に来る観光客は二十代がもっとも多く約二十三パーセント、三十代が十七パーセントを占めている。
「若いやつは大体そんなに金持っていないよな。一泊最低五万はする月乃屋みたいな旅館には泊まれない。温泉の大浴場があるもっと安いところを選ぶだろう」
確かにそうした視点で見ると、月乃屋を買収しようとしたセクハラマシュマロマン――不動産屋の社長の戦略は当たっていると言える。
スーパー銭湯なら若者のニーズを取り込んでいるので、客入りはよくなるだろうし、日帰り客や家族連れにも受けがいいだろう。
一方で月乃屋の客層は五十代、六十代、それ以上や常連客が多かった。
耀一朗が言葉を続ける。
「シルバー層は金を持っているから、そっちを取り込むべきだと思うけど、今のままではターゲットの年齢層の常連客も離れていくぞ。いや、もう離れたのかもしれないな。気付いているだろう」
これまた言い返せなかった。
小百合の代から月乃屋を贔屓にしてくれていた顧客の一部が、何も言わずに一年以上来なくなっている。
これらの顧客から新規客を紹介されることもあったため、それがなくなり売り上げに小さくはない痛手だった。
「なぜかわかるか? 月乃屋全体の質が落ちたのを見抜いたからだ。富裕層はいい変化にも悪い変化にも敏感なんだ」
はっきり指摘されると改めて心臓をぐさりと貫かれた心境になった。
経費削減のためにまず人件費を削った。修繕費を削り消耗品のクオリティを削り、料理の材料費を削った。
菖蒲もやりたくてやったわけではない。そうしなければ借り入れの返済ができなかったからだ。
耀一朗がそんな菖蒲をじっと見て繰り返す。
「でも、何度も言うけどそれはお前のせいじゃない。大月はよくやっている。経営には運やタイミングがあるってだけだ」
「……」
「小百合さんみたいな天才やカリスマにも欠点がある」
圧倒的な才能や魅力で組織の短所を補えてしまう。しかし、いざそのカリスマがいなくなればどうなるか。
「月乃屋に必要なものは名女将じゃない。客観的な視点と合理的なシステム。そして夢と情熱だ。お前はそれだけは誰にも負けないだろ」
「夢……?」
「そうだ。理想や方針とも言うな。従業員全員で共有するもので、それがないと誇りを持って働けない」
耀一朗は力強く頷いた。
「ただ月乃屋を復活させて維持したいだけじゃない。お前にも夢があるはずだ」
断言した。
「私の、夢……」
菖蒲は座卓に視線を落とした。
幼い頃から両親によく語っていたことがある。
『私、月乃屋を日本一の温泉旅館にするの! いつか世界中のお客さんに来てもらうんだから!』
最近は融資を受けるために金融機関を駆けずり回ったり、父の幹比古の病状を心配したりと多忙ですっかり忘れていた。
「思い出した……」
鼻の奥がツンと痛くなる。
しかし、耀一朗の前で泣くなど情けないし、みっともないし冗談ではないと、プライドにかけて堪えて顔を上げた。
「あなたもたまにはいいことを言うわね」
「俺はいいことしか言わないぞ」
耀一朗は腕を組んで菖蒲を見つめた。
「俺はプロのコンサルタントじゃないけど、それに近いことはできる。旅館に何が必要なのかをよくわかっている。月乃屋を立て直してみせてやる。だから大月、俺を選べよ」
耀一朗の言葉には嘘偽りの響きがなかった。心から月乃屋の力になろうとしてくれているのが感じ取れる。
「一体どんな風の吹き回し? 月乃屋が復活したら日高旅館に都合が悪いんじゃないの」
多少皮肉を込めた質問返しにも耀一朗は冷静なままだった。
「それはない。月乃屋も日高旅館も熱海の顔みたいなものだからな。潰れたらこの界隈全体がまずいんじゃないかと取られる。そんな事態は避けたい」
しかし、菖蒲はすぐに返事ができなかった。
「あなたの気持ちはわかったわ。ありがとう」
「そうか、なら――」
菖蒲は「待って」と話を止めた。
「確かに日高は仕事ができそうだし、婿に入ってくれれば月乃屋にはメリットがあるわ。でも、あなたには私と結婚してなんのメリットがあるの」
その疑問がどうにも解消できない。
「だって、あなたの実家にとっては私って敵組織の女ボスじゃない。裏切りだって日高旅館の女将さんが……千晴さんが反対するんじゃない?」
そう、日高旅館の女将である千晴の意見は無視できない。
「てっきりあなたはいつか日高旅館に戻るつもりなのかと思っていた。違っていたの?」
耀一朗は今こそ社長をやっているが、それは武者修行のためなのではと菖蒲は捉えていた。いずれその座を部下なり分家の親族なりに譲り、日高旅館に帰るのではないかと。何せ本家の長男なのだから。
となると、耀一朗が婿入りするこの結婚は日高旅館の跡継ぎを略奪することになる。
「……それは」
「家族の反対だけじゃない。あなたは今東京で仕事をしている。……月乃屋が人手不足だってことはわかっているでしょう」
菖蒲も嘘は吐きたくないので正直に話した。
「この縁談は婿という人手を確保するためでもあるの。だから別居婚も考えていない。でもあなたはそんな二足のわらじを履ける? すごく忙しくなるけど……」
耀一朗はぐっと押し黙ったがすぐに菖蒲の目を見返した。
「まず東京での仕事だけど、仕事大体はリモートでなんとかなる。一ヶ月に一週間くらいは東京にいることになるけど、それくらいなら大丈夫か?」
「え、ええ。一週間くらいなら……」
「だったら問題ない」
また、両親についても問題ないと答えた。
「おふくろについても気にしなくていい。うちはもともと女系だからな。日和があとを継げばいい。やっぱり日高旅館の顔は女の方がうまくいくんだよ」
日和とは耀一朗の妹である。菖蒲の高校時代の後輩でもあった。
日和はふんわりほのぼのとした少女で、更に菖蒲を憧れの先輩として慕ってくれたので、ライバル視する気にはなれずに今に至る。
耀一朗はそれにとライトブラウンの双眸に影を落とした。
「先祖の因縁だかなんだか知らないが、もうそんな形のないものに振り回されるなんてまっぴらだ。いい加減俺たちの代で断ち切るべきだ」
このセリフには菖蒲の心臓がドキリと鳴った。
ロミオとジュリエットのロミオのように、耀一朗も憎からず思ってくれていたのではないかと期待したのだ。
ところが――。
「そして、俺のメリットは女避けだ」
そう言い切ったので愕然とする。
「お、女避け?」
「あの手この手で迫ってこようとする女が結構いるんだよ。取引先の役職者の娘との見合い話も山ほど来てうんざりしているんだ」
耀一朗は心底鬱陶しそうな顔でそう言った。
その辺の男が同じセリフを抜かせばこの勘違い自意識過剰男がと突っ込みたくなるが、耀一朗ならそうだろうねと納得させるだけのスペックだからタチが悪い。
「だが、お前と結婚すれば妻は格式ある老舗旅館の女将。しかも美人だ。その辺の女が太刀打ちできる相手じゃない。お前と結婚したと知ればすぐに諦めてくれる」
「……」
女避けのためだと言い切られてここは悲しむべきなのか、それとも美人と褒められて喜ぶべきなのか判断できなかった。
だが、これ以上意地を張り続けていれば、二度と耀一朗と結婚する機会はないことはわかっていた。
覚悟を決めて小さく頷く。
「わかったわ。お互いの利益のために結婚しましょう」
本当は初恋の相手と結婚できることが嬉しくて堪らなかった。
でも、本心を知られて耀一朗に引かれたくないし、ずっと片思いをしていたと知られるのはなんだか悔しい。耀一朗にはいい女避けだとしか思われていないのに。
耀一朗はそんな菖蒲の心境を知るはずもなく再びパソコンの画面を見せる。
「よし。じゃあ、挙式と披露宴の会場を決めるか。披露宴は月乃屋を使うのでもいいな。いい宣伝になる」
「えっ、今日?」
「そうだ。候補をリストアップしている」
「もう!?」
さすが自他ともに認める仕事のできる男だった。
菖蒲は物心付く前から日高旅館だけには負けるなと言い聞かせられてきた。
『いい? 江戸時代からの家訓なの』
刷り込みとは怖いもので、幼い菖蒲は代々の大月一族と同じく、なんの疑問もなくその家訓を受け入れた。なぜそうしなければならないかという発想もなかった。
『わかった。お母さん、私絶対にあいつには――日高には負けない!』
この「あいつ」が日高耀一朗である。
なんの因果か――というよりは同じ地域にそれぞれの旅館も自宅もあるので当然だったのだが、幼稚園も小学校も中学校も同じ。
高校こそ進路が分かれるかと思いきや、結局同じ進学校だった。しかも同じクラスである。
先祖代々ライバルだった大月家の次期女将と日高家長男、そんな二人が一つ屋根の下で学校生活を送ることになるとどうなるか。
幼稚園ではどちらが早くひらがなを書けるようになるかで火花を散らした。結果は二者同時にすべて覚えたことで引き分け。
この時点で担任の教諭は二人が因縁のライバルだと気付いたのだろう。
運動会では二人を別々にするとまた過剰に競争心を抱くからと、同じ紅組となったものの今度は同じチーム内で玉入れの数を競った。これまた引き分けだった。
小学校、中学校も幼稚園と同じ流れになりやはり引き分け。
高校でも似たようなものだった。
――当時二人が通学していた高校では、試験後担任がクラスの上位五名を発表していた。
「大月菖蒲、斉藤菜々(さいとうなな)、高橋翔(たかはししょう)、日高耀一朗、松井里桜(まついりお)、――以上五名が成績上位者だ。頑張ったな」
発表が終わると生徒たちが一斉に溜め息を吐いた。当人たちに聞こえないよう声を潜めて噂し合う。
「やっぱり大月と日高が入っていたか。あの二人だけは絶対に落ちないよな」
「ねえ、どっちも学年で一位って聞いたけどほんと?」
「満点だって噂だよね」
十七歳の菖蒲はその時一番前かつ廊下側の席だったが、その耳はしっかりと生徒たちの囁きを捉えていた。
悔しさを悟られぬよう机の上の手をぐっと握り締める。
(満点じゃないわ。数学で二点足りなかった)
文章題で二点落としている。
(あいつは一体何点だったのかしら……。負けていたら冗談じゃないわ)
成績上位五名の氏名は発表されるが、個人情報保護の観点から総合点や順位は教えられない。それだけに気になって仕方なかった。
(次こそ満点を取らなくちゃ。満点だったら絶対に勝てる)
そのためには勉強時間を増やさなければならない。バイト扱いで月乃屋の手伝いもしているので疲れるが、耀一朗にだけは負けるわけにはいかなかった。
その日の放課後、菖蒲は校内の弓道場で弓を引いていた。背中まで伸びた長い黒髪を結い上げ、純白の弓道衣と漆黒の袴を身に纏って。
空気がピンと張り詰めている。
黒い瞳が印象的な凜とした横顔に、見学にやって来た男子生徒、女子生徒の双方の視線が吸い寄せられる。
菖蒲が風を切って矢を放つと、吸い寄せられるように的に向かっていき、見事当たった。
わあっと歓声が上がり静寂が破られる。
「すごい! 全部真ん中に的中した!」
「かーっこいい!」
「部長、さすがです!」
菖蒲は先輩後輩の絶大な信頼を得ているだけではなく、インターハイ代表になった功績を買われ、高校二年生で部長に任命されている。
まさに文武両道。際立った和風美少女であるのも相まって、全校生徒の憧れの的になっていた。
女子は皆某歌劇団の男役さながらに憧れていたが、男子はよこしまな観点から菖蒲を評していた。
「大月っていいよなあ。制服も似合うけどあっちの衣装の方がやっぱりいい」
「ああ見えて胸大きいしさ。脱がしてみたいよなあ」
「巫女服とかすっげえ似合いそう」
でもさと男子生徒の一人が溜め息を吐く。
「今のところ告白したやつ全員振られているんだろ?」
「あっ、お前もそうだったのか」
「ということはお前も? あー、付き合ってみたいよなあ。どんな男だったら落とせるんだろう」
一方、菖蒲はギャラリーの声には関心がなかった。男にもてるかもてないかなどどうでもよかったし、弓道についてはこの程度の成果は当然だと捉えていたからだ。
毎朝密かに誰よりも早起きして弓道場に来て、可能な限り練習しているので当然だと。
(大会でちゃんと結果を出すためにはもっと練習量を増やさないと)
――この通り当時の菖蒲はただプライドが高いだけではない。
負けず嫌いかつ大変な努力家だった。やるからには一番にならねばと、日夜勉強に、運動に、女将の修業に励んでいた。
その日菖蒲は珍しく早く部活を終わらせ、家路を急いでいた。二点落とした分を家で再確認し、次回こそ満点を目指そうと考えたのだ。
足早にバス停に向かう。
すると、耀一朗が老人の腰かけた車椅子を押していたので驚いた。停車中のバスに乗車させるつもりらしい。
運転手がバスの中から耀一朗に礼を言っている。
「ありがとう。助かったよ」
「いいんですよ。じゃあ、お爺さんお元気で」
耀一朗は介助を終えバスから降り、その後バスが走り去るのを見送った。
菖蒲はちょっと感動してその場に立ち止まった。
率先して体の不自由な高齢者を手伝うとは、簡単なようでなかなかできないことだった。
いやしかしと目に力を込めて耀一朗を見据える。
旅館業に携わる者ならホスピタリティは常時意識しなければならない。
耀一朗の行動は日高旅館の女将の教育のたまものだと思うと心の中で闘志の炎が燃え上がった。
さて、耀一朗は人助けの間スクールバッグはベンチに置いていたらしい。しかし端に置きすぎたからかどさりと音を立てて落ちてしまった。
ファスナーが開いていたのか中から教科書やプリントが零れる。
「おっと」
その中の二枚が風に流され菖蒲の足下に落ちる。
菖蒲は腰を屈めてそれを手に取り形のいい眉を寄せた。
一枚は数学の解答用紙、もう一枚は英語である。
数学は満点だった。
(……数学で負けた)
しかし、英語は九十八点。菖蒲は満点なので二点差で勝っていた。どうやら今回も引き分けだったらしい。
耀一朗が辺りを見回し落ちたバッグに気付く。
「拾ってくれてありがとうございます……って、大月!?」
菖蒲はつかつかと歩み寄り無言で解答用紙を差し出した。
「この問題はafterじゃなくてawayね。熟語だから頭で考えるものじゃない」
更に文章全体を読んで内容を完全に把握していなければ難しい。引っかけ問題の要素もあり、英語のテストで一番難しい問いだったのではないだろうか。
逆に言えば耀一朗はそれだけしか間違えなかったということだ。次は対策を取ってくるだろうから満点の可能性は高い。
負けられない。
一方の耀一朗は解答用紙を受け取りながらぼそっと礼を述べた。
「……ご親切にどうも」
ちっともありがたそうではなかった。
黒い瞳とライトブラウンのそれとの間で火花が散る。
一分後二人の乗るバスが停車しなければ、ずっと睨み合っていたかもしれない。
しかし、一時中断されたはずの戦いは、今度はバスの中で再開することになった。
その日は高校近くの競技場でなんらかの大会があったらしく、ジャージ姿の他校の学生でぎゅうぎゅう詰めになっており、否が応でも互いに体を密着させなければ乗れなかったのだ。
耀一朗の背に顔面を押し付けられる羽目になり、胸もぎゅっと押し潰されて呼吸が止まる。
「ねえ、もうちょっと前に行けない?」
「無理だって。というか、お前む……」
「? 何よ?」
「……いや、なんでもない」
人混みで蒸し暑いのか耀一朗の首筋がほんのりと赤くなっていた。
その後菖蒲は三年生となり、部活を引退し、やがて東京の大学に進学しようと決めた。
菖蒲としてはすぐにでも女将の修業に入りたかったが、父の幹比古に「大学は卒業しておいた方がいい」と勧められていたのだ。「これからの女将はちゃんと経済学や経営学を勉強しないとやっていけない」と。
菖蒲の第一志望校は東京のK大学の商学部だった。有名私大かつ難関ではあるものの、菖蒲の学力なら合格圏だと担任に太鼓判を押されている。
なお、耀一朗は東京のW大学の商学部を受験するとの噂だった。事実なら十八年目にしてようやく進路が分かれたことになる。
菖蒲は耀一朗と離れるかもしれないと知り、なんとなく物足りなさを覚えていた。妙な心境だった。
(どちらにしろ近い将来日高とは旅館の経営で競い合うことになる。それまでにちゃんと準備を整えなくちゃ)
そのためにもまず確実にK大学に合格しなければならなかった。
ところがよりによって受験当日、菖蒲は思いがけないトラブルに巻き込まれてしまった。
なんと東京に数年ぶりに大雪が降ったのだ。
菖蒲は前日熱海から上京し、最寄り駅のホテルに宿泊していたのだが、朝起きてカーテンを開けてみて目を見開いた。
「嘘……」
街が一面純白に染まっている。綺麗などと見惚れている場合ではなかった。
受験会場はここから更にバスで十五分の距離にある。大雪の影響で発着が遅れていたり、それならまだましでストップしていたりしたら大変だ。
慌ててバス会社に連絡を取ろうとしたが、考えていることは皆同じなのだろう。「ただ今大変電話が混み合っております……」といつまで経っても繋がらない。
それではとタクシーを呼ぼうとしたのだが、これまた同じ状況だった。
このままではらちが明かない。
菖蒲は制服に着替え駅に向かった。直にタクシーを捕まえようと考えたのだ。
ところが、タクシー乗り場には長蛇の列ができており、菖蒲に順番が回ってくるのは当分先になりそうだった。
ひとまず現状をスマホで担任に連絡する。
担任は『大学には僕から連絡しておく。とにかく落ち着きなさい』と宥めてくれた。
『そういう場合は開始時刻を遅らせると思うんだけど……』
「わかりました。ひとまず駅で待機しています。タクシーには乗れたら乗ります」
『うーん、タクシーも似たような状況だと思うけどねえ……』
菖蒲は電話を切りスクールバッグにしまった。
雪が次々と落ちるローファーを見下ろす。
地面が揺れている、いや、不安と緊張で心臓が早鐘を打ち、体が小刻みに震えている。
今まで努力と根性でハードルを越えてきたのに、生まれて初めて自分の力だけではどうにもならない事態に陥ったからだ。
胸を押さえて自分に言い聞かせる。
(大丈夫、大丈夫よ。落ち着いて。なんとかなるわ。精神統一しなくちゃ。弓道で鍛えてきたでしょう)
なのに、気持ちは一向に落ち着いてくれず、目の奥から涙が込み上げてきた。
(やだ、こんなことで。私がこんなに頼りなくて情けないわけ――)
涙を拭おうとしたその時のことだった。
「――大月?」
聞き慣れた声で名を呼ばれる。
涙に濡れた目で振り返ると、そこに宿敵の日高耀一朗が佇んでいた。やはり制服を着ている。
「ひ、だか……」
「お前も受験遅れそうなのか? って……」
耀一朗は目を見開いてその場に立ち尽くした。
菖蒲はライバルに涙を見せてしまったと気付き、慌てて拭おうとしたがもう遅い。
「こ、これは目に雪が入っただけ! 冷たくて痛くて……」
それよりと、キッと耀一朗を睨み付ける。
「どうして日高がこんなところにいるのよ。W大学は隣の区にあるんじゃないの?」
「俺の母方の親戚がこっちに住んでいて、そこに泊まらせてもらっていたんだ」
電車でW大学まで行こうとしたが、電車もダイヤが乱れていて役に立ちそうにないと。
「この分だとタクシーも無理だよな」
「……」
耀一朗も困り果てた顔をしている。
菖蒲はぎゅっと拳を握り締めた。
(こんなこと思っちゃいけないのに……)
耀一朗も同じ状況で同じ心境なのかと思うと、一人ではないのだと感じて少し嬉しかった。
ところが、耀一朗には菖蒲と決定的に違うところがあった。
土壇場で開き直れる度胸である。
「……そうだ!」
いきなり声を上げたので菖蒲はドキリとした。
「な、何?」
「ちょっと待て」
耀一朗は一旦その場から姿を消し、次に現れた時には自転車に乗っていた。
「その自転車はどうしたの?」
「そこのコンビニで自転車のシェアリングをやっているんだ」
一台借りてきたので後ろに乗れという。
「えっ、でも二人乗りって違法じゃ……」
「今日は多分交通事故だらけになるだろう。警察は俺たちになんて構っている時間なんかないぞ」
まだ戸惑っている菖蒲に苛立ったのだろうか。耀一朗は手を伸ばし、強引に菖蒲のスクールバッグを奪い取った。
「あっ」
「つべこべ言わずに乗れ」
「いっ、いい。私も借りてくるから」
耀一朗はまだ小刻みに震えている菖蒲の足下に目を向けた。
「そんな状態でか? ただでさえ雪が降って滑りやすくなっているんだぞ。転倒したらどうするんだ」
「……」
ぐうの音も出ない。
耀一朗は駅前の道路を見た。
「それにお前はこの街の地理に詳しくないだろう」
だが、自分は国道や下道、裏道まで把握しているのだという。屋根付きの道路や融雪剤が優先して撒かれる安全に通行できる道を知っていると。
「俺、東京来る時はいつもタカさん……さっき言った母方の親戚に世話になっているから。この街は第二の故郷みたいなものなんだ」
「で、でも……」
菖蒲はまだ意地を張っていた。
「あなたに私を助ける理由なんてないでしょう」
耀一朗が一瞬押し黙る。
ライトブラウンの瞳が強く光った。
「理由なんてなくていいだろう。お前が困っているから助けたい。……それだけで十分だ」
その一言に菖蒲の心臓がドキリと大きく鳴った。明らかに不安や緊張とは違う感情からだった。
いつもなら「それしかないのなら仕方ないわね」、などと憎まれ口を叩いていたかもしれない。
だが、その日はもう意地を張る気もなくなって、「……ありがとう」と礼を言って荷台に腰を下ろした。
「ちゃんと俺の腰に掴まっておけよ」
「わ、わかったわ」
「――よし! 行くぞ!」
雪交じりの風が菖蒲の頬を撫ぜる。ポニーテールにした長い黒髪が後ろに靡いた。
「ちょっとスピード上げるぞ」
熱海とは違うビルだらけの景色が次々と通り過ぎていく。だが、菖蒲の目にはほとんど入っていなかった。
頬を当てたブレザー越しの耀一朗の背は広い。手を回している腰もがっしりして、自分のものとは全然違っていた。
心臓がまた早鐘を打ち始める。
(どうか日高にバレていませんように)
受験に間に合うことよりもそればかりを祈っていた。