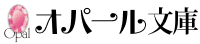結婚しよって言ったよね? 幼なじみ御曹司が私を一生溺愛する気です! 2
第二話
子供の頃は『おっきな家に住んでるなぁ』という大雑把な認識しかなかったし、成長するにつれて世の中を知った時には、
『ユキくんのお父さんって、九条グループの会長だったんだ。私、すごい家に遊びに行ってたんだな……』
と、全てが遠い昔のことになっていた。
貴公子のような容姿に、完璧なキャリアと家柄までついていると考えれば、さっきの女性たちの狂騒っぷりも納得だ。
――っていうかこれ、どこに向かってるの?
――普通に話すだけなら、わざわざバックヤードから移動する必要ないよね?
――どうしよう……。二人きりになった途端、すごく怒られたりして……。
エレベーターが止まり、ビクビクしつつ、案内された部屋に入った瞬間。
夕陽でロマンチックに彩られた光景に、思わず「わぁあ……」と感嘆を漏らしていた。
応接間兼、執務室だろうか。
広い室内は、十八世紀英国のジョージアンスタイルで統一されており、まるで貴族の邸宅だ。
左手にはローテーブルとソファー一式が、右手には装飾的な木彫りが施されたチェストと執務机が構えている。奥にはデザイン階段があり、吹き抜けの上階にいくつかドアが並んで、メゾネット仕様になっていた。各所に配置された照明は、燭台を彷彿とさせるブラケットライトだ。
「ここ……お仕事する部屋? ……それとも、スイートルームとか……?」
「ううん。執務室も兼ねてるけど、ここに住んでるんだよ」
「住……、え? ええ……!?」
階段の上に並ぶドアを見上げる。
もしかすると二階は住居で、ベッドルームやバスルームがあるのだろうか。
「住み込み(リブイン)の方が仕事に集中できるから。海外だと、一流ホテルの支配人は、家族でホテル内のレジデンスで暮らすのが一般的なんだ。一応マンションも持ってるけど、忙しくて……戻るのは年に数日かな」
「それって、二十四時間仕事漬けってこと……?」
「そうだね。部屋を出たら職場だし、いつ呼び出されるかもわからないし」
どんなに豪奢な空間でも、仕事場に寝泊まりなんて、休まる暇もない気がする。
「すごい……本当に、頑張ってるんだね。留学したって聞いた時もびっくりしたけど……」
「円香ちゃん、座って。ゆっくり話そ」
執務机の引き出しに手紙をしまった雪斗が、視線でソファーを勧めてくる。
円香は、覚悟を決めて腰掛けた。
でも一体、どう申し開きをすればいいだろう。
連絡を絶った本当の理由や、今も見通しのない苦しい生活が続いている、なんて事実をそのまま伝えて、反応に困る雪斗は見たくない。同情や憐れみなんて真っ平だ。
――とにかくもう、平謝りするしかないよね……。
――何を言ったって、結局は妬みが原因で、言い訳にしかならないし……。
雪斗はミニバーで二人分のウイスキーを注ぐと、一つを円香の前に置いて、向かいのソファーに座る――かと思いきや。
「……?」
隣に座られて、座面が揺れ、わずかに身体が傾いた。
もちろん、安物のソファーだからではない。本革の立派な造りだ。
つまり、近いのだ。
大人が悠々と三人は座れる大きさなのに、肩と太腿が触れそうな距離。
さりげなくスカートの裾を直すふりで、少しだけ距離を空けて、ちょこんと座り直す。
すると、雪斗も座り直して距離を詰めてきた。
――……? …………???
「嬉しいなぁ。こうやって並んで話すの、二十年ぶりだね」
雪斗はウイスキーを一口舐めてグラスを置くと、円香の顔をまじまじと覗き込んできた。それはもう、失礼なくらいに、ねっとりと。
「あ……、そ、そう……だね……?」
言われてみれば、確かにそうだ。
子供部屋でベッドに座って、図鑑や漫画を読んだ時と、同じ距離。
でも、今や雪斗の体格は、日本の成人男性の平均を大きく上回っている。
可愛いふわふわの子犬が、突然熊になってすり寄ってきたら、同じように仲良くするのはちょっと難しいと思う。
なんなら中身だって、さっきの女性たちへの対応を見るに、別人だった。
しかも――。
「円香ちゃん、昔も可愛かったけど……本当に、とっても綺麗になったね」
「え……」
麗しい顔面が、吐息が触れそうな距離まで近付いてきて仰け反った。
だってこれ以上距離を詰められたら、鼻先が、唇が、触れてしまう。
「ふふっ、顔が赤くなってて、可愛い……。そんな、そっぽ向かないで。綺麗な顔、もっとよく見せて?」
「ひっ……!?」
動悸を耐えるだけで精一杯だったのに、今度は胸元に落ちていた髪を耳にかけられた。
雪斗の太い指が耳の縁に触れて、ぞくっと震えが走り、頭が真っ白になる。
――……、……これ、って……?
――え……? 口説かれ……、……。
――いやいや……いやいやいや……? あれだけ女性に言い寄られてたのに、わざわざ偶然再会した私を、なんて、意味がわからないし……。
――……、あれ? でも。
――良平はユキくんのこと、『言い寄ってこない女を追いかけるのが楽しいらしい』って……、……?
冷静に考える隙を与えないのは、もしかしてナンパ術の一つなのだろうか。
硬直している間にも、更に刺激の強い言葉が襲いかかってきた。
「それで? 教えてくれる? 結婚しようって約束してたのに、どうして連絡、くれなくなっちゃったの?」
「は…………、え……? け、けっこん……?」
「うん。約束したよね?」
「えっと、……、だ、誰と、誰が……?」
今度は雪斗が、笑顔のまま固まった。
しばらく円香の顔を観察した後、少し焦った様子で続ける。
「まさか……忘れちゃったの?『ずっと一緒にいてくれる?』って確かめて、毎日約束したよね?」
「…………」
親密な距離に、強い酒に、歯の浮く褒め言葉。止(とど)めに、強引に持ち出された『結婚』というパワーワード。
間違いない。
やっぱり、口説かれている。
お得意の、女を落とす公式があるのだろう。
確かに、雪斗の言うような会話を交わした気もするけれど、六、七歳の頃の話だ。
子供にとっての『ずっと』なんて、せいぜい一ヶ月や二ヶ月、長くても一年くらいの認識だ。それを二十年越しに、全く釣りあいの取れない女に本気で持ち出すなんてありえない。もし本気で言っているなら、頭がどうかしている。
「どう? 思い出してくれた?」
必死の形相で、ぐぐっと顔を覗き込まれる。
いつの間にか、じりじりとソファーの端の端の端に追いやられて、逃げ場がなくなっていた。とうとう膝と太腿が触れあって、飛び上がりそうになる。
「えーっ……と……! い、いや……ど、どうかな~……? もう、子供の頃のこと、だし……」
――ど、どうしよう……どうしよう……。
――これもう完全に、罠にハマってるやつなんじゃ……。
雪斗を信じて、案内されるがまま、のこのこと部屋に足を踏み入れた数分前の自分を悔いた。
職場かと思ったが、ここはつまり、雪斗の自宅だ。
成人男性の家に連れ込まれたのと同義。
深い関係を許したと解釈されて、迫られても、仕方のない状況。
さっきエレベーターで、
『彼女は今晩の特別なゲストだから。明日の朝まで、部屋には誰も寄越さないで』
なんて、これ以上ないくらい怪しい紹介で納得していた副支配人と、彼女の値踏みするような視線を思い出す。
きっと、『はーん? 今晩はこの女と寝るのか』という呆れだったに違いない。
「円香ちゃん……? いいんだよ。責めたりしないから、なんでも素直に言って? 忘れられちゃってたのはショックだけど……。今日にあわせて数日休みを取ってるし、まだまだ夜は長いから。大事な約束、一緒に思い出していこ?」
「っ……、で……でも、ごめん私、そろそろ……」
雪斗はなんとしてでも、今晩の獲物を逃したくないのだろう。
いや。追いかける方が楽しいらしいし、逃げる姿勢を見せたことで、余計に火をつけてしまったのかもしれない。
そそくさと立ち上がろうとすると、雪斗はすかさず膝の上の手を握ってきた。
「ひ、っ……!?」
「ほら、こうやって……いつも円香ちゃんの手を握ってたのは、覚えてるよね?」
ごつごつした手指が絡んできて慌てて手を引いたけれど、恋人のように指を搦め捕られてしまう。
ふるふるふるっと、思い切り首を横に振る。
そんな記憶はない、断じてない。
服の裾や袖を握られるのはしょっちゅうだったし、時折触れることくらいはあったけれど、手は握られていない。絶対に。神に誓って。
「あれ……そうだっけ? 円香ちゃんが寝てる時に、こっそり触ったんだったかな?」
「ね……寝てる、あいだ……?」
「うん。円香ちゃん、他の友達と外で遊んだ後うちに来たから、時々疲れて、眠っちゃったでしょ? その時の寝顔が可愛くて……」
白くて細くて、天使みたいだった〝可愛いユキくん〟が、そんないやらしいことをするはずがない。
結婚という言葉をチラつかせるだけでなく、記憶にないことを捏造するのも、やり口の一つなのだろうか。
雪斗は思い出にかこつけ、手を繋いで拘束すると、止めに決定的なことを囁いてきた。
「とにかく……今晩は、帰さないから。円香ちゃんの話を聞きたいし、今日までの俺の気持ちも伝えたいし……二人きりで、一晩じっくりお話ししよう? ね?」
「あ……」
体温を染み込ませるように、ぎゅ、と強く手を握られる。
なんとか解いて、押し返さなくちゃと思う。
なのに、心のどこかで、嫌だと思っていない自分が――ドキドキしている自分がいた。
だって、優しい喋り方は間違いなく、円香の知っている雪斗だ。男性経験のない円香にとって、二十年間繰り返し思い出した男の子がこんな素敵な大人に成長して、情熱的に求めてくれるだけで、どうしたってふわふわした心地になってしまう。
それに、二ヶ月前に振られた恋人にだって、こんな甘いことは言われなかった。
それどころか、最後は――。
『恋人作る前に、その親父捨てるか、精神科にぶち込んでこいよ』
そう吐き捨てられた。
わかっていたのだ。泥酔した父の姿を一度でも見た上で、父ごと受け入れてくれる男性などいるわけがないと。
その後の、更に残酷な仕打ちまで思い出しそうになって――思わず息を止める。
――恋愛も結婚も諦めて、お父さんの面倒を見て。
――二度と、自分に与えられた人生から逃げないって決めたけど。
――このまま独り身なら、旅先で、一夜の思い出くらい……。
流されて男性と関係を持つなんて、想像したことすらなかった。
でも今日まで、弱音も吐かずに頑張ってきた。人生でたった一度羽目を外したって、罰(ばち)は当たらない気がする。
田舎に帰ったら、こんなに素敵な場所も、偶然の出会いもない。そして男女の噂はすぐに広まる。仕事柄、気軽に男遊びなんてもっての外だ。
――ユキくんなら……一度きりの関係でも、優しくしてくれる気がするし……。
「円香ちゃん? ちゃんと、自分の意思で残ってくれるよね? でないと……」
声がわずかに低まって、不穏な気配が漂った。
少し痛いくらい強く手を握られて――でも、手の平に滲んだ汗は、そのせいではなくて。
「……そう……だね。私もちょうど、気分転換したいと思ってたから。せ……せっかくの旅行だし? 地元じゃ、そんな羽目、外せないし……」
なんとなく、処女だと気付かれたら敬遠される気がして、慣れたふうを装ってみる。
でも、追いかけるのが楽しいらしい雪斗にとっては、面白くない答えだったのかもしれない。彼は目を眇(すが)めて、更に声を低めた。
「羽目を外す、って……? 何、それ……?」
もう少し、気のないふりをしてから誘いに応えた方が好みだったのだろうか。
でも、男を手玉に取ってきた百戦錬磨の女ならともかく、何もかも初体験で、心臓が破裂しそうなほど緊張している円香は、そのまま話を続けるので精一杯だった。
「ほ、ほら。こんな特別な場所に一泊なんて、良い思い出になりそうだし。今は恋人もいないからさ。そういうのも……いいかなって」
「……円香ちゃん。男と、遊び慣れてるの?」
声音から甘さが消えて、なぜか、詰問の雰囲気を帯びていた。
彼自身は手慣れた様子で部屋に連れ込んで、『結婚』なんて大仰な言葉まで持ち出して口説いておいて、わけがわからない。
「そ、そりゃあ……ユキくんだってそうでしょ? もう二十七だよ? 何もないなんてことは……ないでしょ。田舎だと、恋愛以外に楽しみなんてないし」
「何人?」
怒りを孕んだ、低い声。
淡い鳶色の瞳が、鋭く光った。
「な……何が?」
「何人の男とキスしたの?」
「え……」
「何人とヤった?」
「は、……」
かーっと顔が熱くなって、目が潤んだ。
そんなの、答えようがない。
そんな相手、一人もいないのだから。
そうでなくたって、あまりにデリカシーに欠けた質問だ。
「そっ、そんなの……言うわけないでしょ!? ユキくんには関係ないし……! なんなの? 勝手に部屋に連れ込んで、強引に誘ってきて、話に乗ったら今度は……っ」
「……わかった。もういい……」
遮る声は、小さかった。
気のせいだろうか。病弱だった頃を彷彿とさせる潤んだ瞳の中に、仄暗い影が揺らめいたように見えたのは。
「ベッドルームとバスルームは上にあるから。先にシャワー浴びてきて」
「っ……」
――待って、そんな、流れ作業みたいにするの……?
別に、愛情たっぷりに抱いてくれるなんて期待をしていたわけではない。
初めてだから、痛いのは怖いだけだ。
でももはや、そんな弱音を言える空気ではなかった。
思い出の〝可愛いユキくん〟は、もうどこにもいなかった。
バスローブに身を包んだ円香は、窓の外に意識を集中させて、この冒険を前向きに捉えようとしていた。
皇居が夜に沈み、その向こうには、ビル群の明かりが霞んでいる。
日没と共に暗闇に包まれる田舎ではお目にかかれない、眩い景色だ。
――私の予約したビジネスホテルじゃ、こんな夜景見られなかっただろうし?
――バスタブはジェットバス付きで、私の部屋より広かったし?
――アメニティはオーガニックの高級ブランドで、タオルもふっかふかで。
――……それになんでか……し、下着まで、めちゃくちゃ色っぽくて高そうなの、用意……されて、たし……。
「う…………、ううぅぅ……! や、やっぱりダメ……どうしよう……」
その場にへたり込みそうになって、ごつんと窓に額をぶつける。
――まあつまり、女性用の下着まで準備万端ってことは、しょっちゅうこうやって女性が泊まりに来て、遊んでるってことなんだろうな。それで……、……。
どんなに気を逸らそうとしても、意識は背後の――部屋の半分近くを占拠しているキングサイズのベッドへ向かってしまって、心臓が爆発しそうになる。
「ユキくん、やっぱり怒ってた……よね」
入浴後、この主寝室に案内してくれた時、雪斗の目からは光が消えていた。
その上、
『円香ちゃんがフロントで預けた荷物は、俺が許可を出すまで返さないように指示してあるから。お風呂に入ってる間に、さっき持ってたバッグも預かっておいたよ。もう逃げようとしても、無駄だからね……?』
と、宣言してきたのだ。
なんだか怖くなって、雪斗がシャワーを浴びる音がしはじめてからこっそり階下に降り、半泣きでバッグを探したが、忽然と消えていた。執務机の近くに大きな金庫があったから、その中にしまわれているのかもしれない。
――どうしよう……逃げられないって、何?
――勝手に人のものを取るなんて、どういうこと?
――でも……人を閉じ込めたら、犯罪だよね? ユキくんがそんなことするはずないし。私を連れ込んでるところ、副支配人さんとか、他のスタッフさんだって見てるし。
――バッグと荷物……さすがに、明日は返してくれるよね?
貴重品はもちろん、着替えすらない状況はかなり心許ない。いくら出入りは自由でも、ナイトウェアやバスローブ姿でホテルの外に出るわけにはいかないし、閉じ込められたも同然だ。
――咄嗟の勢いで、遊び慣れてるふりしちゃったけど……途中で処女ってバレて、もっと怒らせちゃったらどうしよう……。
そんな恐怖から連鎖して、ついまた、二ヶ月前の嫌な記憶を思い出してしまった。
初めてのデートを終えた後、彼は家まで送ってくれた。
昼食をご馳走になったお礼に『少しお茶を飲んでいく?』と誘ったのがいけなかった。
玄関を開けると、求職活動で外出しているはずの父が、
『円香! 久し振りに俺が夕食作ったぞ。この間、グラタン食べたがってただろ――』
と酷い酒の匂いをまとって現れたのだ。
父は泥酔すると、円香を離婚した妻と混同し、支離滅裂なことを言って悲しみに打ちひしがれるのが常だった。
だからこの日は、初めて男性を伴って帰宅した円香を見て、元妻に裏切られた日のことがフラッシュバックしたのかもしれない。
隣に立つ恋人を見た途端、絶望に表情を変えて、
『なんだ……なんだお前! 俺の……俺の妻を奪いやがって! どうせ幸せにできないんだ、下心しかないくせに!』
と錯乱し、恋人に掴みかかったのだ。
『何言ってるの!? お父さん、やめてっ……やめてよっ』
どんなに酔っても暴力とは無縁だった父が初めて見せた姿に驚きつつ、円香は必死に父の背中にしがみ付いた。
『なんでこんな奴を庇うんだ! ろくな男じゃない! 不倫だってわかってながら、よくも……! うちには子供が二人もいるんだぞ! 子供たちまで傷つけて……、っ……』
もちろん、泥酔した父と素面の若い男では、喧嘩にもならなかった。
彼が父の手を払うと、よろめいて倒れ込んだ父に巻き込まれて、円香も玄関に尻餅をついた。
彼は軽蔑を露わに見下ろしてきて、それから――。
『なんなんだよ……。こんなイカれた父親がいることを黙ってたなんて詐欺だろ。人を騙す女にうちの子を任せるなんて無理だわ』
元々、父が依存症であることは伝えてあったのだ。
でも、想像と現実があまりにもかけ離れていたのだろう。
『しかも、実家の近くから離れたくないとか言ってたよな? それ、今後も親父の面倒見る気でいるってこと? 恋人作る前にその親父捨てるか、精神科にぶち込んでこいよ』
それで解決するなら苦労はしない。
昔、飲み過ぎて救急車で運ばれた時に措置入院となったこともあるが、入院が必須の状態が続かない限り、どんなに長くても三ヶ月で退院することになる。それならグループホームへの入所をと思っても、父は頑なに病を認めない。
とにかく、交際はそれで終わったが、彼の気持ちは治まらなかったらしい。
後日、円香の働く幼稚園に通っている園児の保護者に、
『うちの子はもう卒園したけど、栗原先生の父親は重度のアルコール依存症で、酔って園に乗り込んで暴力を振るいかねない。子供に万が一のことがあったら……』
と言いふらしたらしいのだ。
すぐに園長に呼び出されて父の問題を確認され、更に、
『今まで残業中に突然帰宅することがあったのも父親が原因では?』
と指摘され、それでは困ると詰(なじ)られた。以降、同僚もあからさまに冷たくなり、辞職に追い込まれた。
でも円香は、父を責めようとは思わない。
父は、母を溺愛していた。
記念日には必ず花を贈って、いつも母と円香をお姫様扱いしてくれた。
『俺が出張でいない間は、お母さんを助けてやるんだぞ』と育てられた。
今も、酔って円香を元妻と勘違いすると、
『なあ、俺に何が足りなかったんだ、なんでも言ってくれ……。戻ってきてくれるなら、なんだってする。もっと仕事を頑張って、稼いで……』
と、泣きながら眠りにつく。
そんな父を見て、いつからか、『自分は母のような女にはならない』と思うようになった。
父を、家族を捨てて、恋愛や結婚を――男を選ぶことだけはしない。
何があっても父に寄り添うと決め、依存症について勉強し、父が病気を否定するのは脳活動が低下しているのが理由で、寛解後も一生の付き合いになる病だと知ってからは、父との衝突も減った。
ここ数年は、依存症家族の会に参加して悩みを共有し、父を見守ることに徹している。
今回も落ち込みはしたけれど、運良く次の仕事が見つかったから、この旅行で命の洗濯をした後は、また淡々と日常を送るつもりだ。
ただ、それだけ割り切ってもなお、異性への憧れが残っているのは、人間の業の深さだろうか。
「はは……、学生時代は恋愛どころか、友達もできなかったし……。いわゆる〝拗らせてる〟ってやつなのかな……」
――でも、前の彼が現実を教えてくれたから、もう結婚を夢見ることはないし。
――きっと今晩のことは、いい思い出になる……はず。
何十回目かの溜息を吐いた時、ドアが開く気配がして、飛び上がるように振り向いた。
円香と同じ、バスローブ姿。
半乾きの前髪を掻き上げる様はとんでもない色気で、心臓が止まりそうになる。
でも相変わらず、不機嫌な表情だ。
雪斗はテーブルの上を見ると、鋭い目を更に細めた。
「食事……美味しくなかった? もし不満があれば、料理長に伝えておくよ。嫌いなものとか、アレルギーはあったっけ?」
「う、ううん……! サンドイッチ、すごく美味しかったよ。でもさっき、会場で色々食べちゃったから、お腹いっぱいで……残しちゃってごめんなさい」
嘘だ。
お腹は少し空いていたけれど、寝室に用意されていた軽食は、まるで、
『セックスのために腹ごしらえをしておけ』
と言われているみたいで、どうしても喉を通らなかった。
「そう? ならいいけど……」
雪斗は、あっという間に距離を詰めてきた。
はだけたバスローブの間から、逞しい胸筋が覗いている。
少しでも動悸を落ち着けたくて昔の面影を必死で探したけれど、白くてひょろひょろだった幼少期とは、欠片も重なるところがない。探せば探すほど、以前との違いに気付いて、ドキドキしてしまう。
視線の圧を受け止めきれず、夜景を見るふりで背を向けてみたものの、すぐに後ろから抱きしめられてしまった。
「っ……!」
「……なんでそうやって、逃げるの? やっぱり、嫌になった? 円香ちゃんから誘ってきたのに」
両腕で閉じ込められたまま、耳元で囁かれるだけで全身にビリビリと痺れが走って、身体が震えてしまう。
「さ、誘ってきたのは……ユキくんでしょ。それに、嫌だったら、抵抗してる……」
「……そうだよね、もう他の男に気持ちいいこと教わって、幸せにしてもらったんだもんね?」
声変わりした低音は冷たく、見知らぬ他人のようだ。
表情を確認したかったけれど、窓ガラスに映り込む雪斗の顔は夜景の光と重なってよく見えない。
「そ……そうだよ。言ったでしょ、そのくらい……」
「円香ちゃんは、気軽に誘ってくる子とは違うと思ってたのに」
「ひぁ、っ……」
責めるように耳を嚙まれて、そのまま千切られる予感に竦み上がる。
けれど軟骨に優しく歯が食い込んだ後は、唇で食まれ、舌が耳の中に滑り込んできた。
「ぇあ……!? ぁっ……! や……、耳、は……くすぐった……」
全身がぞくぞくっと痺れて震え上がる。
思わず押しのけようとした手を取られ、振り向かされた。
長い睫毛(まつげ)に縁取られた瞳が、どんな変化も見逃すまいとばかりに見つめてくる。
顔が熱い。きっと真っ赤になっている。
電球色の間接照明だけだから、気付かれていないと思いたい。
「そ、そんな、見ないでよ」
「ごめん。でも……この二十年想像してたより、ずっとずっと……綺麗だから。もっとよく見たい」
今日まで、男性から『綺麗』だなんて言われたことはない。
ただの雰囲気作りだとわかっていても、つい真に受けてしまって、動揺を苦笑で隠す。
「……ありがと。女の子喜ばせるの、ほんと、上手になったんだね?」
雪斗は悲しげに目を細めた。
何か言いかけて――でも、諦めたように口を閉ざした。
静かに、どこか怯えた様子でゆっくりと顔が近付いてきて、覚悟をして息を止める。
初めてのキスは、想いあう恋人とするものだと信じて疑わなかった。
でも、違和感や嫌悪感は一切ない。
心の通わない、形だけのキスのはずなのに、柔らかい感触と優しすぎる触れ方に、知らない愛しさと感動が込み上げて驚いた。
――よかった……。
――どんなに見た目が変わったって、やっぱりユキくんは、ユキくんのままなんだ。
――喋り方も、笑顔も。昔から、この感触や触れ方と同じくらい優しくて。
――おかげで私は、毎日ユキくんの部屋で、寂しい気持ちを癒やされてたんだから……。
「っ……、ふ、っ……」
分厚い舌が入ってきて、きゅっと身体に緊張が走る。
それをわかっているのか、雪斗の両手が腰を引き寄せて、逃がす気はないと伝えてきた。
「ん、っ……」
舌と舌が吸い付くような感触に、心から求められていると誤解してしまいそうで、ちょっと怖くなる。
――私も舌、動かした方がいい? じっとしてた方がいいの?
――ユキくんを、気持ちよくしてあげたいけど。
――どうしよう、わからない……。
意識すればするほど唇と舌が強張って、慣れたふりどころではない。
でも雪斗は訝(いぶか)しむこともなく、顔を傾け、キスを深めて、舌先で溶かすように愛撫してくれた。
「っん、ぁ……ぅ、……」
雪斗は口内を隅々まで愛撫しながら、腰のくびれを撫ではじめる。
バスローブ越しに脇腹を擦られたり、背骨を上下に辿られると、次第に身体の奥にまで作用して、あっという間に息が上がった。
「っ……ぁ……ユキく、それ、っ……んんっ……!」
顔を逸らして、待ってと伝えようとしたのに、すかさず唇にかぶりつかれてしまう。
――なんで……? 撫でられてるだけなのに、変……。
「ん、……ん、っ……!」
舌と舌の摩擦が生じるたび、無意識に甘い鼻声が漏れる。
じわじわと体温が上がって汗ばみ、緊張が解けて、とうとう膝から力が抜けはじめると、雪斗の腕が力強く支えてくれた。
――なに、これ……。キスって……ただの触れあいだと、思ってたのに……。
――頭の中、ふわふわで、ぽーっとして……舌も唇も、擦れるの、きもちいい……。
――こんなの、ずっと、続けられたら……。
――へんに、なる……。
どのくらい続いたかわからない。
いつの間にか与えられる感触に夢中になり、自ら舌を差し出し、雪斗の背中に縋り付いていた。
そんな円香の変化に気付いたのか、雪斗の触れ方は次第に遠慮がなくなって、息苦しさに仰け反っても、すかさず身を乗り出してくる。
しばらくは受け止めようと努力したが、思うように息を吸えず、震える指でバスローブを引っ張ると、ようやく離れてくれた。
「っは、っは……はぁ、ぁ……」
頭がぼうっとして、身体が熱い。
舌先と唇が、じんじんと痺れている。
「……はじめてなのに……一緒に見た漫画より、エッチなキス……しちゃった……」
「ん、っ……!」
雪斗の声が遠い。涙で霞んで、どんな顔をしているのかも認識できない。
濡れた唇の上を、雪斗の指が滑っていく。
「円香ちゃん、俺のキス……ちゃんと、気持ちよかった? 下手じゃない? ……円香ちゃん?」
「んぁ……、な、に……?」
舌にはまだ雪斗の感触と痺れが残っていて、上手く動かない。
甘い余韻に犯されている円香は、気付けなかった。
雪斗が子供の頃と同じ、自信に欠けた瞳で、おずおずと見下ろしてきたことには。
そして自分の蕩けた顔が、雪斗に過剰な自信を与えてしまったことにも。
「っ……、キスでぽーっとしてるの、可愛すぎる……!」
「ふぁ、っ……! ぁ……!?」
突然、耳元から首筋にかけて、甘えるように繰り返し吸い付かれてよろめき、ガラス窓に背中がぶつかった。
鼻先を擦りつけ、すんすんと匂いを嗅がれ、歯を立てて甘噛みされると、きゅうっとお腹の下が引き攣って体温が上がっていく。
「っ……! だめ……あと、つけないで……っ、こ、恋人同士じゃ、ないんだし……!」
家に帰って、万が一父の目に留まったら、また動転しかねない。
押し返すと、雪斗は思い詰めた表情で言った。
「……キスマークすら嫌なの? 本当にただ、セックスして、気持ちよくなりたいだけ?」
「そ、そんな言い方……きゃああっ!?」
雪斗は突然屈み込んだかと思うと、円香の腰をひょいと抱き上げた。
落ちる――と身構えたのに、やすやすと左肩に担がれて、ベッドに下ろされる。
「っ……、なっ、なっ……」
何が起きたのかわからなかった。
だって昔は、円香の方が雪斗を背負えそうなくらい細身だったのだ。
雪斗もベッドに上がると、スプリングが、ぎしっと微かに音を立てる。
円香は思わず、ベッドの上を尻で後ずさった。
「いいよ。円香ちゃんがさっさと済ませたいなら……そうしてあげる。全部、望み通りにしてあげるから」
部屋が薄暗いせいだろうか。
雪斗の目が虚ろに濁って見えるのは。
「あの……違うの、キスマークがダメなのは、そうじゃ、なく……あっ!? ちょっと、待ってっ……!」
押し倒され、そのままなんの了承もなくバスローブを脱がされ、下着姿にされてしまった。
ブラジャーまで外されて、押さえ込んでいた膨らみがぷるんと溢れる。
「や、やっ、やだっ……」
慌てて両手で胸を隠すと、雪斗は『なんで隠すの』と非難するように睨んでくる。
が、円香の意思を尊重してか、それ以上胸に執着することはなく、今度はがら空きになった下半身に手を伸ばしてきた。
「あ、っ……!?」
これ以上嫌がるとますます怒らせてしまいそうだし、いずれは避けられないことだ。
抵抗の代わりにさりげなく膝を寄せてみたが、あっという間にショーツを脱がされてしまった。
「……ほんとに、慣れてるんだ。キスして撫でてあげただけなのに、もう濡れて、糸引いてる……」
「っ……!?」
キスに気を取られて気付かなかったが、言われてみれば、茂みの奥に濡れた感触がある気がする。
自分ばかり暴かれる恥ずかしさに、ぐっと涙が込み上げた。
「ゆ、ユキくんも、脱いでよ。私ばっかり、恥ずかしい、よ……」
片手を雪斗のバスローブに伸ばすと、彼は円香の下着を投げ捨てて手首を掴み、ベッドに縫い止めてきた。
「っ……ユキくん?」
「嫉妬でどうにかなりそうだけど……待たせた俺が悪いんだよね。でもこれからは、身体も心も、全部俺が満たしてあげるから」
「え……? なに? 何言ってるの……?」
先ほどから、ふーっ、ふーっと、昔聞いた、発作が起きる寸前のような呼吸音がしていることに気付いて心配になる。
でも、雪斗の股間がバスローブを押し上げるほど隆起しているのが目に入った瞬間、頭が真っ白になった。
「あ……」
――……? 何……あれ……?
――もしかして、興奮、してくれてる……?
――え、でも……、……あんなに目立つものなの……?
一体何がどうなったらこんなに飛び出てくるのか、理解が追いつかない。
股間に釘付けになっていると、息を荒げた雪斗が今度は両脚を掴み、膝を思い切り開いてきた。
「きゃああっ!? や、やだっ、そんな……ああっ!?」
慌てて閉じようとすると、力強く胸の方へ押さえ込まれて、おむつを替えてもらう赤ん坊のような格好になってしまう。
「やだ、やだっ……! なんで……やだってばっ! はなしてよっ!」
あまりの恥ずかしさに、もう、なりふり構っていられなかった。
全力で雪斗の手を引き剥がそうとしたが、彼はびくともせず、露わになった場所を凝視している。
「なんで? 他の男には見せたのに、俺は駄目なの?」
「っ……な、な、何度したって、恥ずかしいものは、恥ずかしいの! そんなところ見ながら話さないで!」
「……そう。そんなに何度もヤったんだ。じゃあ前の男が汚したところ、全部綺麗にしないとね……」
「え……?」
陰部を見据えたままの瞳は、昏く虚ろだ。
円香はそれを、強烈な怒りだと誤解した。
恐怖で抵抗をやめると、雪斗は広げた脚の間に屈み込んで、内腿に吸い付いてきた。
「あっ!? ぁあぁ……っ!?」
太腿を囓られ、舌で舐められ、また囓られる。
少しずつ唇が陰部に近付いてきて、茂みのすぐ近くをぬるぬると舌が這って――刺激を予感してひくついた陰部に、ふうっと息を吹きかけられた。
「ひゃ、ぁっ……!」
腰がびくついたが、内腿を押さえつけられているせいで、恥骨が微かに前後するだけだ。
「すごいね、真っ赤に充血しちゃってる……。敏感なところも、大きくなってるみたい。安心して? 優しく、気持ちよくしてあげるから」
「なにっ……、なに……あ! ふぁ、ぁあぁ……!?」
隘路に舌を押し当てられて、小陰唇の間に絡んだ愛液を掬うようにほじられた。
舌の動きも感触も捉えどころがなくて怖いのに、身体はぐんぐんと熱を持ち、汗が滲みはじめる。
「ぁ……、っ……あ……!?」
近くにあった枕を掴み、なんとか未知の感触に耐えていたのに、舌先で陰核を捉えられた瞬間、全身が跳ね上がった。
「ひぁっ!? あっ……!?」
「ああ……やっぱりここ、女の子は大好きなんだ……こんなちっちゃいところで気持ちよくなっちゃうの、可愛い……」
初めてでもないだろうに、雪斗は感動的な様子で呟くと、無邪気に舌先でつつき回してくる。
「あっ、ああぁっ!? なに、っ……そこ、や、っ、あぁあっ!」
刺激を受けるたび、全身に未知の痺れが走り、びくびくと仰け反った。
痺れを快楽だと認識した瞬間、それは倍に倍にと膨れ上がり、息が乱れ、媚びるような声まで漏れてしまう。
「軽く触るだけで、どんどん溢れてくる……そんなに欲求不満だったの? 前の男と別れたのはいつ?」
「っ……、……そ、そんなの、ユキくんに……かんけい、な……」
「教えてくれないの? じゃあ優しくするのやめよっか」
「え……ぁあああぁっ!?」
雪斗は硬くさせた舌を押し付けて、ざらざらと陰核を扱いてきた。
強すぎる刺激に背中が仰け反り、悲鳴が溢れてもなお擦られて、次第に皮が捲れ、剥き出しの突起を容赦なく嬲(なぶ)られる。
「ぁあっ、ぁあぁあ……! いやっ、ぁ、それ、っ……なに……なっ……!? だめっ……さわっちゃ、だめなとこ、っ……」
逃れようともがいているのに、動けば動くほど雪斗の指が内腿に食い込み、脚を大きく開く形で固定されてしまう。
「膨らんで、硬くなってくる……もっと擦って、って言ってるみたい」
やっと舌を離してくれたかと思いきや、彼は勝手なことを呟いただけだった。
またすぐにぱくりと唇に含まれ、じゅるじゅると下品な音が立つほど啜られる。
「あっ、ぁあ……! んんんん……っ!」
どんなに悶えても、口の中で扱き続けてやめてくれない。
しばらく続けられると膣がひとりでに痙攣をはじめて、愛液がシーツまで滴り、腰が勝手に前後して止まらなくなった。
「ぁあ、ぁ、っ……だ……め……っ、なんか、へん……へんな……っぁあ、あ……!」
痛みを覚えるほど陰部が疼いて、爪先が宙を蹴る。
全身から汗が噴き出し、膣がひときわ強く収縮して――一線を越えた感覚が訪れてもなお、雪斗の舌は止まらない。
「あ、っ、あ……! あー……!?」
不規則な痙攣で、円香の変化は伝わっているはずだ。
けれど雪斗は小さな花芯に執心し、余韻すら与えない勢いでむしゃぶりついてくる。
「ぇあ、っ、ぁう、ぁあー……ユキく……やだ、っ……や……っ……やら、ぁあぁ、あ、また、また……ぁ……、っ……!」
力なく泣き喘ぎ、その間にも、爪先が繰り返しぴんと引き攣った。
何度やめてと懇願しても無視されて、頭を押し返してみてもびくともしない。
「あっ、あっ……! ひぁ、あっ……!」
快感で痺れた指先で髪を引っ張ると、抵抗は許さないとばかりに、じゅるじゅると吸いながら扱かれて、もう何度目かわからない絶頂を迎えた。
初めてなのに。
キスまでは、素敵な雰囲気だったのに。
雪斗なら、きっと優しくしてくれると思ったのに。
自分だけあられもない姿にさせられて、一番恥ずかしい場所を貪られて、やめてと言っても聞いてくれないなんて。
「っひ……っぅ……やだっ……やだって、いってぅ、のに、なんで、っ……なん、れ……」
円香は知らない天井を見上げながら、行き過ぎた快感を受け止めきれずに涙を流した。
限界を迎えた身体が、汗で濡れたシーツに沈みはじめる。
――ユキくんは……無視なんて、ぜったい、しなかったのに……。
――ひどいこと、する子じゃ、なかったのに……。
――私、そんなに嫌われること、しちゃった……?
「あ……、ぁ……、っ……」
声が掠れ、喘ぐことすら困難になって、やっと気付いた。
じゅく、じゅる、と吸い上げる音に重なって――喘鳴(ぜんめい)に近い呼吸音が続いていることに。
さっきも息が乱れていたことを思い出して、一気に血の気が引いた。
「あ……、……だめ……」
昔は、外に出られないほど酷かった喘息だ。
元気になったとはいえ、こんなにしゃぶり続けていたら、息ができなくなってしまう。
円香はびくびくと震えながらも、ほとんど反射的に、昔見た吸入器を求めてナイトテーブルの上を見た。が、そこにはシェード付きのランプがあるだけだ。
「ユキくん……っ、ね……まって……呼吸……もっと苦しく、なったら、たいへんだから、はなれて……、ぁんっ……! あッ……!」
心配すら抵抗と捉えられたのか、舌先で陰核の根本を擽られて腰が浮く。
自分の愛液か、はたまた雪斗の唾液が、浮き上がった臀部とシーツの間で、体液がねっとりと糸を引いた気がした。
「んぁ、ぁあ、ぁー……!」
びくびくと震えながらまた達して、雪斗の頭に触れたままになっていた指が、ぎゅうっと強張った。
髪を引っ張られて顔を上げた雪斗は、『どうして邪魔するんだ』とばかりに忌々しげな様子で円香を見下ろしてくる。
「っ……は……ぁ……、っ……だいじょう、ぶ……? 息……苦しく、ない?」
心配が、愛撫の余韻を上回った。
今や雪斗の呼吸は発作が起きる直前のものよりもずっと乱れているのに、顔色一つ変えず、手の甲で濡れた鼻先と唇を拭う。
その仕草は少し野蛮で、全く雪斗らしくない。
その上、下半身は、先ほど以上に存在感を増しているように見えて。
「円香ちゃん……」
シーツの上でくしゃくしゃに乱れた髪を撫でられた。
この先の行為を意識させる、淫靡な手付きで。
「今もそんな心配してくれるなんて、優しいんだね……。でも俺、元気になったんだよ? 昔の俺とは違うの、まだわからないのかな?」