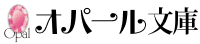結婚しよって言ったよね? 幼なじみ御曹司が私を一生溺愛する気です! 1
第一話
気付くと、豪奢な宮殿の大広間に立っていた。
何やら盛大なパーティーが催され、ドレスやコートで着飾った紳士淑女が溢れていて、円香(まどか)は気後れしてしまう。
――ああ……これは夢だ。
すぐにそうわかったのは、広間全体が、漫画みたいにキラキラと大袈裟に輝いていたからだ。
――はぁあ……。
――今はこんなファンタジーな夢を楽しむ元気なんてないし、帰りたい……。
出口を探して、会場を見渡した時。
人混みの向こうがざわめき、魔法のように人の波が割れて――小さな男の子が現れた。
白くて神々しくて、まるで天使だ。
懐かしい気がするのに、振り向いた顔は、ぼやけてよく見えない。
でも――。
『円香ちゃん!!』
声でわかった。
大好きだった幼馴染みの男の子――雪斗(ゆきと)が、弾ける笑顔で駆け寄ってくる。
――ユキくん? なんで?
――ああ……最近は辛いこと続きで、ユキくんのことばっか思い出してたせいかな……。
でも懐かしの彼は、一歩ごとにすくすく、にょきにょきと背が伸び、愛らしい面立ちは凜々しく成長して、眩いほど輝きはじめた。
発光していて、顔はやっぱりよく見えない。
でも、とんでもない色男に成長したらしいとわかった。
だって周囲の女性たちが、『きゃーっ』『何よあの女!?』『九条(くじょう)くんは私のなのに!』なんて黄色い悲鳴を上げている。
『円香ちゃん……っ! やっと会えた!』
抱きつかれて、大勢の人が見ている中で、頬にぶちゅっとキスをされた。
『なっ、なっ、何するの!?』
『いっぱい待たせちゃってごめんね! じゃっ、結婚しよ!』
そう言われた瞬間、広間の壁が取り払われ、天井が吹き飛んで青空が広がった。
色取り取りのバルーンや花びらが舞い、草原いっぱいに丸テーブルが並んでいる。席に着いた客たちが、一斉にこちらを振り向いて拍手した。
『円香、結婚おめでとう!』
『おめでとう! 円香、幸せになれよ……!』
毎日アルコールに溺れている父は、今よりずっと若く、とびきりの笑顔で涙ぐんでいる。
兄はまだ中学生くらいで、亡くなったはずの祖父母も若々しい。
『円香ちゃん。今度は俺が、幸せにしてあげる番だから』
『きゃあぁあっ!?』
耳元で熱っぽく囁かれたかと思うと、白いタキシードに身を包んだ雪斗が抱き上げてきた。
ウエディングドレスの裾がぶわっと広がって、招待客全員が立ち上がり、拍手が割れんばかりに大きくなる。
『ちょっと、何っ!? なんなの!? 下ろして! 下ろしてよ!! 私結婚なんてしないよ!? もう恋愛も子供も、ぜーんぶ諦めたんだから!』
手脚をばたつかせ、あらん限りの力で叫んだが、何も変わらない。
どんなに幸せな光景でも、意思を無視されたらただの悪夢だ。
昔は細くて病弱だった雪斗は、円香を楽々と抱き上げたまま壇上に上がっていく。
『二度と俺のそばを離れないで。おいてかないで』
『はぁあ!?』
切ない顔で勝手なことを言い、こつんと額をあわせて、じわりじわりと唇を近付けてくる。
『二人ともおめでとう!』
『お幸せに!』
『おめでとう~!』
『待って、待ってっ!? 皆おかしいよ!? 突然結婚だの、無理矢理キスだの、全然おめでたくない! ただの犯罪だよ!?』
唇を避けようと必死に顔を逸らしているはずなのに、視界が全く動かない。
抵抗も虚しく、むにゅ、と唇を押し付けられた。
やけに生々しい感触に、ぞぞっと怖気立つ。
『ふふっ、これで一生一緒だね! じゃあ次は子作りしよっか!』
『や……やっ……やだぁあぁああっ! えっち! 変態ッ! あんた誰よ! ホンモノのユキくんは、もっとちっちゃくて可愛くて優しくて、絶っっ対に、こんなことしないんだから!!』
『大丈夫だよ、気持ちよくしてあげるから。朝までじっくり、愛しあおうね……』
ドレスを一瞬で脱がされ、悲鳴を上げた――その時。
夢の外から光が差し込んだ。
――ああ……! 朝だ! 朝日だ!
――目を開ければ救われる……!!
ぶちゅぶちゅとキスをしてくる雪斗を引き剥がしつつ、懸命に瞼に力を込める。
まさか、目覚めた先でも夢と同じ結末を辿ることになるなんて、露ほども思わずに。
ユキくんのおうちは、すっごく大きい。
ぐるっと続く高い塀の横を歩いて、やっと現れたインターホンに悴(かじか)んだ指を伸ばす。
「円香ちゃん、こんにちは」
ボタンを押す寸前に後ろから呼びかけられて、ランドセルを背負った肩がびくっと揺れた。
「今日も雪斗と遊びに来てくれたの?」
振り向くと、ユキくんのお兄さんが立っていた。
ユキくんは五人兄弟の四番目なんだけど、これは一番上のお兄さんだ。制服を着てて、背が高くて、すっごくかっこいいの。学校から帰ってきたところなのかな?
もじもじしながら頷くと、門を開けて、二階のユキくんの部屋まで案内してくれた。
「円香ちゃんが遊びに来るようになってから、雪斗、時々部屋の外に出たり、リビングで食事を摂るようになったんだけど……。俺が顔を出すと、嫌がるかもしれないから。あとはよろしくね」
そう言って、お兄さんは一階に戻っていった。もしかしたら、お手伝いさんにおやつの用意をお願いしてくれるのかも。いつもすっごく美味しいクッキーを出してくれるんだ。
「ユキくん。私だよ。円香! 今日もきたよ~、入るね~」
返事はなかった。
ドアに耳をつけると、嫌な音が聞こえて慌てて中に入る。
ユキくんはベッドの中で丸まって、咳が止まらなくなっていた。
何度も聞いたことがあるから、普通の咳じゃないって、すぐにわかる。
「まってて、今、お薬……!」
部屋を見渡し、勉強机の上にあった吸入器を引っ掴んで差し出すと、ユキくんはなんとか吸い込んで――それでもまだ咳を続けてたけど、頭や背中を撫でてあげると、少しずつ落ち着いてきた。
「円香ちゃん……ありがとう」
ユキくんは枕の上で恥ずかしそうに顔を背けて、滲んだ涙を拭った。
「大丈夫? お兄さんか、お手伝いのお姉さん、呼んでくる?」
「……平気。寒いと、具合悪くなりやすいだけ……」
ユキくんはいつも『平気』って強がりを言う。
本当に平気なら学校に来てるはずだし、白くて細くて消えちゃいそうで、いつも泣いた後みたいな顔をしてるのに。
「それより、今日も来てくれて、嬉しい」
「へへ……私も、ユキくんと会うの楽しみだから」
ランドセルを下ろして、マフラーとコートを脱ぐ。ベッドの端に座ると、ユキくんが身体を起こした。また発作が出ないように、ベッドの端にあったカーディガンを肩にかけてあげる。
「……ありがとう。円香ちゃん、今日も公園で友達と遊んできたの? 同じ二年生の子? 男の子もいた?」
「うん! ユキくんも早く元気になって、一緒に遊べたらいいね。私だけじゃなくて、たくさんお友達がいた方がいいと思うし」
「……別に……僕は、円香ちゃんさえ来てくれれば……」
声がちっちゃくて聞き返す。でもユキくんは「なんでもない」って首を横に振っただけだった。
ユキくんは小学校に入ったばっかりの時に隣の席だったけど、入学してすぐ、授業中に咳が止まらなくなって、救急車が来て……それから、学校に来られなくなっちゃったの。
目の前で倒れたのを見てから、私はユキくんが心配で……一年半、毎日のようにユキくんの家に通ってる。
「そうだ。漫画の続き、持ってきたの! この間買ってもらったんだけど、ユキくんと一緒に見ようと思って、まだ読んでないんだ」
「……! 嬉しい。僕も続き、気になってたから」
不安そうなユキくんの顔が、ふわっと明るくなった。
女の子向けの絵だけど、ユキくんはなんでも、『円香ちゃんが好きなのがいい』って言ってくれるんだ。
ランドセルを開いて漫画を取り出す。先生に見つかったら怒られちゃうけど、私とユキくんの家は学校から反対の方向で、取りに帰るのは大変だから仕方ない。
ユキくんが読み終わったのを確認しながら、ゆっくりページを捲っていく。
主人公は中学生の女の子で、いつも転校生の男の子が意地悪してくるんだけど、この日は、ちょっとびっくりすることが起きたの。
残りのページが少なくなってきて、『続き、どうなっちゃうんだろう!』って思いながら捲ったら――。
「あ……、……」
主人公の女の子が、いつもケンカしてた転校生の子から、突然、キスされちゃってるんだもん!
キスしてる絵も、それをユキくんと一緒に見てることも、お互い固まっちゃったのも、なんだか恥ずかしくて。
ちらっとユキくんを見ると、耳まで真っ赤になっていた。
ぱっちりした大きな目が、長い前髪の間で潤んで、泣きそうになってて。
白くて細くて冷たい指が、私のセーターの裾を摘まんできた。
こんな時、やっぱりユキくんには私がついてなきゃダメなんだ、って思う。
「……僕、円香ちゃんと、……してみたい、……」
「えっ……」
ユキくんはまだ、キスしてる絵を見てる。
私も、もう一度漫画を見た。
……してみたいって。キスのこと?
……私とユキくんが? キス?
「……だ、ダメだよ、こういうのは……大人になったら、するんだと思う……!」
「大人になったら?」
ユキくんの目が、まっすぐ見上げてくる。
セーターを握る指に、ぎゅっと、力が籠もった感じがした。
「じゃあ、それまでずっと……一緒にいてくれる? 明日も明後日も、来てくれる? 急に来なくなったりしない?」
「もちろんだよ! でも、まずはユキくんが元気にならなきゃね。そしたら学校でも会えるし、皆と一緒に、もっと遊べるもん!」
「……うん」
またキスの話にならないように漫画を閉じると、お手伝いの可愛いお姉さんが、クッキーとホットミルクを持ってきてくれた。
おやつを食べた後は、ユキくんの勉強机に並んで座って、私の宿題を一緒に解いた。
ユキくんはすっごく頭がよくて、教えるのが上手なの。
学校に行けない代わりに、家庭教師さんと、おうちで勉強してるんだって。学校の授業より、ずっと先のことを教わってるみたい。
それから、ユキくんの本棚にある植物の図鑑を一緒に眺めた。
でも、一緒にベッドでごろごろしながら見てたせいで……。
「円香ちゃん。雪、降ってきちゃったよ。帰らないと……」
「ん、……、……」
「……円香ちゃん? ……寝ちゃったの?」
頭を、撫でられた気がする。
――……お願い、起こさないで……。
――まだ、帰りたくない。ユキくんと一緒にいたいよ。
お母さんは知らない男の人と家を出て行っちゃったし、お父さんはお仕事で遅くて……最近はお酒の匂いがして、時々一人で泣いてるの。
晩ご飯は、お兄ちゃんが塾の帰りに、コンビニでお弁当を買ってきてくれるけど……。
お腹が空いたまま一人で待ってるのは、すごく寂しくて、怖いから。
――それに、ユキくんには、私がいなきゃ……。
――ユキくんは私より小さくて、弱くて。他にお友達だって、いないでしょ?
――だから……もう少しだけ、ここにいさせて……。
この日の夜のことだった。
珍しく早く帰宅した父が、泣き腫らした目で、
『お母さんはもう帰ってこないから、お父さんと一緒に、田舎のばあちゃんとじいちゃんちに引っ越そうな』
と言って、円香と兄を抱きしめてきたのは。
『そんなの嘘! お母さん、絶対帰ってくるって言ってたよ! 私のこと、おいてくわけないもん……!』
そう言ったけれど、引っ越しの日になっても、母は戻らなかった。
そして田舎へ引っ越した後は、全てが不幸に転じた。
失ったのは、母や学校の友達だけではなかったのだ。
『円香は我が家のお姫様だからな』と抱きしめてくれた大好きな父は、妻に裏切られたショックでアルコール依存症に陥った。
エリート街道を歩んできた父にとっては、離婚も、田舎へ戻っての転職も、何もかもが耐え難い苦痛だったに違いない。
酒が原因でどの仕事も長続きせず、毎晩祖父と口論を繰り返し、その横で祖母が泣く。
円香は家にいても全く心が安まらず、かといって転校先の学校では、『東京から引っ越してきたからって、気取ってる』と、のけ者にされた。
円香の居場所は、どこにもなくなった。
やがて地域に父の噂が広まってまともな仕事に就くのが難しくなると、祖父母の年金と貯金頼りの生活になり、兄が就職して仕送りをしてくれるまで、貧しい生活を強いられた。
その一方で、雪斗は――。
円香が引っ越した途端、どんどん元気になり、幸せな人生を手に入れていった。
まるで、元々円香の助けなど必要なかったと証明するかのように。
病気を克服し、学校に通い、たくさん友達を作り、部活や習い事をはじめて、家族で海外旅行を楽しみ――メッセージに添付された写真に映る笑顔は、年々輝きを増していく。
いつだって明るく励ましてきたし、この先もそんな存在でありたい。
自分の状況を伝えたところで、幸せそうな雪斗を困らせるだけだ。
だから、『新しい学校でも、友達と仲良くやってるよ!』と嘘を吐いた。
けれど、引っ越し前と変わらない自分を装い、現実とは真逆の嘘を重ねるにつれて、雪斗と交流を続けることが辛くなりはじめた。
――ユキくんは、私がいなきゃダメだったんじゃないの?
――なんで、一人で幸せになっちゃうの?
――ユキくんには支えてくれる家族や友達がいるのに。どうして、どうして私は……。
雪斗だって、相当な努力を重ねたはずだ。
なのに日々の辛さから、次第に嫉妬や僻みが生じて、そんな自分に耐えられなくなり――中学に進学してしばらく経った頃、円香は一方的に連絡を絶った。
そうして、やっと気付いた。
雪斗の幸せなど、本当は願っていなかったのかもしれないと。
病弱な雪斗の世話を焼くことで、自分の居場所を作っていただけだと。
しばらく罪悪感と自己嫌悪に苦しみ、その後、兄が家計を助けるため遠方に就職し、より孤独と向きあわざるをえなくなって、円香は決意した。
せめてこの先は、大事な人の幸せを心から願えるよう、自分に与えられた人生に精一杯向きあって生きようと。
二十年ぶりに東京を訪れた栗原(くりはら)円香は、同窓会の会場をきょろきょろと見渡した。
各国のVIP御用達のラグジュアリーホテル、〝クリスタルメドウ〟の広間は、着飾った男女に彩られ、燦然と輝いている。
クラシックスタイルのシャンデリアに、ブルーのモチーフが配列された毛足の短いカーペット。
大きなガラス窓の向こうには、九月らしい秋晴れの元、緑が広がっていた。
――観光がてら東京駅からここまで歩いてきたけど、途中にもSNS映えしそうなカフェがいっぱい並んでたし。都会って洗練されてるな~……。
――でもやっぱり……同窓会は欠席して、観光だけにしておけばよかったかな……。
溜息を飲み込んで、ショルダーバッグのベルトを握り締める。
引っ越し後、唯一連絡を取っていた同級生からしつこく同窓会に誘われたのが、約二ヶ月前のこと。
誘ってくれた友人以外は疎遠になっていたから、当初は全く気乗りしなかった。
心変わりのきっかけとなる出来事があったのは、つい先月だ。
アルコール依存症の父が原因で恋人に振られ、その余波で仕事まで辞めざるをえなくなり、『同窓会と東京観光で気分を変えて、心機一転頑張ろう!』と半ば自棄(やけ)になって参加を決めた。
でもキラキラした会場には、それに相応しい人間が集まるものだ。
華やかさを競うようにブランドファッションに身を包み、仕事もプライベートも充実した友人ばかりが集まっている。そもそも、昔通っていた小学校は、学区に高級住宅地を含んでいたため、クラスメートの多くは実家が太いのだ。
出てくる話題は、海外旅行や、ハイスペックなパートナーとの恋愛や結婚、子供の受験の苦労話。
今までもこれからも、円香の人生には縁のないものだ。だから、
「円香は今、どうしてるの?」
なんて気さくに話しかけてくれることを嬉しく思いつつ、毎回答えに困ってしまった。
恋人に振られて職を失ったなんて、どう考えても不向きな話題だし、かといって日常はといえば、六年前に祖父母が相次いで亡くなってからずっと、依存症を認めない父との口論ばかりだ。
――そろそろ予約したホテルにチェックインできる時間だし、退散しようかな……。
そう思って、出入り口に視線を投げた時。
「栗原! なんだよ、もう帰るの!?」
ワイングラスを片手に慌てて近寄ってきたのは、同窓会の幹事で、何度も誘ってくれた松永良平(まつながりょうへい)だ。
彼の親は共働きで――つまり円香と同じ中流階級で、価値観も馴染むところが多かった。
転校後も節目節目に連絡をくれて、気負いなく近状を報告できたのは彼だけだ。良平が結婚してからも、つかず離れずの交友が続いている。
「いやー、移動で疲れちゃったから、先に失礼しようかなって」
円香の暮らす千葉県の南端から東京まで、電車を乗り継いで四時間はかかる。トレンチコートの下に同窓会向きのワンピースを着込んで会場に直行したこともあり、少し疲労も溜まっていた。
「えーっ、二十年ぶりなのに! 二次会も出ようぜ。それにほら、雪斗とか……仲良くしてただろ? まだ会ってないよな?」
「え……」
予期せぬ名前に、心臓が跳ねた。
彼は日本にいないと聞いていたからこそ参加したのだ。
雪斗とは、十四年近く連絡を取っていない。
幸せに嫉妬して、連絡を全て無視する形で一方的に縁を絶ったのに、今更あわせる顔などあるわけがない。
「何言ってるの。アメリカに留学して、そのまま向こうで就職したって教えてくれたのは、良平でしょ」
「あー……まあ……そう、なんだけどさ」
良平は歯切れ悪く視線を逸らし、ワイングラスを傾けた。
「ニューヨークだっけ? 有名なホテルで働いてるとか」
「んー、そうそう、五つ星の超~高級なとこ。アイツ引っ込み次案だったのに、すごいよなぁ」
「……、うん。いっぱい努力したんだろうね」
「地頭いいけど、それ以上に努力家だったもんなー」
引っ越す前、雪斗の友達は円香だけだった。だから良平の方が雪斗をよく知っているのは、未だに違和感だ。
楽しげに思い出話を語りはじめた良平を前に、目を伏せた。
――また幸せそうな人を妬むことがないように頑張ってきたつもりだけど。
――本当にちゃんと、そんな生き方ができてるのかな……。
十数年前。雪斗に嫉妬してしまったのは、自分の人生から逃げているからだと気付いて、それからはどんなに辛くても真正面から向きあってきた。
成人してからは、『依存症の父に寄り添いながら恋愛や結婚は難しいだろうし、生涯独身なら、せめて仕事で子供と関わろう』と考えて、幼稚園教諭の道を選んだ。
いや、二ヶ月前に、職場の幼稚園を卒園した子の父親、シングルファザーに告白され、もしかして……なんて思った日もあったことはあったのだ。
けれど、あっという間に破局した。
あまりに酷い終わり方だったので、むしろもう恋愛は二度とごめんだった。
それでも人生を謳歌している旧友たちをつい眩しく思ってしまうのは、やっぱりまだ覚悟と努力が足りないのかもしれないなと思う。
ちらりと腕時計に目をやると、もう夕方の五時半を過ぎていた。
九月に入って日が短くなりはじめているし、慣れない場所だから明るいうちに移動を済ませたい。でも良平の昔話は、放っておいたら延々と続きそうだ。
「ご、ごめん良平。私そろそろ……ホテルまで電車移動が必要で、暗くなると道に迷いそうだから」
「えっ。いやいや、もうちょっと! あ、向こうにスイーツあったぞ、もう食べた?」
「あのねえ、子供じゃないんだから、お菓子で釣ろうなんて――」
苦笑した時、会場の出入り口がざわついた。
何やら、女性たちの黄色い声が聞こえてくる。
「? なんだろ……?」
「はぁ~、やっと来たか。にしても、芸能人みたいな騒がれようだな……」
「え、芸能人?」
背の高い良平には、注目の的が見えているらしい。
せっかく東京まで出てきたのだ。珍しいものならなんでも見ておきたい。
円香は興味本位で背伸びをした。
「わぁあ……」
ものすごいオーラを放っているから、人混みの中を探すまでもなかった。
良平の言う通り、芸能人かと思わせる二枚目が、近寄ってくる女性たちに温和な笑みを向けている。
日本人離れした精悍な顔立ちと、鳶色(とびいろ)の髪。
色素の薄い肌は瑞々しく艶やかなのに、スーツのシルエットから、雄々しい体格が透けて見える。
男性を見ただけでドキドキするなんて、初めてのことだった。
彼を取り囲む着飾った女性たちは霞んで、背景と化している。
彼はその背景をぞろぞろと引き連れて、会場の中へと進んできた。
「すごーい……ホントにアイドルみたいだねぇ」
珍しい動物でも見るような気持ちで背伸びを続けていると、良平が苦笑交じりにぼやく。
「すぐストーカー化するから女友達ができないとかぼやいてたけど、贅沢だよなぁ。毎晩美女を取っ替え引っ替えできる身分ってだけで羨ましいし」
「取っ替え引っ替え、って……」
――遊び人ってことかな?
――まーでも、あんなに神がかった容姿の男性に迫られたら、どんな女性でも、ぐらっときちゃうかも……。
実際、まとわりついている女性たちは彼を見つめ、さりげなく髪を直し、必死に求愛行動をしているように見える。毎晩取っ替え引っ替えどころか、何人も侍らせることができそうだ。
「まぁすごい変わり者で、全く言い寄ってこない女を追いかける方が楽しいらしいけどな~」
良平がにやにやと笑みを浮かべて、円香へ視線を移す。
「へ~……モテすぎると、普通の子は飽きちゃうのかな? っていうか良平、知りあいなんだ? 転校生?」
「え……?」
驚いた顔で見下ろされて、首を傾げて見つめ返す。
「いやいや、よく見ろよ。知ってるだろ」
何か勘違いしてるんだろうなと思いながら、もう一度背伸びをして――男と、ばちんと目があった。
切れ長の目が、まあるく見開かれる。
それから、子供が宝物を見つけたかのような笑顔が咲いて。
「円香ちゃん……!」
「え……」
男が、周囲の女性を振り切って、まっすぐに駆け寄ってくる。
瞳の淡い輝きに、切ない思い出が蘇った。
でも、違う。
大きさも容姿も振る舞いも、何もかもが別人だ。
それに、あんなふうに女の子の扱いに慣れているなんて――。
「会いたかったっ……っ!」
「ぎゃっ!?」
駆け寄ってきた勢いでタックルされて――そのまま両腕が背中に絡んで、胸が押し潰されそうなほど強く締め付けられた。
「っぐぇ……! っ……あ、あの、」
「円香ちゃん! ほんとに……ほんとに、円香ちゃんだ……! ああ、髪伸ばしたんだね? 背も伸びてる! お化粧もしてるし……! すごい、大人になってる……!」
しっかりした男らしい輪郭も、切れ長の目も、まっすぐに通った鼻筋も。
やっぱり、子供の頃の印象とは完全に別物だ。
円香の知っている〝ユキくん〟は、縋るような怯えた目をしていたし、声だって弱々しくて聞き取りにくかった。
でも目の前の男の眼差しは包み込むように力強く、声だって、明るく朗らかな中低音だ。
何より自信に満ちた立ち居振る舞いは、青白い顔でベッドに横たわっていた時とは別人で。
それでもなんとか、髪と同じ淡い鳶色の瞳が、わずかに記憶と重なった。
「……、……ユキ……くん……?」
「そうだよ! 何、そんなにびっくりした顔して!」
「……だって、あの、海外で働いてる、って」
「あ、俺のこと聞いてたの? 嬉しいなぁ……! 一昨年、日本に戻ったんだよ!」
「そう、だったんだ……」
――もしかして良平は知ってたの? どうして教えてくれなかったの?
そう思いながら振り向いたが、あれほど『残れ残れ』と言って強引に引き止めた彼は、煙のように消えていた。
「円香ちゃんは? 今、どんな感じなの?」
「あ……えっと、私は……通信で資格取って、ずっと幼稚園で働いて、って感じで……そんなに、面白い話ってないかも」
「幼稚園の先生? 子供好きなの!? よかったぁ~、俺も好きで、いっぱい欲しいなぁって思ってたから!」
「……、……? そ、そうなんだ……?」
――……『よかったぁ~』って、何が……?
問い返すべきか迷った時。雪斗を囲っていた女性たちが、
「栗原さんと九条くんって親しかったっけ?」
「一緒にいるところ見た記憶ないけど」
「あの女誰? 私知らない~」
「なんなの? あんな馴れ馴れしく……」
なんて、嫉妬を剥き出しに囁きあう声が聞こえてきた。
早く退散した方が良さそうだなと思うのに、雪斗はお構いなしに話しかけてくる。
「円香ちゃん、女子同士の集まりにも参加してないって聞いてたから、今日も来ないかと思ってたんだけど……すごい偶然だね!」
きっと海の向こうで、途方もない努力と経験を重ねてきたのだろう。
堂々とした振る舞いは、彼の人生がいかに順風満帆で満ち足りているかを物語っている。
万が一再会することがあれば、今度は心から雪斗の幸せを祝福したいと思ってたのに――今やあまりの眩しさに、直視することすらできなかった。
「……そ、そうだね、私も、もう会わないと思ってた……。本当に、元気になったんだね」
連絡を無視をした円香を責めるでもなく、真っ先に再会を喜んでくれたことに戸惑いを覚えたが、考えてみれば、別れてからもう二十年だ。
円香にとっては雪斗と過ごした日々が唯一の幸せな思い出だったけれど、雪斗はたくさんの喜びで思い出を更新して、とっくにどうでも良くなっていたのかもしれない。
「円香ちゃん、今日は二次会までいる?」
「ううん。ちょうど、帰ろうとしてたところで」
「えっ、もう? もしかして今も実家? あんまり時間、なかったりする?」
「いや、そういうわけじゃないんだけど、……」
周囲の女性から向けられる嫉妬の視線に、殺意が交じりはじめている。
冷や汗をかきつつ半歩後ずさったのに、雪斗は離れた分以上にずずいっと近付いてきた。
「えっと、しばらく観光するからホテル取ったけど、暗くなると道が不安で。……あの、もう昔のことだけどさ、私――」
手短に昔の不義理を謝罪して、さっさとこの場を離れようとした矢先。
「ねえ! 九条くん!!」
殺意高めの視線を送ってきた女性の一人が、『いい加減譲りなさいよ!』とばかりに割り込んできた。
「この後の二次会抜け出して、二人で飲みに行かない? 私、朝まででも平気だし……」
彼女は胸の膨らみを強調するように、さりげなく両腕を寄せる。
大胆な誘いに目を丸くしたのは円香だけで、雪斗の対応は慣れたものだった。
「お誘いありがとう。でも今晩一緒に過ごす相手は、もう決まってるから……また今度、ね?」
角が立たないようにリップサービスをしたのか、はたまた、次は本気で相手をするつもりなのか。
たっぷり含みを持たせた『ね?』のニュアンスに興奮した女性たちが、
「えーっ、ずるい~! 私とも遊んで!」
「私も~!」
と瞳を輝かせ、雪斗にべたべたと触りはじめる。ほとんどセクハラだが、雪斗はそんなアプローチすら、
「困ったな。誰か一人を贔屓にはできないし。せっかくだから俺の友達も呼んで、別の日に皆でパーティーでも開こうか?」
なんて余裕の笑顔で捌いている。女性陣は、「え~っ、九条くんと二人きりがいい~!」と言いつつ嬉しそうだ。そうこうしている間にも、夜の街灯に群がる蛾のごとく、わらわらと新たな女の子が集ってきた。
――な……何これ…………。
――あ、遊ぶって、どういう意味? パーティーって? 一体何をするの……!?
いい歳をした大人だ。まさか朝までお茶を飲んでお喋り、なんてことはないだろう。良平も、『毎晩美女を取っ替え引っ替え』と言っていた。
男性と縁遠かった円香には、全く考えられない世界だ。
何より、あの可愛くて気弱だった雪斗が、こんなに遊び慣れているなんて、にわかに信じられない。
――どうしよう……ついていけない……。
――せめて一言謝ってから帰りたいけど……。
できる男は、円香の困惑まで把握していたらしい。
「待たせちゃってごめんね」
と円香の肩口で囁くと、よく通る声で、
「申し訳ないけど、ちょっと用事があるから。パーティーに興味がある子は、良平に連絡先を預けておいて!」
と強引に取りまとめて円香の手を取り、人を掻き分けて会場の外へ向かった。「え~っ」という悲鳴と共に背中に強い嫉妬の視線を受けて、冷や冷やする。
「あ、っ……あの、私は、帰るところだったから、気にしないで――」
「いや。さっきの話の続きだけど、時間はあるんだよね? 突然連絡くれなくなっちゃった理由をちゃんと聞きたい。ずっと気になってたから」
「あ……」
斜め前を歩く雪斗の顔をよく見ると、女性たちに向けていた笑顔は消えていた。
気さくな振る舞いから、もう過去の不義理は気にしていないのかと思ったが、どうやら違ったらしい。
雪斗がどう捉えていようが、謝罪は謝罪できちんとすべきだったのに、軽く済ませて帰ろうとした自分が恥ずかしくなってくる。
「もちろん……。私もずっと、謝りたいと思ってたから……」
「とにかく、また邪魔されそうだし、場所を変えよう」
雪斗は次々に声をかけてくる女性たちを強引にかわして会場を出ると、ロビーラウンジとは逆の――ホテルの奥に進み、スタッフ専用のドアを開け、事務所らしき横を通り過ぎた。
「え……えっ? ねえ待って、ここ、入っていいとこじゃないんじゃ……っ」
「大丈夫。近くの店に入ると、同窓会の参加者がいるかもしれないから」
「で、でも……」
雪斗は円香の手を握ったまま、立ち止まらない。
すれ違うスタッフは全員漏れなく驚いた顔で雪斗を見て、なぜか「お疲れ様です」と頭を下げた。
エレベーターのボタンを押して、中に引っ張り込まれる。ワゴンが何台も乗りそうな広さで、どう見ても業務用のエレベーターだ。
雪斗が最上階から一つ下のボタンを押す。
その時、中年の女性スタッフが駆け寄ってきて閉まりかけたドアを止め、雪斗に洋封筒を差し出した。
「お休みのところ申し訳ありません。三日後にご宿泊予定のルイーズ・キャンベル様から、総支配人宛てにお手紙とお花が届きまして」
世界的に有名なセレブモデルの名前だ。確か父親は、アメリカ最大手の製薬会社の会長だった気がする。クリスタルメドウは各国の大統領や王族に利用されているから、セレブが利用客でも不思議はない。
だから、耳を疑ったのはそこではなくて。
――そう、しはいにん……?
目を丸くして隣の雪斗を見上げると、先ほどの女の子たちへの軟派な対応とは打って変わって、引き締まった顔で手紙を受け取った。
「ありがとう。……贈り物は必要ないって言ったのに……」
彼は差出人を確認し、困った様子で溜息を吐く。
「花はいつも通りバックルームに飾って、スタッフの皆で楽しんで」
「はい、そのようにいたします」
そう答えたスタッフは、値踏みするように円香を見て、雪斗に視線で『彼女は?』と問いかけた。胸元のネームプレートには、〝副支配人 杉本(すぎもと)〟と書かれている。
「彼女は今晩の特別なゲストだから。明日の朝まで、部屋には誰も寄越さないで。後のことは頼むよ」
たったそれだけの説明で、杉本は「承知いたしました」と頷いた。
再びドアが閉まると、ごっ、と音を立てて、エレベーターが上昇をはじめる。
別世界に連れ去られる不安に駆られて、こくんと喉が鳴った。
「ユキくん、もしかして……ここで働いてるの? クリスタルメドウで……?」
「うん、そうだよ」
自慢するでも、自信ありげに振る舞うでもない。
ごく自然な返事に、現実が遠退いていく。
――そういえば。
――そもそもクリスタルメドウって、九条グループの系列会社が経営してるん……だったっけ……?
九条グループは日本を代表するコングロマリットの一つで、手広く事業を展開しているから確信は持てないが、いずれにしても、コネで総支配人になれるほど甘い世界ではないだろう。
何より、雪斗から発せられる自信に満ちたオーラは、どう見ても、張りぼての肩書きで得られるものではない。
とにかく、円香はここにきて初めて、彼が九条グループの御曹司であることを強烈に実感した。