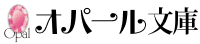運命のひと、見つけました。 敏腕弁護士とめちゃ高速しあわせ婚!? 4
第四話
久保フードサービスのトップページから、就職活動中の学生向けのページを開く。
「活躍する社員紹介」のページには、男女合わせて十人ほどの写真が並んでいた。
「美人に撮れてるでしょ」
沙也香の顔写真を指さして、人事の松下琴美は胸を張った。撮ったのは琴美なのだ。
「なんか……自分で言うのもなんだけど、笑顔がうさんくさい」
「そんなことないって。さわやか、さわやか」
琴美が軽く言う。
沙也香は苦笑いして、『広告宣伝部S.Mさん』のところをクリックした。
仕事のやりがいや、女性の働きやすさ、一日の仕事の流れなどが、沙也香にインタビューしたという体で載っていたが、どれも喋ったことの三倍くらいキラキラしているように見える。
「こんなに毎日充実してないんだけど」
「一週間分の仕事の、いい感じのところを繋ぎ合わせて一日の流れを作ってみましたー」
まるっきりの嘘ではないが、脚色がすごい。
朝から晩まで撮影やデザインに追われ、これでは独立した売れっ子のグラフィックデザイナーのようだ。
現実とのギャップに、複雑な気分になる。
「でもさ、私なんかから見ると、沙也香の仕事や環境ってすごいキラキラしてるよ」
「どの辺が?」
「グラフィックデザインって、横文字なのがまずかっこいいし」
「横文字がかっこいいって感覚がわかんないけど、人事部だって、横文字にすればいいじゃない。パーソナル……なんだろ。わかんないや」
「上司は、会社で一番のモテ男の久保さんだし」
琴美は久保のデスクに目をやった。今日は外出していて、いないのが残念そうだ。
「久保さん、会社にいるときの九割は二日酔いでヘロヘロしてるよ」
「嘘だぁ、私が見るときはいつもピシッとしてるもん。それでいて気さくだし、かっこいいし」
「……まあ久保部長、私の自由にはやらせてくれるから、その点はいいかな」
「彼女いないって噂、本当かなあ」
「気になるなら、本人に聞けば?」
「聞けるわけないじゃん! あー、そういえば、あの人も素敵だったよね。この前一緒に飲みに行った、顧問弁護士の清水先生」
「え? あ、うん……」
やましいわけではないのだが、返事がちょっと、ぎこちなくなってしまった。
「彼女いるのかなあ」
琴美は気にする様子がない。
「知りたいなら、本人に聞きなさいよ」
「だから聞けるわけないじゃん! 清水先生は、誠実そうなのがいいなあ」
琴美が遠い目をした。
「男はやっぱり、誠意だよね……」
誰を思い浮かべて言っているのかは、あえて聞かなかった。
琴美はもう三年近く、一回り以上年上の人事部長と不倫している。
うまくいっているのかは知らない。
不倫にうまくいくもいかないも、ないかもしれないが。
なんとなく、琴美は不倫に疲れてきているんじゃないかと、沙也香は最近思っている。
琴美は大卒だから、もう二十九だ。年齢の問題ではないのかもしれないが、他の男性に目が向くなら、その方が絶対いい。
沙也香は琴美の顔をじっと見た。
「なに?」
「あ、いや……」
子供シェルターひまわりのボランティアは、慢性的に人数が足りていない。
いま琴美を誘ったら、佑目当てにくるんじゃないだろうか。
ボランティアの人数は増えるし、琴美は佑にお近づきになれるしで、いいことずくめだ。
「……なんでもない」
なぜか誘うことはできず、沙也香はごまかすように首を振った。
定時で会社を上がって、電車に乗る。
吊革に掴まって電車に揺られながら、なぜ琴美をボランティアに誘うことができなかったのか、考えた。
子供たちのための空間に、男目当てで入り込んでほしくなかった?
そういう沙也香だって、高邁な精神で子供シェルターひまわりに通っているわけではない。世話焼きな性格ゆえに、小学生たちの勉強を見たり、みんなのご飯を作ったりするのは楽しいし、そういうことをする時間的余裕もあるというだけだ。
電車を降りて、改札を出る。
なにげなく駅ビルの二階にあるスポーツジムの大きな窓を見上げたが、佑の姿は当然ない。彼は朝にしかジムにこない。沙也香もそうだから、顔を合わせる機会は多い。
そのうえ子供シェルターひまわりでも会うから、佑との距離が急激に近くなっているようには感じていた。
家の鍵を探していたところで、鞄に入れていたスマホが震えた。
佑からのメッセージだ。
「……?」
やりとりするようになった猫の写真だとばかり思ったら、ただの空いた段ボール箱だ。佑の真意がわからず戸惑っていると、続いて注釈が送られてきた。
『三分前まで猫が入っていた(と思われる)箱』
エア猫か。
「フッ」
小さく声を出して笑ってしまった。
高校生の友達同士みたいな、こんな些細なやりとりに、幸せを感じてしまう。
佑は忙しい人だから、長文を送ってきたりはしない。沙也香も長々と返事を書くのは苦手なタイプだから、いまくらいの距離感が心地よかった。
もう一度、スマホが震えた。
またメッセージかと思いきや、電話のようだ。
珍しいなと思いながら、すぐに出る。
「――お疲れ様です」
『お疲れ様です、いま話して大丈夫ですか?』
「平気です、もう家に着いたところです」
『実はいま大阪から帰ってきて、もうすぐ東京に着くところなんですけど……少しだけ会えませんか』
「え?」
『この前のお礼に、お土産渡したいなって。いくろーおじさんのチーズケーキ買ってきたんです。これ、すぐ食べた方が絶対美味しいから』
「嬉しい、大好物です」
大阪土産の、定番中の定番だ。中央におじさんの焼き印が押されたスフレチーズケーキは、6号サイズと大きいのにふんわり軽く、いくらでも食べられてしまう。
沙也香は佑に住所を教えて急いで家に入り、人に見られてもギリギリセーフなくらいに部屋を片付けた。
漫画本は大部分を子供シェルターひまわりに寄付したとはいえ、ものが多い家なのはもう仕方ない。
紅茶の準備をしているときに、入り口のチャイムが鳴った。
すぐに玄関のドアを開ける。
冬の空気をまとった佑が、ケーキの箱を持ってニコニコしていた。
「おじさん、増量しておきました」
「フフッ、ありがとうございます」
おじさんの焼き印が増えたからといって、ケーキの量は増えないので、笑ってしまった。
「どうぞ、上がってください」
「いいんですか?」
「一緒に食べましょうよ。いま紅茶入れます」
「では、お邪魔します」
佑はトレンチコートを脱いで、沙也香がいつも座っているソファに座った。
物珍しそうに部屋の中を見回して、不躾だと思ったのか慌てたように視線を戻したのがおかしかった。
紅茶をふたつテーブルに出してから、ケーキの箱を開けた。
おじさんが七人、ケーキの上でニコニコしている。
ナイフを構えて、沙也香は迷った。
「清水さん、どのくらい食べられます?」
「ぺろっと全部いけちゃいそうですけど、それだとお土産にならないので、適量で」
「私も全然ひとりで全部いけちゃいそうなんですよね」
考えてみたら、晩ご飯を食べていない。これが夕食と思えば、まるまる食べたって許されそうだ。
「半分こにして食べましょう。清水さん、レーズンお好きです?」
このケーキは、下にレーズンがパラパラと敷かれている。そして沙也香はレーズンがあまり得意ではなかった。
「大好きです」
「それはよかったです」
沙也香は大きめの丸皿を二枚テーブルに出した。
そしてナイフを横に構え、ケーキを上下に半分に切った。
沙也香はおじさんを独り占め、佑はレーズンを独り占めできる切り方だ。
我ながらうまいことやったなと思ったのに、佑は口元を覆って肩を震わせている。
「半分って、こうくるとは思いませんでした」
「おじさん、欲しかったです?」
「おじさんはいらないので大丈夫です。でもこれが苺のデコレーションケーキだったら、絶交するところでした」
「危ないところでした」
しょうもないことを言い合いながら、チーズケーキを口に運ぶ。ふんわりとした食感がたまらない。口の中で溶けていくようだ。
そうそうこの味、と子供の頃のことを思い出した。
「小学生の頃、父が大阪出張のお土産にこのケーキを買ってきたことがあって」
「はい」
「おじさんのところをどっちが食べるかで、弟と掴み合いのケンカになりました」
あのとき、おじさんの焼き印がたくさんついていたら、ケンカにはならなかったんだろうか。
「おじさんモテモテだ」
羨ましいです、と美味しそうにケーキを食べながら佑が言う。
ケーキはものの十分で、ふたりのお腹に収まってしまった。
「ふう、ごちそうさまでした」
沙也香はフォークを置いた。
佑の顔を見る。明らかに物足りなさそうな顔をしている。
その気持ちは、よくわかった。
「……口が、しょっぱいものを求めていません?」
「わかります?」
「わかります、わかります」
聞けば佑も、まだ夕飯を食べていないのだという。
「よし、唐揚げにしましょう」
沙也香は胸の前でぐっと拳を握った。
「あ、デリバリー頼みます?」
佑がスマホを手に取ったが、沙也香は首を横に振った。
「作った方が早いです」
キッチンに行き、冷凍庫から下味をつけてある鶏もも肉を出して、電子レンジで解凍する。油を温めている間にポリ袋のなかで片栗粉と小麦粉を肉に揉み込んで、温まったところで揚げる。
十五分ほどで、鶏もも肉二枚分の熱々の唐揚げが出来上がった。
これはビールだろうと思い、冷蔵庫から二缶出して一緒にテーブルに持っていった。
「え、すごい」
唐揚げとビールを前にして、佑が目を輝かせる。
「はい、カンパーイ」
なんだか子供シェルターひまわりの帰りにふたりで飲むのと同じような雰囲気になってきた。
「あつっ、うまっ……うまいっ」
育ち盛りのような勢いで唐揚げにかぶりつく佑を見て、沙也香は目を細めた。
「清水さんて、ほんとに美味しそうに食べますよね」
「ほんとに美味しいですからね」
「……私、弁護士さんって、もっとなにを考えているのかわからないような感じなのかと思ってました」
偏見ですね、すみませんと謝って、唐揚げをひとつ食べる。ササッと作ったわりには、よくできていた。
「や、でも実際、表情を取り繕っているときは多いですよ。特に仕事のときは。いまはそうする必要性を感じていないだけで。って俺、初めてお邪魔したのに、くつろぎすぎですね。すみません。増村さんち、居心地よくて」
「いえいえ」
いつもはひとりで食べる夕飯を、お喋りしながら食べるのはとても楽しかった。
チーズケーキに唐揚げと、栄養バランスを全然考えてない感じもまた楽しい。
一年前まで同棲していた元カレのことをふと思い出した。彼との食事だって、最初の頃は楽しかった。だんだんと、沙也香が毎日料理するのが当たり前になっていって、美味しいと言ってもらえなくなっていったけれど。
「……増村さんて、すごいですよね」
「え、いまなにかすごい要素ありました?」
過去のほろ苦い思い出から、現在に意識が引き戻される。
「唐揚げ食べようってなっても、こんなすぐ出てこないですよ、普通」
「たまに食べたくなるので、備えているだけです。食いしん坊なんです」
どうぞどうぞと、遠慮しないよう勧める。
佑は本当に遠慮せず、唐揚げの皿は、いつのまにか空になっていた。沙也香は三個しか食べられなかったが、佑が美味しく食べられたならそれでいい。
ふたりの間にまったりした空気が流れる。佑が壁の時計を見た。彼がここにきてから、もう二時間くらい経っていた。
明日も平日だし、そろそろ解散の時間だろう。
名残惜しい。もっと、一緒にいたかった。
「帰りたくないなあ……」
ボソッと、佑が呟いた。
それから、ハッとした顔で否定しにかかる。
「違っ、あの、そういう意味じゃなくて……すみません」
酔うほど飲んではいないはずだが、頬が少し赤い。
「帰ります。お邪魔しました」
佑がコートを着て玄関に向かう。
靴を履いて、改めて沙也香と向き合う。
「ごちそうさまでした。また……明日?」
「明日」と頷く。
明日はジムでも子供シェルターひまわりでも会う予定だった。
それでもまだ足りないと思ってしまうこの感情の意味がわからないほど、沙也香は子供ではなかった。
近い距離で、ふたりの視線が絡み合う。
「――早く明日になればいいのに」
そう言った佑の顔が、沙也香の顔に近づいてくる。
初めての佑との口づけは、自分が作った唐揚げの味がした。
「ん……」
軽く触れるだけで離れていった唇が、もう一度近づいてきて深い口づけになる。背中を抱かれると同時に舌を吸われ、沙也香はビクッと体を震わせた。
佑とのキスは、口のなかがトロトロと溶けていくみたいに気持ちがよかった。
これ以上続けられたら、たぶん自分は流されてしまう。
沙也香は、彼の胸を軽く押した。
勢いで寝るような関係にはなりたくなかった。
佑はハッと我に返ったように、沙也香から離れた。
「また明日」
気まずくなりたくなくて、笑みを浮かべる。
「……また、明日」
と、佑も小さく笑い、沙也香の部屋から出ていった。
◇◆◇◆
久保部長が頬杖をついて、まじまじと沙也香を見てくる。
「なにかいいことでもあった?」
「そんなふうに見えます?」
「超見えるね」
いいこと、なのかはともかく、なにかあったのは事実だ。
具体的にいうと、昨夜、佑とキスをした。
いままで恋愛経験がなかったわけでもないのに、自分でもびっくりだが、キスひとつで浮かれている。
まったく変わり映えのしない、久保部長とふたりきりの広告宣伝部の部屋までキラキラして見えるのだから、重症だ。
「べつになにもないですけど」
「嘘だぁ」
「ちょっと、ちゃんと仕事を頑張ろうとは思いました」
いままでは頑張っていなかったのかと久保部長がキャンキャン言っているが、いままでだって給料分は頑張っていた。
でもそれだけではダメなんじゃないかと、佑の生き方を見ていて思ったのだ。
彼と向き合って恥ずかしくない自分でいたい。
そのためになにをすればいいのかはわからないけれど、まずは目の前の仕事を頑張りたい。三か月後にオープンするビストロのロゴをデザインして、外部のインテリアデザイナーとも相談しながら看板やメニューを作っていく。いままで何度も同じことをしてきたけれど、より丁寧に、真面目にやろうと思った。
「――沙也香」
仕事に集中して二時間ほど経ったところで、知った声に話しかけられ、なにげなく顔を上げた。
「琴美!?」
声をかけてきた琴美は、真っ青な顔をしていた。
「ちょ……どうしたの? 具合悪いなら、医務室行った方が」
「……これ、見て」
「え?」
琴美の震える手から、郵便物を受け取る。
あて先は琴美だ。
そして差出人は。
「弁護士……?」
といっても、佑ではない。聞いたことのない名前だった。
「なかも見て」
封筒のなかには、人事部長と琴美がラブホテルに入っていく瞬間を捉えた写真、そして、人事部長の配偶者の代理人として、慰謝料二百万円を請求するという内容の文書が入っていた。
「二百万っ……!?」
「そんなお金、払えないよ」
琴美はべそをかきだしている。
沙也香はなにも言えなかった。
この金額が不倫の慰謝料の相場として妥当なのか、沙也香にはわからない。
「でも払わないと裁判起こすって。どうしよう、パパとママには、こんなこと絶対知られたくない」
人事部長が妻帯者だと知っていて三年も付き合っていたんだから、自業自得だと言うのは簡単だ。だが相手あってのことで琴美だけが責められるのは、気の毒に思える。
沙也香の脳裏に、佑の顔が浮かんだ。
「……会社の顧問弁護士に、相談してみたらどうかな」
「それがいいと思うよ」
と、久保部長が口を挟んできた。
手にはもうスマホを持っている。
「その内容だと、うちの会社に呼びつけるより、向こうの事務所で話した方がいいかな」
「……お願いします」
久保部長が電話している間、琴美は怯えきった顔で沙也香の手を握っていた。
「――十五時に来てくださいって」
「わかりました」
頷いて、琴美は真剣な顔で沙也香を見てきた。
「沙也香、一緒に行って」
「えっ」
反射的に久保部長の方を見る。
「行ってあげたら? 急ぎの仕事はないだろ」
「はあ……」
急ぎの仕事はないが、生々しい不倫事情を隣で聞かされるのかと思うと少々腰が引けた。
「お願い、沙也香」
「う、うぅん――」
結局断りきれず、沙也香は琴美とふたりで十五時ぴったりに、佑の勤めている佐川法律事務所へ出向いた。
駅からすぐのところにある二十階建てのオフィスビルのワンフロアが、まるまる佐川法律事務所のようだ。
三十名ほどの弁護士が所属する佐川法律事務所は、多種多様な案件を扱っており、一般民事の訴訟案件から企業再編などの企業法務まで、専門的な分野に精通している弁護士が対応してくれるのだという。
一二階でエレベーターを下りると、受付があり、かちっと髪をまとめた女性がふたり並んで座っていた。さすがというべきか、久保フードサービスの社員のようなちょっとした緩さはどこにもない。奥の様子は、壁に遮られていて見えない。
入り口からすでに社風の違いを感じ、緊張してしまった。
来意を告げ、受付の女性に案内されて、応接室に入る。
「――お待たせいたしました」
いくらも待たないうちに、佑がやってきた。
カッチリとしたスーツを着こなして前髪を上げている佑につい見とれてしまいそうになるが、気を引き締めた。勤め先にいる彼は真面目な顔をしていて、当たり前のことだが昨日の夜の甘さを微塵も感じさせなかった。
琴美も、佑を前にしても、この前の飲み会のときのような浮かれた様子はまったくなく、青い顔をしてテーブルの隅を見ている。
「まずは、そちらの内容証明郵便を見せていただけますか」
「は、はい……」
琴美はよく切れる包丁でも渡すみたいに、おずおずと向こうの弁護士からきた手紙を差し出した。
ラブホテルに入ろうとしているふたりの写真を見ても、二百万という数字を見ても、佑は顔色ひとつ変えなかった。
最後まで目を通し、なるほど、というように頷く。
「二百万とはまた、ふっかけてきましたね」
「そうですよね、ひどいですよね!?」
琴美が身を乗り出す。
だが興奮しているのは琴美だけで、佑は冷静だ。
「いくつか確認させていただきたいことがあります。お相手が妻帯者だということは、最初からご存じでしたか」
「……はい」
琴美の声が小さくなる。
「不倫関係になってから、どのくらいの期間が経っていますか」
「三年……くらいです」
一拍おいて、佑が口を開く。
「結論から申し上げますと、示談を持ちかけることをお勧めします。話し合い次第ですが、百万までは払わずに済むのではないかと思われます」
「結局、お金払わなきゃいけないんですかっ!?」
琴美はいまにも泣き出しそうだ。
「証拠はしっかりとられている、夫婦の婚姻期間が長い、未成年の子供がいる、不倫期間が長い……慰謝料の増額要素となる事情がいくつもあります」
「それは……そうかもしれませんけど……」
「それでもご夫婦に離婚するつもりはないようなので、交渉次第で提示された金額の半額以下まで下げることを狙えます」
「……は?」
琴美は、ぽかんと口を開いた。
「離婚は、しない?」
「おそらく」
佑は頷いた。
「するのでしたら、そう書いてくると思います」
「下の子が高校に上がったら離婚するって言ってたのにっ……!」
そうなんだ、と思ったが、沙也香は口を挟まずにいた。
人事部長の下の子は、たしかいま中三で、あと四か月もすれば高校生だ。
多感な時期に、しかも受験前に親がこんなことになって、一番の被害者は彼なんじゃないだろうか。たとえ隠されていたとしても、同じ家に住んでいれば、ただならぬ気配は察するだろう。
「待って、それじゃ向こうはなにも失わなくて、私ばっかり彼もお金も失うってことですか? 誘ってきたのは、向こうだったのに!?」
「ですが、独身だと騙されていたわけではないですよね?」
「それは……はい……」
琴美は気まずそうに佑から視線を背けた。しかし納得したわけではないようで、食ってかかるように身を乗り出した。
「で、でもっ――」
「この場合、向こうの奥様は旦那さんと松下さん双方に慰謝料を請求できます。ただ、生計を一にしている夫婦間でお金を動かしてもあまり意味がないので、おそらく旦那さんには請求しないと思われます」
佑の説明は淡々としていた。
冷たくはないが、同情しているようでもない。
「こういった事案で裁判までいくことは、ほとんどありません。話し合いで解決できれば、双方、時間も労力も節約できますので。交渉次第ですが、分割ではなく一括払いすることで、さらに減額してもらえる可能性もあります。まずは、おいくらまでならご自分が支払えるか、考えてみてもらえますか」
途方に暮れたような顔をして、琴美はしばし黙り込んだ。それから細く長い息を吐き、立ち上がった。
「……お手洗い、お借りしていいですか」
「どうぞ」
ちょっと頭を冷やしてきます、と琴美はフラフラした足取りで化粧室に向かった。
沙也香とふたりきりになると、佑の表情がわずかに緩んだ。
「……琴美が悪いっていうのは頭ではわかるんですけど、人事部長だって同じかもっと悪いはずなのに、ほとんどおとがめなしっていうのが……なんだか琴美が可哀想に思えてしまいます」
琴美と佑の話をずっと黙って聞いていた沙也香が言った。
琴美は沙也香の友人で、人事部長には特に恩もないし、その奥さんに至っては顔も知らないから、どうしたって琴美に肩入れしてしまう。
「結婚っていうのは、それだけ重い契約なんです。慰謝料は請求されなくとも、人事部長さんはこれから、部下に手を出した上司ということで会社内でなんらかの処分が下されるでしょうし、家庭のなかでもしっかり奥さんに釘刺されると思いますよ」
そう言ってから、佑は自嘲気味に笑った。
「なんて、わかったようなこと言ってますけど、僕片親でしたし、離婚案件でうまくいっていない夫婦ばっかり見てるから、結婚ってなんなのか、正直よくわからないんですけどね」
それはそうだろうなと沙也香は思った。
「うまくいっているご夫婦は、あんまり弁護士さんに相談なんてしないですもんね」
「相続なんかのご相談にいらっしゃるひとたちもいるんで、まったくないってことはないですけどね」
沙也香は一番身近な夫婦である、自分の両親を思い浮かべた。
「夫婦かぁ……うちの親は、仲がいいっていうか、男と女ではなくて、『父親』と『母親』っていう生き物みたいな感じだなあ……」
だから、ラブラブではないが、不倫という言葉からはもっとも遠いところにいるように娘からは見える。
「子供第一の、いいご両親なんでしょうね。沙也香さん見てるとわかります」
「……ありがとうございます」
照れくさくて、佑から視線を外した。
両親を褒められるのは、自分を褒められるより嬉しい。
「ちょっと琴美の様子を見てきます」
なかなか戻ってこないから、心配になってきた。
沙也香は席を立って、化粧室へ向かった。
「――琴美」
「沙也香……」
少し泣いたんだろうか。琴美の目が赤い。
「大丈夫……?」
大丈夫なわけないのに、つい聞いてしまった。
「頭ではわかってるんだ、私が悪いって……でも、心がついてこなくて」
わかるよ、とは言えない。
それでもいまは琴美の心に寄り添いたくて、そっと肩を抱く。
「三年もなにやってたんだろう、私……あの人にとって、私っていったいなんだったんだろうなあ」
答えが欲しいのではないとわかっていたから、沙也香はただ、琴美の肩を抱いている手に力を込めた。