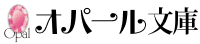運命のひと、見つけました。 敏腕弁護士とめちゃ高速しあわせ婚!? 3
第三話
週末の午後、沙也香は漫画本ではち切れそうになったトランクを持って、教えてもらった住所へ向かった。
「ここかな……?」
古い住宅街の細い路地の先にあった、木造の二階建てを見上げる。
「子供シェルターひまわり」という看板は、どこにも出ていない。
少し迷ってから、インターホンを押す。
バタバタバタっと誰かが階段を下りてくる音がして、玄関の扉が開いた。
「いらっしゃいませ、ひまわりへようこそ」
佑が笑顔で立っていた。ジムで見るスポーツウエア姿とも、会社で見たスーツ姿とも違い、カジュアルな綿シャツとデニムを着ている。
その後ろには、小学五年生くらいの男の子がいて、好奇心を隠そうともしない様子でこちらを見ている。
「……たすくんの彼女?」
「違うよ」
彼はここでは「たすくん」と呼ばれているらしい。
「二階に子供たちが集まる部屋があります。それ重いでしょ、俺が持ちます」
「すみません、お願いします」
ここまで引きずってくることはできたが、さすがにこのトランクを持って急な階段を上るのはキツいなと思っていたので、素直に頼んだ。
トランクを持った佑の、後ろに張り付いている男の子の、さらに後について、二階に上がる。
短い廊下の先には、八畳ほどの部屋があった。
畳敷きで、長テーブルと座布団が並んでいる。
なかにいた子供たちが、いっせいに沙也香の方を見た。
想像していたより大きい子が多い。小学校高学年から、高校生くらいまで、五、六人いる。男女比は半々くらいだった。
「たすくんの彼女?」
また同じことを子供のひとりに聞かれ、「違うよ」と今度は沙也香が答えた。
「私は増村沙也香っていいます。漫画たくさん持ってきたから、よかったら、読んでね」
佑が持って上がってくれたトランクの鍵を開けると、歓声が上がった。
「あっ、これいまアニメやってるやつ」
「こっちは、完結したばっかりのやつだ」
次々と手が伸びてきて、トランクから本を奪っていく。
なるべくメジャーで、新しめなものを選んで持ってきたのは、正解だったようだ。
「本当にありがとうございます、助かります」
佑に改めてお礼を言われ、首を横に振る。
「いえ、私も助かりました。本は読んでくれるひとのところにあるのが一番いいので」
思い思いの格好で漫画を読みはじめた子が四人。部屋の隅の方で真面目に勉強をしている子がふたり。高校生だろうか。そっちはだいぶ大きい子だ。受験を控えているのかもしれない。
「たすくん、数学わかんない。ヘルプ」
勉強していた、男の子の方が片手を上げた。
「よしきた」と佑がそちらへ行く。
さすがだ。高校生の数学なんて、沙也香にはとても教えられない。
小中学生たちは、漫画に夢中だ。
とりあえずこの部屋でやれることはしばらくなさそうなので、沙也香は佑に声をかけた。
「キッチン、お借りしていいですか」
「あ、はい」
佑が立ち上がろうとしたので、大丈夫、というように手で制す。
二階のもうひとつのドアが開いていたので、そこがダイニングキッチンなのはわかっている。
「なにか作るの?」
漫画本から顔を離して、高学年らしい女の子が話しかけてきた。
「みんなにおやつ作ろうかなって思って」
「私もやりたい」
「じゃあ、手伝ってくれる? ええと、なにちゃんかな?」
「心愛」
女の子がじゃれついてくる。人懐っこい子だ。
ふたりで手を繋いでキッチンに入った。まずは持ってきた袋のなかからテーブルの上に材料を全部出す。
「……おやつ、餃子?」
心愛が不思議そうな顔で五十枚入りの餃子の皮を手にした。
「ううん、ひとくちピザ。ラップあるかな?」
「あるよ」
心愛が引き出しから取ってくれたラップを、テーブルの半分くらいの範囲に敷く。
そこに、ふたりでどんどん餃子の皮を並べていった。
ピザソースは、チューブの市販品だ。それを心愛がひとつずつ真ん中に絞っていって、沙也香がスプーンで塗り広げる。
トッピングは、あらかじめ茹でてきたアスパラや半分に切ったミニトマト、パプリカ、ソーセージなどいろいろある。それらをのせ、上からパラパラと溶けるチーズをかけたら、あとは焼くだけだ。
二口コンロの両方にフライパンを置き、焼きはじめる。
心愛は食器棚から大きな皿を二枚出した。
「美味しそう。楽しみ」
「焼けたらこっそり先にちょっと食べちゃおう」
「いいの?」
「作ったものの特権だよ」
なにせ生地が餃子の皮で薄いから、あっという間に焼ける。
心愛はミニトマトとソーセージのひとくちピザを選んで取り、目を輝かせて食べた。
「美味しい……!」
「でしょ? どんどん焼くから、運んでくれるかな」
「うんっ」
大皿に第一弾をのせて、心愛がみんなのところへひとくちピザを運んでいった。
歓声が上がるのを聞いて、嬉しくなる。
夕飯は、野菜たっぷりの中華丼を、これも心愛と作った。
食材は、シェルターの理念に共感してくれたスーパーや企業の提供と、募金で賄われているらしい。
ありがたいことに食材庫にはタケノコの水煮やウズラの卵の缶詰まであったので、かなり本格的な中華丼ができた。
「みんな、ご飯にするよーっ」
そう言うと、漫画を読んでいた子が慣れた様子で布巾を濡らし、長机を拭いた。それから各自トレーを持ち、その上に皿やスプーンをのせて並びだした。
ご飯はセルフサービス、中華丼のあんは沙也香がバランスよくかけてやる。
沙也香と佑も、子供たちと一緒に食卓を囲んだ。
いただきますをして、いっせいに食べはじめる。
「美味しい!」
「すげえ、たすくんがいる日なのに、カレーじゃない!」
「うるせえよ」
と、佑が男の子たちに文句を言う。
「中華丼って初めて食べたー」
「ねえねえ、おかわりある?」
「あるよ、いっぱい食べてね」
沙也香は笑顔で言った。
大人数の食事を作り慣れていないものだから、作りすぎたかと心配になっていたのだが、子供たちはみんな食欲旺盛だ。大鍋いっぱいに作ったものはみるみる減っていき、最後には綺麗に空になった。
夕食の時間が過ぎ、子供たちが「またね」と次々帰っていく。
そんななか、心愛だけは食後も漫画本を読み、帰る気配がない。
どうしたんだろうと思いながら、沙也香は皿を洗った。
キッチンの片付けが終わる頃、ボランティアらしき若い女性が「こんばんはーっ」と二階に上がってきた。
「こんばんは、初めまして。増村と申します」
「初めまして、お疲れ様です、田中です。今日は私が泊まり当番なので、もう上がって大丈夫ですよ」
「泊まり当番?」
「家に帰りたくない子がいるときは、同性のボランティアがひとり、一緒にここで朝まで過ごすんです。心愛は週に一、二回泊まっていきますね」
「そうなんですか」
なぜだろうと思ったけれど、本人がそう遠くないところにいるのであまり立ち入った話はできなかった。
手袋が欲しいほどではないが、陽が落ちるとぐっと冷え込むようになった。
沙也香は空になったトランクを引いて歩き、佑と一緒に手近な居酒屋に入った。
お疲れ様の乾杯をする。二人とももうお腹は満たされているので、つまみは枝豆や冷やっこなど、軽いものばかりだ。
「今日は本当にありがとうございました」
佑が今日何度めかの礼を言ってくる。
「増村さんが小学生たちの相手と食事の支度をしてくださったおかげで、高三のふたりの勉強をしっかり見てやれました」
「やっぱり受験生だったんですね」
佑が頷き、それにしても、と続ける。
「小学生たちにずいぶん懐かれていましたね。子供のあしらい方がお上手だ」
「弟と少し年が離れているので……あと、人懐っこい子が多いですよね。みんなあんまり人見知りしない感じでした」
「みんな寂しいんです。親がいなかったり、いても帰りが遅かったりで」
まるで自分も寂しいみたいに、佑が言う。
「寂しい子は、危ないんです。悪い大人に簡単につけこまれる」
「だから子供シェルターを?」
「俺も母子家庭育ちなんでね。ひとりで家にいたくなくて、フラフラしてしまう気持ちはよくわかるんです。そうすると、いろんなひとが寄ってきます」
沙也香は生ビールのジョッキを傾けた。
「私は両親の揃った家で育ちましたし、弟もいたので清水さんの言う寂しさについて、わかる、とは言えませんが……今日は、子供たちと過ごせて楽しかったです。みんないい子でした」
「今日は気軽に誘ってしまいましたけど、ご予定とか大丈夫でした?」
佑が心配そうな顔で尋ねてきた。
「いやー、私、友達少ないですし。彼氏もいないものですから、週末だいたい暇で」
自分で言っておいて情けないが、実際そうだった。
「私こそ、子供たちに相手してもらってありがたかったです」
沙也香は本心からそう言って笑った。
「……そうなんだ」
「え?」
「いえ、なんでも」
佑が澄ました顔で枝豆を摘まんだ。
「またお手伝いしに行ってもいいですか? ご迷惑じゃなければ」
佑は大きく頷いた。
「もちろん。嬉しいです、いつでも大歓迎です」
「よかった」
「そうそう、中華丼すごい美味かったです。俺が夕飯作ると、毎回カレーになっちゃうから、またかって不評なんですよね」
沙也香は笑ってしまった。
カレーなんて子供は大好きだろうに不評ということは、よっぽど頻繁に作っているのだろう。
「清水さんは、一人暮らしなんですか?」
「そうです、大学時代に母親が亡くなってるので」
なんでもないことのように佑は言ったが、母子家庭できょうだいもいなかったと以前言っていたから、いまは天涯孤独ということだ。それはとても寂しいことのように思えるが、もちろん口には出せない。
「そうだったんですか……自炊はなさらないんですか?」
「ほとんど外食で済ませちゃってますね。帰りが遅いので、出前頼んで事務所で食べることも多いですし。増村さんも一人暮らしですか?」
「はい、いまは」
頷いたとき、一年前に別れた恋人の顔が脳裏に浮かんだ。
彼とは半年間、同棲していた。家賃や生活費は折半していたが、家事は百パーセント沙也香がやっていた。それを不満に思ったこともなかった。
気の強そうな見た目から意外に思われることが多いのだが、沙也香はひとの世話を焼くのが嫌いではない。
そして弟はともかく、恋人に対してはこの性質はあまりいい方に働かない。
調子に乗って浮気されたり、母親扱いされて女として見られなくなったり、「俺はお前の弟じゃない」とフラれたり、もう散々だった。
という話をすると、佑は自分のことでもないのに憤慨した。
「それ、増村さんは悪くないじゃないですか。男の方が悪い。甘えすぎです」
「ふふ、ありがとうございます。でもちょっともう、恋愛ごとはしばらくこりごりです」
「寂しいもの同士」
乾杯しましょ、と佑がグラスを傾けてきたので、手にしていたジョッキをコツンと軽く当てた。
同士、ということは、佑もいま恋人はいないらしい。
だからなんだということもないはずなのに、佑とふたりきりで飲んでいるいまの状況をやけに意識してしまい、緊張してきた。
「――人間はともかく、猫飼いたいんですよね。やっぱりちょっと、寂しいので」
緊張を振り払うように、明るい声で言った。
「でもいま住んでいるアパートは、ペット飼育禁止で。仕方なく、友達の家にたびたび猫を吸いに行ってます」
「俺もめちゃくちゃ飼いたいです。でも家にいる時間が短くて猫が可哀想だし、やっぱり飼育禁止だしで、仕方ないからキャットタワーだけ買っちゃいました」
「えっ、タワーだけ!?」
「そう、タワーだけ」
なかなか衝撃的な発言だと思うのだが、佑は淡々としている。
「一番てっぺんに、猫用のベッドを置いてるんです。中身は下にいると見えないんで、『いまあそこで俺の猫が寝ている』と思い込むことで、エア猫との暮らしが実現します」
「エア猫……」
「変ですかね?」
変じゃないです、とは言えなかった。
クスクスと、笑いが止まらなくなってしまう。
肩をヒクヒクさせている沙也香を、佑は優しい目でじっと見ていた。
週が明けて、月曜の朝。いつもならジムへ行く時間に、沙也香は近所の公園にやってきた。広域避難場所になっている大きな公園には、一周約八百メートルのランニングコースがある。道沿いにはずらっと桜の木が植えられていて、桜の名所として知られている。
「……さむっ」
上下長袖のジャージを着てきたが、じっとしていると、けっこう冷える。時計塔の下に立ったまま、膝を曲げ伸ばししたり、軽くジャンプしたりして運動していると。
「――すみません、お待たせしました」
こちらはランニングタイツにショートパンツ、フード付きのパーカーを着た佑が、駆け寄ってきた。
「おはようございます」
待ち合わせした時間ちょうどだ。
「おはようございます、じゃ、行きましょっか」
挨拶もそこそこに、ふたり並んで走りだした。
ハッ、ハッ、と吐き出す息が白いが、手がかじかむほど寒くはない。
たまには外で走りませんか、と昨晩誘ってくれたのは佑だ。
朝はかなり冷え込むのではないかと、返事をするのに少々躊躇したが、来てよかった。雲ひとつない青空に、キリリと冷えた空気が気持ちいい。
真冬だとキツかっただろうが、いまの季節なら天気さえよければ案外快適に走れると知った。ジムで走るのとはまた、気分が変わっていい。
ランニングコースには、ふたりの他にも、走っているひとがチラホラいる。ウォーキングしているひとや、犬の散歩をしているひともいた。コースの脇には木製の大掛かりなアスレチックがあり、昼間にはかなり賑わうのだが、まだ早い時間だから、親子連れの姿は見当たらない。
「気持ちいいですね」
「寒くないです?」
佑が気遣うように尋ねてきたが、五分も走らないうちに、体はだいぶ温かくなっていた。
「ちょっと寒いのが、朝活してる! って感じでいいです」
「これで、森の仲間たちがいれば完璧だったんでしょうけど」
「けっこういるじゃないですか。ひととか犬とか」
「それ町の仲間たちですね」
しょうもないことを話しながら、タッタッとリズムよく地面を蹴る。
佑とは脚の長さがだいぶ違う。快適に走れるということは、彼が自分に合わせてくれているのだろう。
そんなふうに、コースをちょうど一周したときだった。
「――ジョンちゃんっ!」
女性の悲鳴が背後から聞こえた。
振り返ると、大きな犬――おそらくボルゾイが一匹、飼い主の手をすり抜けて走りだしたところだった。ボルゾイはもう一匹いて、そちらのリードは女性の手に握られている。
「あっ……」
沙也香が反応する前に佑が、逃げたボルゾイに向かって猛ダッシュした。
みるみるうちに犬との距離を詰め、ラグビーでトライを決めるみたいにリードの端を掴み、ゴロゴロと地面に転がる。
「……ったー」
「大丈夫ですかっ」
リードを掴んだまま地面に大の字になった佑に、急いで駆け寄る。
「ワンッ」
ボルゾイは遊んでもらっていると思ったのか、はしゃいだように佑に体を擦り付け、べろべろと土のついた顔を舐めた。
「ハハッ、くすぐってー……よしよし、もう逃げんなよ」
土で汚れた笑顔が眩しい。
考えるより先に、体が動いたのだろう。
このひとは、反射的に他人のために行動できるのかと、沙也香は感動していた。
けっこうすごい転がり方をしたと思ったのだが、大丈夫そうでよかった。
「す、すみませんっ! ありがとうございました、ジョンちゃん、コラっ!」
飼い主の年配の女性がようやく追いついてきた。
女性はジョンちゃんのリードを佑から受け取り、ペコペコと何度も頭を下げて、去って行った。その間佑は地面に座ったまま、左手を膝におき、笑顔で右手を振っていた。
「さて……その左手をどけてみていただけますか」
女性の背中が遠ざかってから、沙也香は言った。
「……バレました?」
佑が苦笑いして左手を膝からそっと離す。
ランニングタイツに大きな穴が空き、そこから土や砂で汚れた擦り傷が見えた。
「膝擦り剥くなんて、大人になってからは初めてです。まあたいしたことないんで、放っておけば治るでしょ」
「駄目です、ちゃんと手当しないと。そこの水道で、傷をよく洗ってちょっと待っててください」
佑の返事を待たずに、沙也香は公園の外にあるコンビニに向かって走りだした。
この時間だと、ドラッグストアは閉まっている。コンビニでサイズの大きな絆創膏があるか心配だったが、肘・膝用、しかも消毒せずに、洗った傷を覆うタイプの絆創膏が棚にあった。普通のものより早く、綺麗に治るというやつだ。それを掴んでレジで会計を済ませ、またダッシュで佑の元へ戻る。
擦り剥いた膝をびしゃびしゃにして、ちょっと途方に暮れたような顔をして立っているのが、やんちゃな男の子みたいで可愛い。
「お待たせしました」
まずは水分を取るため、ウエストポーチからハンカチを出し、傷にそっと押し当てた。
「あ、そんな。汚れちゃいます」
佑が慌てた声で言ったが、ハンカチなんて汚すためにあるようなものだ。
佑の膝は、横幅三センチくらい、皮がべろっと剥けてしまっている。そこをきっちり覆うように、絆創膏を貼る。
三枚入りだったので、残りの二枚は佑に渡した。
「これ、おいくらでしたか。払いますよ」
「いえ、けっこうです。私が勝手に買ってきたので」
たいした値段ではないし、この場で財布を開けて小銭をやりとりするのも気が進まなかった。
「わかりました。今度べつのなにかで埋め合わせします」
「……楽しみにしてます」
遠慮せずにそう答えてしまったのは、またふたりで会いたいからだった。
◇◆◇◆
ぴろん、と佑のスマホが気の抜けた音を立てた。
立ち止まって、メッセージを開く。
沙也香からきた、野良猫の後ろ姿の写真を見て、頬が緩んだ。
いまはもう十二月。沙也香が子供シェルターひまわりに初めてきてくれたときから、半月が経つ。
佑は、梅田の街をビジネスホテルに向かって歩いている。明日大阪地裁で行われる法人破産事件の債権者集会に出席するため、前乗りで大阪入りしたのだ。
ボランティアの予定を入れている日以外は、毎晩帰りは遅いし、週に二、三度は出張もある。佐川法律事務所のアソシエイト弁護士として相も変わらず忙しい日々を送っているが、最近は毎日が楽しい。
猫が飼いたいのに飼えない仲間として、お互い見かけた猫を、沙也香とこうして送り合っているからだ。
常時四、五十件の訴訟案件や倒産事件、交渉事件を抱えているなかで、沙也香とのこんな些細なやりとりに心癒やされている。週に三日ほどは、朝のスポーツジムで直接顔を合わせて挨拶を交わせるのも嬉しい。
彼女は子供シェルターひまわりにも、もう何度も来てくれていて、あっという間に子供たちになじんでしまった。
サバサバしているようで、情の深いひとだと思う。カラっとした笑い方が魅力的で、いつまでも見ていたくなる。
膝の手当をしてくれたお礼というのを口実にして、なにか大阪土産を買って会いに行ってしまおうかと思うくらいには、佑は沙也香に惹かれていた。
こんな感情は、久しぶりだ。
弁護士になって一、二年目の頃は、勉強漬けだった学生時代の反動のように、誘われるまま合コンに行った。そういう場で出会う女性は、例外なく弁護士という肩書を「すごーい」と褒めてくれた。
はじめは単純に喜んでいた。
しかし、次第に違和感を覚えるようになった。
新米の、ひとりじゃなにもできないような弁護士なんて、すごくもなにもない。
気を遣って初対面の女性と飲むのもなんだか億劫になり、いまではほとんどそういう場に行かなくなった。
佑のようなものは少数派で、同世代の弁護士仲間は、皆タフだ。三十を越えたいまでも、女性のいる銀座の店なんかに繰り出して、毎日のように飲みまくっているものが少なくない。
佑も顧問弁護士をしている企業のお偉いさんから誘われたりすると、断りきれず銀座へ行くこともあるが、さほど楽しくはない。
もう自分は、女性にときめいたりする感情が枯れてしまったのだと、ここ数年は思っていた。
「おっ……」
路地の入り口に、去勢手術をされた証拠である桜耳の三毛猫を見つけ、立ち止まる。
中腰になって、スマホのカメラを構えた。
「そのまま動かないでくれよ……」
連写モードでパシャパシャと写真を撮る。
「オッケー、ありがとう」
お礼を言うと、三毛猫は音もなくスッと路地の奥へと去っていった。
撮れた写真のなかから、一番写りのいいものを選んで、沙也香に送る。
すぐに既読の文字がつき、三毛猫のスタンプが返ってきた。
ふわっと胸のなかが温かくなる。
ビジネスホテルに向かう足取りが、軽くなった。