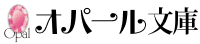運命のひと、見つけました。 敏腕弁護士とめちゃ高速しあわせ婚!? 1
第一話
タッタッタッと小気味いい音を立てて、増村沙也香は、山道を走る。半袖Tシャツに下はジャージ姿で、首の後ろで束ねた長い黒髪が、尻尾のように揺れている。
小道の向こうに、鹿がヒョイっと顔を出して、すぐに逃げていった。
二十四時間営業の、駅ビルのなかにあるスポーツジムだった。目の前のモニターは、いまの季節である晩秋の、森の風景を映している。
沙也香が家から五分のこのジムに入会して、二週間ほど経つ。インストラクターは朝九時から夜八時までしかいないが、それ以外の時間も会員なら自由に出入りして運動することができる。なので、ほぼ毎日、出勤一時間前にきて、三十分ほど軽く走って、シャワーを浴びてから会社に行っている。
疲れるほどは走っていないし、朝から頭がスッキリして、なかなかいい。
天気や季節に関係なく走れるというのも気に入っている。昼間はともかく、朝方はすっかり冷え込むようになったいま、外を走るのはちょっとキツそうだ。
沙也香がジム通いを始めるようになったきっかけは、両親が終活を始めたからだ。
先日、沙也香は一人暮らししているアパートから、電車で二十分ほど離れたところにある実家に帰った。
お土産に持っていった豆大福を頬張り、五つ年下の弟も交えて近況報告などしていたとき、両親が、思い出したように沙也香が元自分の部屋に置きっぱなしにしていた漫画本やめったに着ない服なんかを、全部持っていけと言ってきた。
便利さを優先したため、沙也香が一年前一人暮らしするのに選んだアパートは、狭い。
クローゼットは満杯だし、本棚から溢れた本が床にタワーを作っている。
いまだって十分ゴチャゴチャしているワンルームのアパートに、大量の漫画本や服が増えた光景を想像すると、げんなりした。
かといって、勝手なもので、捨てられてしまうのも嫌だ。どの本や服にも、それなりに思い入れがあるからだ。
どうすんのと迫ってくる母に、沙也香はちょっと考えさせて、と逃げた。
「それにしても、六十代で終活って、早くない?」
せめてあと十年くらいはそのまま置いておいてくれないかなという願いを込めて、沙也香は尋ねた。
「体が動くうちに荷物を減らして、身軽になっておいた方がいいんだって。みんな言ってるわ。七十越えたら億劫になって片付けなんてやってられなくなるって」
みんなって。
はるか昔に、沙也香が「みんな持ってる!」とゲーム機をねだったときは、「うちはうち、よそはよそ!」と言っていたくせに。
大人げないが、母にも、母に終活とやらの重要性を吹き込んだ輩にも、文句のひとつも言いたくなる。
「姉ちゃんは? なにかしないの?」
お気楽な調子で、弟の豊が尋ねてきた。
豊は大学三年生で、神様が全力で甘ったれを立体で表現したような顔をしている。
つまり、可愛い。
「なにかって?」
「父さん母さんは終活、俺は就活ときたら……姉ちゃんは、婚活とか?」
「いやあ」
ないない、と沙也香は顔の前で右手を振った。
半年同棲して、一年前に別れた元カレとは、漠然とそのまま結婚するんだろうなと思っていた。でも別れてしまったし、沙也香はまだ二十七歳だ。誰でもいいからと、結婚を焦るような年でもない。
「じゃあ、あれだ」
「あれ?」
「朝活」
「朝活――」
豊に乗せられたような形で朝活を始めた沙也香だが、いまではジムに入会してよかったと心から思っている。
もともと太ってはいないので、体重に変化はないが、すこぶる体調がいい。昼間の仕事の集中力が増したし、夜はぐっすり眠れるようになった。
ジムに入ってすぐの頃はいろいろなトレーニングマシーンを試してみたりもしたが、いまはもっぱらランニングマシーンだ。
ただひたすら走るというのが、性に合っている。
各ランニングマシーンの前にはモニターが設置されていて、テレビ番組やランニング用の風景、映画など好きな映像を流すことができる。大きな事件が起こったときなどはテレビ番組を見ることもあるが、沙也香はだいたいはランニング用の風景を流している。
心を無にして、軽快に森のなかを走っていたときだった。
隣のランニングマシーンに、誰かきたような気配がした。
横目でチラリと見る。
四十代くらいの男性のようだ。日焼けした肌が、テラテラと光っている。
この時間帯、ジムは人が少ない。わざわざ隣にこなくても、いくらでもマシーンは空いているのに。
「おはようございます」
「……おはようございます」
「こちらには、よくいらっしゃるんですか?」
男のランニングマシーンは、止まったままだ。
値踏みするような目で、頭の天辺から足の先まで見られたのがわかって、ぞわぞわする。
沙也香は舌打ちしたい気分だった。
こんなところで、ナンパするなよ。
インストラクターがいない時間帯とはいえ、防犯カメラがあるのだから、あまりしつこければ退会させられるのだろうが。
「走らないんですか」
「つれないなあ」
自分は三日前にこのジムに入会したばかりだ。会社はここから二駅。朝もくるが仕事の後にも利用したいと思っている。今日は綺麗なひとと一緒になってラッキーだ。などと、ぺらぺらとよく動く口が、尋ねてもいない情報を垂れ流してくる。
あまりのうっとうしさに、目眩がしてきた。
森のリスさんが、逃げていってしまったのすら男のせいに思えてくる。
気が弱いわけでもない沙也香がハッキリ拒絶できずにいるのは、男が手を握ってきたり、デートに誘ってきたりはしていないからだ。
それに自宅の最寄り駅が同じということは、今後もジムの内外で顔を合わせる可能性がある。
変に逆恨みされては怖い。
まだ走りだして十五分くらいしか経っていないけれど、今日はもうやめて会社に行ってしまおうか。
そんなふうに考えだしたときだった。
「――あ、おはようございまーす」
某うたのおにいさんのようなさわやかな声で、挨拶をされた。
ハッとして顔をそちらに向けると、何度かこのジムで顔を見かけたことのある男性が、屈託のない笑みを浮かべて、片手を軽く上げていた。
声だけでなく、顔もさわやかで、ナンパ男の油分でねとついていた体の内側が浄化されたような気分になった。
「おはようございますっ」
すがるような思いで、挨拶を返す。
「今日、いつもよりちょっと早くないです?」
男性はナンパ男とは反対側の隣に、ごく自然に移動してきた。マシーンに乗り、スイッチをオンにして、早歩きから始めている。モニターには沙也香と同じ、ランニング用の風景が映し出されている。
「あ……ちょっと、早めに会社行こうかと思って」
「あー、夜けっこう降るみたいですもんね。俺も早めに行こうかな」
いかにも知り合いっぽい会話をしているうちに、ナンパ男は気まずそうに別のマシーンへ移っていった。
「……余計なお世話でした? 嫌がってるように見えたから」
声のトーンを落として、男性が言った。
「助かりました。超イヤでした」
「やっぱり」
男性が顔をくしゃっとさせた。
その笑顔に、キュンとした。
Tシャツと短パンという服装のせいもあるのだろうが、人懐っこそうな笑顔はまるで学生のようだ。自分より、三、四歳年下だろうか。
こうして話すのは初めてだが、黙々とトレーニングに励んでいる姿は、何度か見かけた記憶がある。
「この時間、よく一緒になりますよね」
「そうですね」
男性の方も沙也香を認識していたと思うと、ちょっと嬉しくなる。
細身だが、筋肉のついたいい体をしている。これが細マッチョというやつだろうか。
なんの仕事をしているんだろうなとふと思ったが、聞けるほどの関係性ではない。
消防士さんとか似合いそうだなと、心のなかで想像した。
「……俺も走るときは、だいたいこの風景を流してるんですけど」
「はい」
「十キロごとのタイミングで、低確率で右下の隅に隠れキャラが出てくるの、知ってます?」
いままで沙也香が見たことがある動物は、鹿、リス、イノシシ、名前のわからない鳥数種類だ。だいたい、朝の三十分だけだと十キロまでなんてとても走れない。
「……熊とか?」
そういえば一度だけ、ツキノワグマが出たときはあった。
「惜しい。正解は、パンダです」
惜しくないし、パンダは日本の森の仲間ではない。
「絶対嘘でしょ」
「嘘だと思います?」
男性は澄ました顔をしている。
「え、だって……」
考えてみたら、画面のどこにも「日本の」風景とは書かれていない。
いや、でもここは広葉樹林だ。パンダは竹林にいるイメージなのだが。
「……ふっ」
隣の男性が、信じかけている沙也香を見て、こらえきれなかったという様子で、小さく笑った。
「やっぱり! 嘘つき!」
「いやホントに。あははは」
しょうもないことで笑い合っているうちに、さっきまでの不快さはすっかりどこかへ飛んでいっていた。
沙也香が美術専門学校卒業後に、株式会社久保フードサービスで働き出してから、もう七年になる。
首都圏を中心に、居酒屋やカフェをチェーン展開している会社で、広告宣伝部は、沙也香を含めて四人の部署だが、グラフィックデザイナーは沙也香だけだ。
三つ年上の部長、久保大和は、ビジネスマンにしては長めの茶色がかった髪と人形じみた美形で、人目を引く存在だ。そのうえ現社長の息子なので、モテるなんてものではない。
のだが。
「――部長。久保部長ーっ! 起きてください!」
「うう……」
「ちょっと、メニュー作ったので、見てくださいってば!」
「増村さんの美声が、頭蓋骨にガンガン反響してくる……俺の前世、銅鑼かよ……」
久保部長は三十を越えても落ち着く様子がまるでない。毎晩のように合コンに参加して、プライベートの連絡先をバラまきまくっているらしい。
今日も、昨晩の酒を引きずってヨレヨレになっている。
まったく、キラキラした目で部長を見てくる他部署の女の子たちに、机に突っ伏したこの姿を見せてやりたい。
「美声って言っておけば仕事しなくていいわけじゃありませんよ。働いてください。ほら、頭が低い」
「ピザって百回言って」
「肘。居酒屋の冬限定メニューの鍋です。ほーら、美味しそうですよー」
通常メニューに挟み込んで使う、一枚もののメニューだ。商品部が実際の鍋を作り、食べ物専門のカメラマンに写真を撮ってもらって、沙也香がデザインをした。
「増村さん、冷たい……うう……」
久保部長は唸りながら顔だけなんとかこちらに向けた。
「おお、すっげー美味そう……いいと思います……」
「それじゃ、このまま進めますね」
こんなにヨレヨレでも、ダメなときはダメだと言うひとなのはわかっているので、ホッとした。
「増村さん、その鍋出たら、ふたりでしっぽり食べに行こうね……」
「セクハラですし、こんなヨレヨレしたひとと食べに行くの、普通に嫌です」
「俺、オンオフの差が激しいんだよね」
「いや、いまオンですよね!?」
「オフのときはビシッとしてるんだ」
「そうですか……」
広告宣伝部のあとのふたりは、店舗やメディア関係などへ外出していることが多い。そのため久保部長とふたりでいる機会は多いが、他の人の目がないときにビシッとしているところは、ほとんど見たことがない。
気を取り直して、パソコンに向かおうとしたときだった。
「沙也香ーっ」
元気よく広告宣伝部に入ってきたのは、同期で人事部に所属している松下琴美だ。二十人近くいる他の同期は全員店舗勤務だから、唯一の本社仲間ともいえる。
琴美は、背が高めで黒髪ロング、パンツやロングスカートを着ていることが多い沙也香とは対照的に、ふわっとした膝丈スカートのオフィスカジュアルがよく似合う、女性らしいタイプだ。男性から人気があるのに、もう三年近く、一回り以上年上の人事部長と不倫している。
正直もったいないなと沙也香は思っているが、いい大人同士の話なので口出ししたことはない。
「ちょっとお願いがあるんだ」
琴美は、席を外している社員の椅子を引き寄せて、沙也香の隣に座った。
「なに?」
沙也香はチラリと久保部長の方を見た。いつのまにかピシッと背中を伸ばしてパソコンに向かっている。
まったく外面がいいったら。
「いま就活生用のサイト作ってるんだけど、そこの『現役社員紹介』コーナーに出てほしいんだよね。写真とインタビューで」
「えぇ……」
あまり気は乗らなかった。
ああいうところに載るのは、もっと仕事熱心で輝いている社員なんじゃないだろうか。
「ほら、広告宣伝部って、なんか響きがかっこいいし、沙也香美人だし。店舗社員ばっかりじゃなく、こういう社員もいるって、就活生に見てもらいたいんだ」
沙也香は苦笑いしてしまった。
たしかに広告代理店に憧れるような就活生の目を引くかもしれないが、沙也香が実際にやっている仕事は、地味なものだ。
久保フードサービスの全業態のメニュー、ショップカード、チラシ類や看板、名刺などひとりですべて作っても、正直たいした量ではない。だから、広告宣伝部の他の社員の仕事を手伝っても、毎日定時で会社を上がれている。
「グラフィックデザイナー」と一言で言っても、デザイン事務所に勤務してそれだけを専門にしているひとたちとは、やっていることが全然違うのだ。
美術専門学校の友達は、みんな就職に苦労していた。デザインとまったく関係ない仕事に就かざるを得なかった友人も少なくなかった。
だから、グラフィックデザインを仕事にすることができてありがたいと思っているのは本当だし、会社の居心地や待遇も悪くない。
自分の現状に、大きな不満はない。
それでも、胸を張って学生たちの前に出られるのかと聞かれると、答えに詰まる。
「というわけで、来週辺り時間ちょうだい。二時間くらい。そのとき写真も撮るから、化粧気合入れてきて」
「わかった、わかった」
どうやら拒否権はないらしい。
その週の土曜日、沙也香は湾岸エリアにあるタワーマンションのひとつにやってきていた。
目の前は海なのでとても見晴らしがいいこのマンションには、美術専門学校時代からの友人、夏川香奈が住んでいる。彼女の夫である亮と、五歳になる白猫のフッフール、三歳の娘の千紗も一緒だ。
沙也香が一人暮らししているアパートは、ペットの飼育が禁止されている。なので月に二、三度は夏川家に遊びにきて、猫を堪能するのが、沙也香の癒しだった。
「フッフールー、今日も可愛いねえ、可愛いねえ」
ソファでくつろいでいるフッフールの胸に顔を埋めて、思い切り息を吸い込む。フッフールは、まあ好きにさせておいてやるかという感じで、小さくあくびをしている。
「沙也香ちゃん、千紗も、千紗もすーっしてー」
「いいよぉ、千紗も可愛いねえ、可愛いねえ」
フッフールにしたのと同じように、小さな胸に顔を埋めて思い切り息を吸ってやると、千紗はウキャウキャと声を上げて喜んだ。
可愛い。
結婚したいとか、子供が欲しいとか、そういうことはまだそこまで思っていないが、千紗のことは新生児の頃から見ているせいか、特別可愛いと思っている。ほっぺなんて、お餅のようだ。
「香奈もしようか?」
「遠慮しとくー」
カラカラと幸せそうに笑っている香奈は、絵本作家だ。在学中にコンテストで大賞を取って以来、半年に一度は新作を出版している。
「亮さんは? 仕事?」
「うん。撮影入ったって」
「そっか」
沙也香は顔には出さなかったが、少しだけホッとしていた。
香奈の夫は、業界で知らないものはいない、グラフィックデザイナーだ。自分の事務所を構えて、何人も人を雇っている。
沙也香の名刺にも、肩書のところに「グラフィックデザイナー」と書いてあるが、やっていることは彼と全然違う。
亮はいいひとだから、会えば「グラフィックデザイナー仲間」という感じで沙也香に話を振ってきたりするのだが、そのたび何とも言えない気分になる。
「ねえ、お昼パスタでいい? 沙也香が持ってきてくれたモッツァレラチーズ、すごい美味しそう」
「美味しいよー、ウチのイタリアンの業態で使ってるやつ。社販で半額だったから買っちゃった」
会社では、賞味期限が近づいた食材や、メニューが切り替わったときに残った季節商品などが不定期で社内販売される。かなりお買い得なので、毎回大人気だ。
「じゃ、ミニトマトとバジルを収穫して、冷製パスタにしよう」
香奈がベランダに出る窓を開いた。ワイドスパンのベランダには、端から端までコンテナやプランターが置かれ、様々な野菜が栽培されている。
こういうところ、香奈はまめだよなと思う。自分には絶対真似できない。沙也香はエアプランツすら枯らした女だ。
香奈と千紗が、仲良くベランダで昼食に使う分の野菜を収穫している。
のどかな光景だ。
幸せそうでなによりだと思うし、正直少し羨ましい。
ひとり暮らしも、気楽で悪くはないのだが。
男性にはそこそこ縁のある人生を、いままで送ってきた。
直近では、半年間ほぼ同棲していた恋人がいたが、別れてもう一年近く経つ。
一年以上付き合いが続いたひとは、いままでひとりもいない。
二十七までこんな調子なものだから、さすがに恋愛にはあまり向いていないらしいと自覚してきた。
ましてや結婚なんて、できる日が来るとは思えない。そういうことを急かしてくるような親じゃなくてよかった。
冷製パスタを食べ終え、まったりと紅茶を飲んでいたとき、その電話はかかってきた。
『――姉ちゃん、どうしよう』
スマホの向こうから聞こえてきたのは、いまにも泣き出しそうな弟の声だ。
嫌な予感しかしなかった。
「……なに」
とは言ったが、全然聞きたくない。
『あの……俺さ、就職活動始めるじゃん?』
「うん」
『それで……たいした大学じゃないし、武器っていうか、売りっていうか、そういうあれがあった方がいいのかなって思って……』
弟の話し方は要領を得ない。
「それで?」
と、トントンと指先でテーブルを叩きながら先を促す。
『やっぱりこれからの時代は、英語だって言われて……俺もそうかもって思って……』
「は? いまから英語?」
沙也香は耳を疑った。
「いや、遅いでしょ。英語力をつけたかったなら、もっと前からやってないと」
『俺もそう思ったんだけど、いい教材を使えばまだ間に合うって、二人がかりで説得されてさあ……俺もだんだん、まだいけるかもって思っちゃって、だから、その……』
「ハッキリ言いなさい」
『……英会話教材買っちゃった』
目の前が暗くなった気がした。
「いくら」
『……三十六万。姉ちゃん、どうしよう』
「どうしようって、あんた……」
沙也香は頭を抱えた。
向かいで千紗が沙也香の真似をして、香奈に「やめなさい」とたしなめられている。
弟は気のいい、優しい男だ。
ただちょっと、押しに弱くて考えが足りない。
そして沙也香は、どんなに「馬鹿なやつめ」と思っても、弟に泣き付かれると弱い。
以前、同額くらいの版画をキャッチセールスに買わされてきたときは、まだ未成年だったから、沙也香が前に出てクーリングオフさせた。
今回はどうだろう。
学生とはいえ、弟はもう成人している。契約は成立してしまうんだろうか。
「……明日帰るから、契約書とか、全部用意しておきな」
ため息まじりにそう伝える。
「ありがとう、姉ちゃん」
弟は小さな声で言い、電話は切れた。
「……豊くん、またやっちゃったの?」
香奈が心配そうに尋ねてきた。
「うん。馬鹿な弟を持つと、苦労するわ……」
ネットワークビジネスやら新興宗教やら、弟は様々なものを引き寄せる。なにかそういう物質でも体から滲み出ているんだろうか。
「明日実家帰って、詳しく聞いてくる」
「そっか、お疲れ……」
「沙也香ちゃん、帰っちゃうの?」
「ううん、まだ帰んないよ」
沙也香は千紗を抱き上げてポンポンと背中を叩いた。
今日は土曜だ。明日のうちに契約書と現物をちゃんと見ておいて、明後日の月曜、法テラスにでも行って相談してみよう。