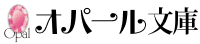エリートパイロットは身代わり妻を離さない 6
第六話
──こんなに暇って、人生のうちで初めて。
身代わり妻になっている間は仕事に出ることもできないし、詐欺事件のせいで数少ない友人とも疎遠になったので、ほぼ一日中マンション内で過ごしている。
することといえば、掃除、洗濯、食事作りの一般的な家事のみ。多くは午前中で済むから、時間を持て余し気味だ。
そうなれば、頭の中には自然に悠人のことが浮かんでくる。彼の柔らかい笑顔と耳に心地いい声、やさしい手も、見つめてくる目も、穂香の思考を埋め尽くす。
胸の中でくすぶっている悠人への気持ちは、暇であればあるほどに大きくなっていく気がする。
──このままじゃ、ダメだ。誰かと会ったり、なにかをしないと!
そう感じた穂香の脳裏に浮かんだのは、桜坂真奈美だった。
イタリア大使のパーティ後、悠人は『桜坂さんの奥さんとなら、親しくなってもいいよ』と彼女の連絡先を伝えてきた。
『ふたりはいい友人になれそうだ。よかったら、仲良くさせてもらいたい』
真奈美の夫である伊織がお願いしてきたそうで、連絡先を渡したことは彼女も了承してるとのことだった。
真奈美とは親しくなりたいと思っていたので、大変ありがたい申し出だった。こちらからお願いしたいくらいだと、感謝の気持ちを込めながら彼女に連絡をしたのである。
そんなわけで今……。
「あっ、桜坂さん!」
マンションから遠く離れた都内の主要駅構内。穂香は人波の中に真奈美の姿を見つけ、手を振って合図した。
「上月さん、よかった。今日はメガネをされてるから、一瞬見間違えました。場所はすぐにわかったんですね」
真奈美はほっとしたような笑顔を見せるが、うっかりメガネをしてきた穂香は少々焦っていた。
「いつもはコンタクトなんですけど、今日は気分的にメガネなんです」
フフフと笑ってごまかすと、真奈美は「そういう日もありますよね」と、さらりと納得してくれる。
現在身代わり妻として生活しているのは空港近くのマンションだが、穂香はもともと都内に住んでいた。
待ち合わせの駅は、いつも利用していた通勤電車の路線である。迷子などなりようがない。
しかし、そんなことは真奈美には言えない。
「それに、こちらにはよく遊びに来ていたもので、ちょっとだけ土地勘があるんですよ」
「そうなんですか。それじゃあ、料理教室のあたりもご存じかもしれませんね。行きましょうか。ここから近いんですよ」
歩いて行けるんですと、真奈美は先導するように歩き始めた。
パイロットの仕事は不規則勤務だ。
国内線は往復便なので一日で勤務終了だが、国際線は四日から五日ほど帰ってこない。
このほかスタンバイという勤務もあって、何らかの理由でパイロットに欠員がでればフライトを代わる。それが国際線のフライトなら、出勤してそのまま二日から三日間帰ってこないこともある。
ということで、悠人は副操縦士といえども腕の良いパイロットのためフライトが多く、ほぼ家にいないというありさまだ。
多くの人の命を預かるパイロット。長時間気の抜けない仕事である。国際線では時差もあるから、体調管理が大変だろう。
知れば知るほど悠人の仕事の貴重さと重責さを感じ、いてもたってもいられない気持ちになる。
だから毎日何事もないように祈るし、帰宅したときは大いにねぎらい、手料理を振る舞ってあげたいと思うようになった。
こういうのは、恋心とは別である……はずだ。
同じ屋根の下で生活するなら、相手を敬って気遣うのが大切だと思うのだ。人命を預かる仕事をしている相手ならば余計に。
そんな思いを真奈美に話したら、自身が通っている料理教室の体験に誘ってくれたのだった。
「ここですよ」
ほどなく着いた雑居ビルには、外国語や音楽など、様々なカテゴリの教室が入っていた。
その中でフランス語の教室を見つけ、今回の悠人のフライトがパリ行きだったことが頭に浮かび、遠い空の向こうに思いをはせた。
彼が帰宅するのは明後日の予定だ。
──そのときに、ここで教えてもらった料理を作ってみようかな。
「こんにちは。はじめまして。上月清美です」
エプロンをつけて挨拶をすると、先生が目じりにしわを寄せた。
「今日の料理は和食をアレンジしたものなんですよ。楽しんでいってくださいね」
料理教室は和食から洋食まで教えてくれるという。料理本を出している著名な料理研究家で、通う人は主にセレブのマダムだった。
──だからか、月謝もお高めなのね……。
食材費が別料金で交通費を含めればかなりの出費になるが、穂香には身代わり妻の多額な謝礼金とヤククソのパリ旅行で使い損ねた貯金が残っている。
それは悠人がお得な情報を教えてくれたから残ったわけで、謝礼金もここで使うのは正解だと思える。料理教室に通うのは、彼のためでもあるのだから。
しかし、通うには教室仲間の雰囲気の良さも重要である。
──彼が信用している桜坂さんのおすすめだから、決して悪くないと思うけれど。
「みなさん、お教室は楽しいですか?」
「ええ、もちろん。こうして集まってお話しするのも楽しみの一つよ」
「そうそう。家にいると、暇にあかせて余計なことばかり考えてしまうもの。忙しくしていないと、ダメよね」
教室に通う理由が穂香と似通っていて、にわかに親近感がわいた。
真奈美は子育てで忙しい中でも、料理を習いたいために通っているそうだが、三十人ほどいる生徒の大半は子育てを終えている世代である。
生徒たちは珍しい外国産の食材を使ったり、先生の考案した創作料理を習うのが楽しいと口をそろえて言う。
「ここで覚えた料理を家で作ると、大変喜ばれますのよ」
少し年配のマダムが上品に微笑む。
作った料理を食べながらのおしゃべりはたわいのない世間話で和気あいあいとし、ありがちと思えるご主人の職業に関するマウントもない。
作った料理もおいしく真奈美とも楽しく過ごせた穂香は、教室に通うことに決めたのだった。
今日は悠人がパリ直行便のフライトから戻ってくる日だ。
穂香は教室で教わった料理を作るべく食材を買い込み、お気に入りのエプロンをつけてキッチンに立った。
空港に到着する時間は午後二時頃。フライト後のデスクワークを終えて帰宅するのは、夕方近くになるはずだ。
疲れて帰ってくる悠人のために最高の食事を用意し、お風呂も沸かして、すぐに休めるよう準備万端にして迎えるつもりだ。
「えっと、まずは……」
スマホに保存したレシピを見返していると、着信メロディが鳴り始めて心臓が跳ねた。
──知らない番号だけど……?
普段なら無視するのだが、繰り返し着信があるのはただならぬ事態を想起させた。穂香の携帯番号を知っているのは、悠人を含めてごく少数だ。発信者は誰か。
「……はい、穂香です」
『上月です』
電話は悠人の父、雄三だった。
『落ち着いて聞いてください』
雄三の声音には穂香だけでなく、自らを言い聞かせているような震えがあると感じる。
──なんだろう。嫌な予感がする。
「……はい」
『これから悠人が危険な着陸を試みます』
「えっ、危険とは、どういうことですか!?」
スマホを持つ手が震え、体中の血がサーっと引いていく。気が遠くなるような状態の中、耳は必死に雄三の言葉を拾っていた。
『機長の体調が悪く、悠人がメインで操縦桿を握っているんですが、飛行機前部の車輪が出ないんです。幸い後部左右の車輪が出ますので、水上ではなく滑走路におります。ですが、最悪の場合は飛行機が炎上します』
「そんな……!」
『それを……』
穂香はスマホをぽとりと落としてしまった。画面にはまだ通話中の表示が残っているが、胸中に広がる暗雲に苛まれてスマホを拾う余裕がない。
──どうしよう。彼がけがをしたら、どうしよう。
それどころか、最悪の場合は……燃え盛る炎で……。
飛行機が壊れて火に包まれるコクピットと、着陸のショックで気を失った悠人の姿が脳裏に浮かんだ。
「嫌っ!! そんなのダメ!!」
青ざめた穂香はガタガタ震えながらもスマホを拾ってバッグに突っ込み、コートを引っかけるように羽織って家を飛び出した。
──行かなくちゃ。私が行ってもどうにもならないけど、それでも!
今は午後二時をまわったところ。予定通りなら着陸態勢に入っているところだろう。タクシーでは時間がかかる。特急電車に乗るしかない。
駅まで全速力で走り、息を切らせながら改札を通った。
ホームに滑り込んできた空港行の電車に飛び乗り、ドアの横に立つ。
これならば空港まで十分足らずで着く。だが、これでも飛行機の着陸に間に合わないかもしれない。
──どうか。どうか。悠人さんが無事に着陸できますように……!
移動中も祈るように手を組み合わせ、停車駅で止まるたび、早く扉が閉まるように念を送った。
電車がホームに滑り込んでいき、ドアが開くと同時に全力で走って空港内に急ぐ。
息が切れ、日ごろ運動とは縁のない穂香の肺が破れそうになる。それでも足を止めることなく走り続けた。
──悠人さんっ、悠人さん!
胸の中で必死に彼の名を呼び、JSLのスタッフを捜した。十二月半ばの空港内にはスーツケースを手にした人が多く行きかい、普段と変わりない様子に見える。
そんな中、悠人と再会したときにJSLの部屋に案内した黒服の男性を見つけた。彼ならば、穂香のことを覚えているはずだ。
「すみません! そこのあなた!」
ゼイゼイと息を吐きながら早足で歩いている彼の前に立ちはだかり、すかさず口を開いた。
「悠人さんは、飛行機は今どうなってますか!」
肩で息をする穂香の迫力に一瞬ひるんだ様子の彼は、「あなたは……」とつぶやいた後スッと真面目な表情になり、「落ち着いてください」と諭した。
「今は、万が一の大規模な炎上を免れるために、燃料を消費するべく上空を旋回している状態です」
胴体着陸は成功しても火花が散るため、燃料に引火して爆発することがあるという。
黒服の彼はこういう事態に慣れているのか、妙に落ち着いている。
「燃料が少なくなれば、着陸は安全なんですか? 私、心配で……心配で……いてもたってもいられないんです」
「旋回している間に何度か車輪を出す試みをすれば、出ることも多々あります。僕は社長秘書の遠(えん)藤(どう)と申します。パイロットの腕を信じましょう。よろしければ、展望デッキにご案内しますよ」
遠藤とともに、展望デッキへ急いだ。
デッキには規制が張られているため、空港スタッフなど航空会社の関係者しかいないようだ。みんな不安げに空を見上げている。
晴れていたはずの空は厚い雲がかかっていて小さな雪が舞い落ちてきた。
滑走路のそばには放水車と救急車など、複数の車がスタンバイしている。
「今日は横風も吹いてるし、ちょっと厳しいかもな」
他社パイロットの制服を着た人のつぶやきが聞こえ、穂香の不安が増大した。
「でも機長は旗本さんだ。副操縦士も上月さんなら、上手くランディングできるんじゃないか」
見物している中には少なからずのパイロットたちがいる。その人たちの会話から、風の状況が悪いために、飛行機を水平に保つのが難しいことが伝わってきた。
同時に、他社パイロットたちから〝機長も副操縦士も腕がいい〟という評価を得ていることも。
「大丈夫ですよ。機長の旗本はベテランのパイロットです。たとえ体調が悪くても上月パイロットと一緒に全力を尽くしますから」
遠藤の落ち着いた声が穂香の不安を和らげる。
「……悠人さん……頑張って」
パイロットたちが懸念している風は一向にやまない。穂香には毎日吹いている冬風と同じに思えるが、日ごろ操縦桿を握っている彼らにとっては注意すべき状況なのだろう。
「あっ、来たぞ」
誰かが空を指差した。尾翼にJSLのマークのある機体が、滑走路を目指してどんどん大きくなってくる。
心なしか機体が斜めになっていて、ふわふわと上下に揺れているように見える。
遠藤が風の影響で揺れる機体を細やかな操縦で水平に保っていると、穂香に説明してくれた。
「さすがに上手いな」
「あぁ、でも不味いな。前輪が出てない」
パイロットたちの会話で、デッキ上の空気がシンと張りつめた。
車輪を出すことに失敗した飛行機が徐々に高度を下げてくる。風にあおられるのか、機体が傾きかけたり水平になったりして、悠人たちの努力がひしひしと伝わってくる。
穂香はぎゅっと唇を結んで手を組み合わせ、飛行機を凝視してひたすらに着陸の成功を祈った。