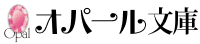エリートパイロットは身代わり妻を離さない 5
第五話
時はあっという間に過ぎ、イタリア大使のパーティの日がきた。
穂香はメガネを外してコンタクトに替え、悠人が見立ててくれた総レースのドレスに身を包む。ピアスをつけ、清美の写真を参考にしながら、華やかに見えるようなメイクをした。
そうすれば、いっそう彼女に似た自分の姿が鏡に映っている。
今日は如月穂香ではなく上月清美だ。誰に会っても、ぼろを出さないように努めないとならない。
──自分では化けるのに成功してると思うけど。悠人さんの反応はどうかな。
リビングに行くと、悠人はすでに支度を終えてソファに座っていた。
三つ揃えのブラックタキシード姿が様になっている。彼はどこでどんなスタイルをしていても絵になる。悔しいくらいのイケメンだ。
穂香に気づいて立ち上がり、こちらに向かってくる彼は、レッドカーペットを歩くハリウッドスターのようだ。
「悠人さん、どうかな?」
「ああ、とても綺麗だ」
彼は目を細めて微笑む。けれど、その褒め言葉に複雑な気持ちになる。
清美に似ているのだから、褒められたのは穂香だけじゃないのだ。穂香の影には、いつも清美がちらつく。
「ん? ネックレスはどうした?」
不思議そうに首をかしげる。
「実は……金具が小さいから、自分でつけるのが難しくて……」
不器用なのが申し訳ない。おずおずと手に持ったネックレスを見せると、悠人はくすっと笑う。
「いいよ、貸して」
彼に背を向けてうなじを出すと、するっと回された手が穂香の首をかすめた。
男性的な長い指が自分の肌に触れそうで触れなくて、その危うい状況に首筋がゾクゾクしてしまう。
──やだ、またドキドキしてる……静まって、私の心臓。
「よし、できたよ。完璧だ」
「ありがとう」
「じゃあ、行こうか。今日はなにがあっても俺が守るから、きみは堂々として、微笑んでいてくれればいい」
「うん。なるべく、しゃべらないようにするね」
時刻もちょうどいい。
初陣に赴く騎士のような心持ちで、悠人とともにパーティ会場へ向かった。
駐日イタリア大使館。
都心にあるにもかかわらず緑豊かなここは、江戸時代に松平隠岐守の中屋敷があったところだという。
エントランスに施されたイタリア国旗のイルミネーションが、夕暮れの薄闇に映えてとても美しい。
「庭にある池は、数名の赤穂浪士が自害した場所を掘り起こして作られたそうだよ」
「えっ、ほんとに?」
「池のそばにある小山に事件を記した記念碑があるんだ」
車寄せから会場に向かう道すがら、悠人が豆知識を教えてくれる。実際に見せてもらったこともあるらしい。
歴史的な曰くのある場所がイタリアの大使館になっているのは、なんだか不思議な気分である。
「悠人さんは何度もここのパーティにきたことあるの?」
「イタリア料理週間のディナーとか、来日した歌劇団のレセプションパーティくらいかな。大使といっても、とてもフレンドリーだから、穂香も緊張しなくて大丈夫だ」
とはいえ、パーティ会場は多くの招待客でいっぱいだ。
広大な庭園と広間が解放されているのに、どこを見ても正装の紳士と着飾った淑女たちが目に入る。
──この中に、清美さんの知り合いが絶対にいるよね……。
顔見知り程度ならばいいが、友人に会ったら終わりではないか。
そう思えばどんどん緊張が増してきて、手のひらにじんわりと汗がにじんでくる。知らずにきょろきょろして、落ち着きがなくなっていく。
そうすれば、右手に外国の方と談笑している初老の紳士が目に入ってぎょっとする。
「えっ、あそこにいるお方は、もしかしなくても総理大臣?」
「ああ、そうだね。あちらには、財界のドンと呼ばれる人物がいるよ」
悠人が示す左方向には白髪の紳士がナイスミドルたちに囲まれていた。
「ほんとだ。ニュースで見たことある……」
予想はしていたが、どちらを見ても政界と財界の著名人たちがいて、穂香は緊張して息をするのも忘れそうになる。
始まる数分前には皇室の貴婦人まで登場されて、気が遠くなる空間となった。付け焼刃の気品と演技で対応するのは不安しかない。
「あああぁ、どうしよう」
もはや泣きそうである。
「穂香、背筋を伸ばして、自信もって。それに守ると言っただろう? 俺のそばから離れなければいい」
「……悠人さん……」
頼りがいのある言葉に感激してうるっとし、見つめると優しい瞳を向けてくれる。
穂香が困る場面に、悠人は必ず助け舟を出してくれる。そう確信することができた。
──彼から離れなければ、大丈夫だ。
イタリア大使の挨拶と乾杯のあと、食事と歓談の時間に移る。庭園はそこかしこにかがり火がたかれ、十二月といえども暖かい雰囲気を醸し出している。
庭園にも多くの人が出て談笑を始めた。
JSLの御曹司である悠人には、各界の著名人たちから積極的に声がかけられる。
与党の政治家や有名企業の社長などの大物を相手にしても、悠人は畏まってはいるが堂々と会話をしている。
時折穂香の容姿をほめちぎられるので、引きつりながらも笑顔を貼り付けた。
「まあ、奥さま、お久しぶりでございます。今日は体調がよろしいんですか?」
見知らぬご婦人から声をかけられるが、久しぶりというならば、知り合いなのだ。穂香の心臓がバクバクと脈打つ。
おそらく五十代前半くらいで、穂香の母と同年代だと思える。友人の親だろうか。それとも取引先の社長夫人か。
「ええ、今日は、いくぶんかは」
言葉短く答えてひたすらに微笑むと、ご婦人がふと真顔になり「そういえば」と言葉を継いだ。
「ご存じですか? 真城のお嬢さまのこと。奥さまは大学時代のご友人でしょう? なにか進展はございますかしら」
──真城? 誰? なにかあったの? なんだか不穏な感じだけれど?
こんな場で出す話題ならばネガティブなことではないと思うが、セレブの世界は常識とは違うかもしれない。冷や汗が出る。
もっと清美の友人関係について聞いておけばよかった。とはいえ、悠人もそれほど詳しくないのが実情だろう。
なにせ彼は、清美の仕草や口癖もわからなかったのだから。
焦る穂香とご婦人の間にすっと悠人の腕が割り込んだ。
「ご婦人、申し訳ありません。彼女はまだまだ本調子ではないので、あまり体力を使わせたくないのです。会話を差し控えていただきたいのですが」
スマートに制してくれる。
「えっ?」という表情をしたご婦人を見て、穂香はハッとして口元を押さえ、少し気分悪そうにしてみた。
「あらまあ! そうですの! もしかして、めでたくていらっしゃるのかしら。それならば大事なお体ですもの。気が付かなくてごめんなさいね」
なにか勘違いした様子のご婦人は大仰に言ってバチンとウインクした。
「とても仲がよろしいご様子で、私までハッピーになりましたわ。では奥さま、お体を大切になさってくださいませ!」
ご婦人はうれしそうに去っていき、近場にいた初老のご婦人と会話を始めた。
「……授かってるって思われたみたい?」
「そうらしいな。でも構わないよ。わざわざ否定することもない」
誤解の噂が広まってもいいのだろうか。そう思うけれど、彼が必要ないというならばどうしようもない。
歓談のさなか、突如として会場の中心付近から歓声が上がった。
悠人の体の陰からそちらを覗くと、人の輪の中心でイタリア大使ご夫妻がダンスを踊っていた。
ゆるやかに流れるメロディはワルツだ。夫妻は、あのときに悠人が教えてくれたステップを優雅に踏んでいる。
笑顔で楽しそうに踊る二人にひかれて、手を取って踊り出す人が現れ始めた。なんと、総理大臣夫妻も加わっている。
──うっ、やっぱりダンスするんだ……。
懸念していた通り、社交の必須項目なのだ。思わず身を縮ませる。
目立たないようにしていれば、誘われることはないだろう。
そう思っていたのだが、ダンスの輪から視線を外して向き直ったら、正面にいた若い男性がにこっと笑いかけてきた。
この男性は、さきほど与党政治家のご子息だと紹介された人である。
「上月夫人の清美さんは、社交ダンスに長けているとお伺いしています。よろしければお相手をお願いしたいのですが。いかがですか?」
──ええっ!?
穂香は声にならない叫びを呑み込んだ。
「社交ダンスの大会では上位に入賞されたと、耳にしていますよ。私もダンスを始めて五年になるんです。ぜひ、ご教示お願いしたいのですが」
清美にそんな特技があったなど、知る由もない。断れずに踊ってしまったら即ばれだ。血の気がサーっと引いていく。
──どうしよう。どうすれば? 足を痛めていることにする?
あわあわする穂香と笑顔でぐいぐい迫ってくる政治家子息の間に、スッと悠人が入り込んだ。
「申し訳ございません。彼女は、いまだ体調が優れませんので、ダンスのお相手はご遠慮申し上げます」
「……そうですか。そういえば、顔色が優れませんね。残念ですが。清美さん、またの機会にお願いします」
心底残念そうにして彼は去っていった。
危機を脱した穂香は、ほっと息を吐く。まったく心臓に悪い場だ。早く帰りたいと願い、遠い目をした。
でも、彼が穂香の前に立ってくれたとき、フランスで助けてくれた姿と重なった。
「ありがとう。悠人さん」
穂香が声をかけられると悠人がすかさずフォローに回ってくれる。彼のそばにいれば不安はないのだ。
「上月さん、お久しぶりです」
話しかけてきたのは悠人と同世代の男性だ。見上げるほどの身長に、気品ある穏やかな雰囲気。お隣に綺麗な女性を伴っている。
「これは、桜坂さん。ゴルフコンペ以来ですね」
笑顔で応じる悠人は、先ほどまでの畏まった感じと違って砕けたムードがある。親しい間柄のようだ。
「こちらは、桜坂グループの桜坂伊織さんと、奥さまだ。彼女ときみは、気が合うと思うよ」
「はじめまして、桜坂の妻の真奈美です」
にっこり笑ってくれる彼女は優しげで、おとなしい印象を受ける。
ちらりと悠人を見れば、微笑んでうなずいている。この人とならば、自由に話をしてもいいらしい。信用できる人なのだろう。
「はじめまして。ほ……いえ、清美です。よろしくお願いします。たどたどしくてすみません、緊張してしまって」
ふぅっと息を吐いて胸のあたりに手を添えた。
本来なら、生粋のお嬢さまである清美が緊張することなどないだろう。けれど真奈美に対しては警戒心が外れ、素が出てしまっている。
失敗したと思ったが、真奈美はうれしそうに一歩近づいてきた。
「わかります! 私もなんですよ。この独特のセレブな空気には、もうずっと、全然慣れないんです」
真奈美には同じ空気を感じるというか、とても話しやすい雰囲気を持っている。
「イタリア語がわからないから、話しかけられても笑うしかなくて。今日に限らず、こういう場では伊織さんに頼ってばかりなんですよ」
彼は外国語が堪能だと、照れたように笑う真奈美は心から夫のことを信頼しているようだ。
常日頃から守られているのだろう。しあわせな生活を送っていることがひしひしと伝わってくる。
「桜坂さんのご主人、やさしいんですね」
伊織は悠人と会話をしながらも、時折真奈美に視線を送っている。それに気づいて、思わずニマニマと笑ってしまう。
「そういう上月さんこそ。さっき見てましたよ。ささっと守られてましたよね? まるで姫を守るナイトみたいでしたよ」
「ナイト……そうかも! 彼に初めて会ったとき、王子さまみたいって思ったんです」
「そういえばうちも! 娘がパパは王子さまだよねって、いつも言うんです」
穂香と真奈美は談笑する悠人と伊織を見た。
タキシード姿の美男子はまさに貴公子だ。ふたり向き合って話している様子は社交界の華といえよう。
「じゃあ、私たち、お姫さまでいいのかな?」
真奈美と顔を見合わせて、ぷっと噴き出した。
──このパーティで、こんな冗談が言えるなんて。
穂香はくすくす笑いながら、緊張や焦りが吹き飛んでいることを自覚していた。VIPぞろいの会場内で、唯一気遣わずに話せている。
「娘さんがいらっしゃるんですね」
「ええ、もうすぐ六歳になります」
楽しくかわす会話の途中で、穂香はふと真奈美のドレスのリボンが気になった。
「桜坂さん、背中のリボンが解けそうになってます」
「え、やだ……どうしましょう」
「お化粧室で直しましょうか」
悠人に「場を離れる」と声をかけると、「いっておいで」とうなずいた。
真奈美と一緒に化粧室に向かい、背中のリボンを無事に直すと、彼女は個室にも入るという。
失礼して先に出た穂香は、男性の化粧室から出てきた悠人の父、雄三に出くわした。彼もパーティにきていたとは、思っていなかった。
──見かけなかったのに……。
「ご無沙汰しています」
「どうですか。上手くやれてますか」
心配で気になっていたらしい。
「悠人さんが気遣ってくださるので、大丈夫です」
笑顔で答える穂香に対し、雄三は厳しい顔つきになった。周りを見渡し、誰もいないことを確認すると声を潜める。
「あなたには、くれぐれも立場をわきまえてくださるよう、願います。決して清美に取って代わろうなどと思わないでください。今回の件がどんな結果になっても、悠人にはふさわしい家の女性と連れ添うように言っていますので」
どうあっても、会社にとってお得な女性としか結婚させないということだ。
「わかっています」
思わず憮然としてしまう。『悠人に惚れるな』なんて、そんなことは注意されなくても肝に銘じているのだ。
それに、悠人も穂香とどうにかなりたいと思っていないはずだ。胸がチクッとするが仕方がないことだ。
「それでは、くれぐれも、頼みますよ」
念を押すように言い含め、雄三は会場へと戻っていった。彼は息子の幸せを考えていないのか。穂香は少なからずの憤りを覚える。
思う相手と結婚できないのは、中世の王子さまと一緒だ。そんなところまで王子然としなくてもいいのに、と思う。
「すみません、お待たせしました」
真奈美の笑顔を見るとほっとする。彼女の今までの言動から、政略結婚とは違う形で彼との愛を育んだとわかったからだ。
──しあわせそうで、ほんとうに素敵。
真奈美とは、もっと親しくなりたいと思えた。
「戻りましょうか」
会場内では、悠人が変わらずに伊織と笑顔で話をしていた。真奈美とともにそばに戻ると、スッと腰に手を回してきた。
そのままそっと引き寄せられて、彼との距離がいっそう近づく。あくまでも自然な行為だ。
このやさしい腕は、穂香を心配してくれたものなのか。それとも会社のために、周りに体裁よくするためか。
こんなことを考える自分は、やっぱり彼に惹かれてしまっているのだ。
淡い恋心を自覚するも、その場はなんとか蓋をした。
◆◇◆◇
シャルル・ド・ゴール国際空港。二十時二十分。
ほぼ定刻通りに滑走路に入り、無事にタッチダウン。車輪が地面を捕まえ、速度がゆるやかになっていく。コクピット内の緊張が解ける瞬間だ。
飛行機は上空で安定飛行に入れば自動操縦に切り替えられるが、離陸と着陸はパイロットの操縦でなされる。
安全な離着陸を行うには、天候条件に対応する技術と予期せぬトラブルに対する的確な判断が必要だ。
腕のいいパイロットとなるには豊富な経験がものをいう。
「上月くん、ナイスランディング」
悠人は握っていた操縦桿から手を放して一息つき、旗本機長に笑顔を返した。
「ありがとうございます」
柔和な笑顔をくれる旗本はこの道三十年のベテランで、悠人がもっとも尊敬しているパイロットだ。
飛行機は飛び立てばどこかに着陸せねばならない。どんな条件でも、事故なく安全にするのがベストである。
旗本は台風並みの悪条件の中でも、一度もゴーアラウンドせずにランディングさせることで有名だ。パイロットとしての判断力と技術は、天下一といっても過言ではない。
惜しげもなく自分の経験と技術を悠人に教授し、最近ではよほどの難条件でない限りすべての離着陸を任せてくれる。
今回は雨天のために視界が悪く、滑走路が滑りやすい中でのテイクだったが、彼の指導のおかげで難なくランディングできた。
「機長のおかげです」
「なに言ってるんだ。今回、俺はほぼ指導してないだろう。上月くんの腕だよ。自信持ちたまえ」
こうして自信を持たせてくれるところも、信頼すべき良き上司であると思う。
「お疲れさまです」
フライトを終えて飛行機から降りる旗本と悠人に、CAたちからねぎらいの言葉がかけられた。
みな約十三時間という長丁場の勤務を感じさせない美しい笑顔だ。彼女たちは接客のプロだな、と感じる瞬間である。
「お疲れさま」
旗本とともに彼女たちをねぎらいステイ先のホテルに向かう。
「ところで上月くん、最近なにか良いことがあったのか?」
「は?」
どうしてそんなことを? という意味を込め、悠人は疑問符を返した。
「ここ数か月の間、浮かない顔をすることが多かったが、今は明るい顔をしてる」
「そうですか? 特別なにも変わってないですが……」
旗本の言葉で穂香の姿が浮かんだが、知らぬふりをしてかわした。
「そうかな?」
それでも旗本は騙せないらしい。ニヤッと笑ってポンポンと悠人の肩をたたく。
「照れなくてもいい。夫婦円満なのは、素晴らしいことだよ」
気づかないうちに耳を赤くしていたことを知り、悠人は手のひらで前髪をクシャっとさせた。
穂香の存在が悠人の心を穏やかにしていることは事実である。それに、家に帰る楽しみもできた。
清美が見つからなければ問題は解決しないというのに、心が軽くなっている。
正確に言えば夫婦ではない。
だがここで否定するのは対外的に不味い気がする。この会話が誰かの耳に入り、尾ひれがついて世間に広まっていくことがありえるからだ。
イメージを大切にする社長の方針から外れるのは困る。
「ああ、そうですね……おっしゃる通りです」
あいまいな表現にとどめておいたが、後ろにいるCAたちからちょっとしたどよめきが起こった。彼女たちに聞こえたらしい。
夫婦円満と思われすぎても、また、困惑するのだが。
この先難しい選択を迫られることになるかもしれない。だが、穂香を悲しませるようなことはしたくない。それだけは、誰がなんと言おうと、絶対である。
駅からホテルに向かう道すがら穂香と出会った場所を見つけ、悠人はふと微笑む。
──そういえば、あのときの天使をリビングに飾っていたな。
誰かへの土産ではなく自分のために購入したのだな、と思い、同時に結婚詐欺事件のせいで友人たちと疎遠になったのは事実なのだと、改めて犯人を嫌悪したのだった。
でもそれがなければ穂香と出会えなかっただろう。少々複雑である。
彼女を救った当時を思い出せば、勘違いで失礼なことをしたことと、そのあとの楽しかった時間が容易によみがえってくる。
あの置物と似たものを見つけたら、土産にしようか。きっと喜んでくれるはずだ。
穂香の笑顔を胸に浮かべて頬を緩める悠人を、旗本が穏やかな目で見ていた。